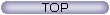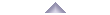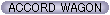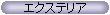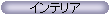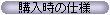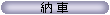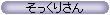|
2008.01.07 いきなり、完成した写真からです。 MC前のモデルにMC後のヘッドライトユニットが 付けられるのか? 付かなかったら発注しちゃったこの部品達はどうする? 等という懸念を持ちながらも・・・ 結論としては、ヘッドライトユニットに付随する 殆どの部品の形状に違いがあり、 意外と多くの部品を発注する必要があるのですが、 基本的なヘッドライトユニット形状はほぼ同じなので そのまま取付けられました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
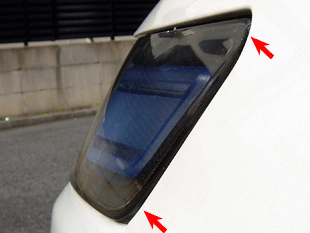 |
外観で形状の違いが目立つのはこの部分です。 上部はMC前の部品と同じく、フェンダー面から 2ミリ程度内側の位置に収まるのですが、 下端が全体に3ミリ程度はみ出しています。 ヘッドライトの前部は元々、MC前後共に 上部がボンネットに埋まるようになっており、 下部が出気味な構造なので、サイド部分の下端が はみ出していてもデザイン的には破綻していません。 違和感は全くありませんし、 バンパーとの接合部が隠れるので 却って綺麗に見えます。 以下、発注した部品です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
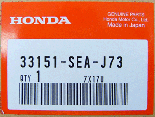 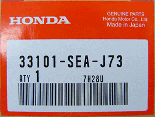 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
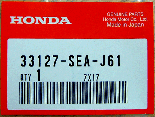 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
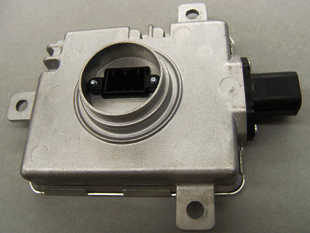 |
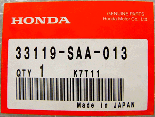 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
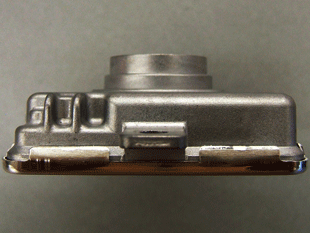 |
ヘッドライトユニットへの接合部にフランジが付きました。 ヘッドライトユニットへの取付けネジ3本は 前の物をそのまま外して使いました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
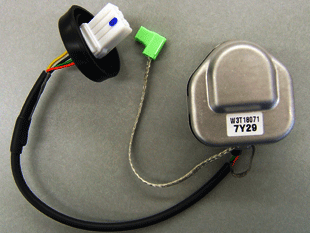 |
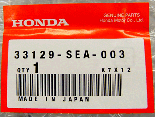 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
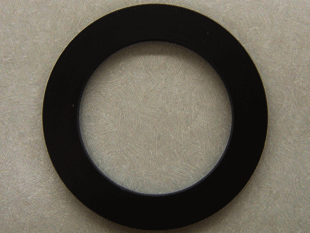 |
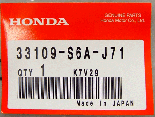 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
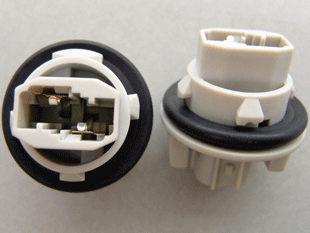 |
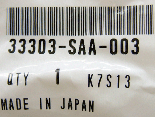 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
購入した着色電球に記載されていた 端子位置の違いです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
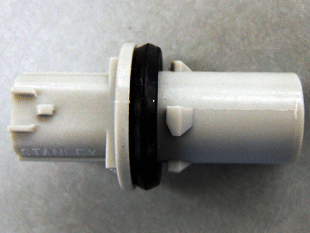 |
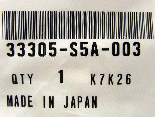 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
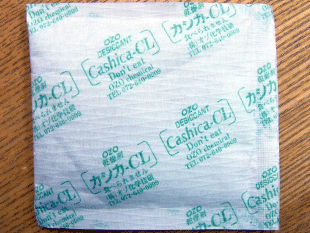 |
ヘッドライトユニット内の乾燥剤は MC後には付いていません。 ヘッドライトユニットの箱の中には1個入っていますが、 これを取り付けろという意味ではないと思います。 以前、MC前のヘッドライトユニットを発注した時には ロービームの横に1個貼り付けられていて、 箱の中にもう1個入っていました。 乾燥剤は何れも株式会社 オゾ化学技研の商品でした。 ホームページ上では再放出しないと記載されていますが、 元々、気密状態ではないので、充分に飽和してしまった 上に、ロービームの真横で高温になれば当然、水分を 放出してしまうのだと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
ウインカーの電球は以前の透明な電球が使えないので これを2個購入しました。 ロービーム(D2S)、ハイビーム(H1)、車幅灯(T10)は そのまま移植できます。 基本的には、交換に必要な部品は以上です。 後は、当然、弄ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
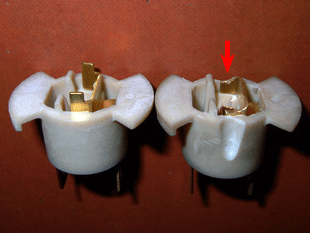 |
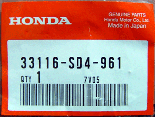 ×2個 ×2個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
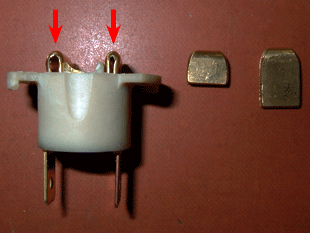 |
上下にある接点を削っちゃうと H1バルブのマイナス側との接続が出来なくなるので 1mmの黄銅板で端子を作ります。 この接点はH1バルブをヘッドライトユニットに押しつける 機能も兼ねているので端子の高さは削る前の 上下の接点より低くならない様に揃える必要があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
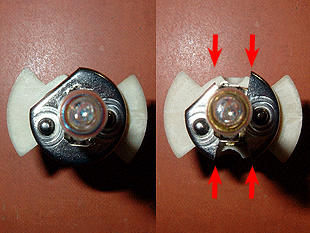 |
H1バルブの上下をダイヤモンドカッターで切断します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
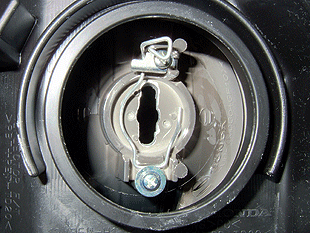 |
ヘッドライトユニットのハイビーム部分の上下を H1サイズ+6mmになるようにヤスリで広げます。 ここに直径5mmのウェッジ球が入ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
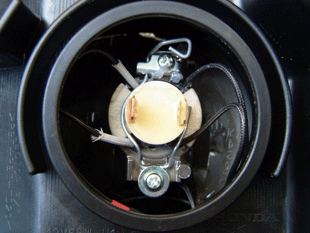 |
前作と同様に1.4Wのウェッジ球を取付け、 フォグライトでも使用した耐熱コードで配線します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
1.4Wウェッジ球先端に銀色の耐熱ペイントを 塗ることにより前方への光をある程度遮断出来ます。 適当な皿に少量吹き出しておいて、 爪楊枝でペタペタと頭の丸い所だけに塗っていきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
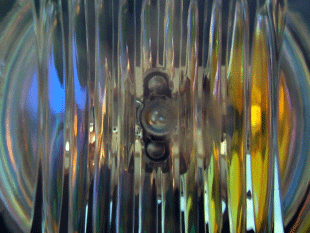 |
前から見るとこうなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
 |
夜はこんな感じです。 前作よりも明るくなりました。 今回、車幅灯をLEDにするのはやめました。 前作で車幅灯をLEDにしたのですが、夏の深夜に峠道を ハイビームで1時間位走ったらヘッドライトユニット内に 熱がこもり、点灯しない部分が数箇所出来てしまい、 その後も白色LEDからぼちぼちと消えてしまったので 今回はオレンジ色の電球を入れるだけにしました。 温度が下がると点灯することもあるので、多分LEDの モールドに使用されているアクリル等が熱で膨張した 時に、チップにボンディングしているアルミ線を 引き千切っちゃったのではないかと思われます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
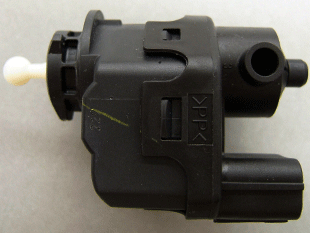 |
取り敢えず、普通通りに光軸を調整しましたが、 MC後のヘッドライトユニットにはレベライザが 標準で付いています。 折角付いているのだから機能させずに放っておくのは 勿体ないと思うので、配線してみます。 電球と同様に捩じって外してみるとこんな感じです。 品名はヘッドライトアジャスタモータです。 単体で発注すると高価な部品です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
HELLA製、Made in Germanyの文字があります。 007 878の数字がHELLAの商品番号になるようで、 ネット検索すると色々な車種用の部品が出てきますが、 これと全く同じ物は見当たりません。 このユニットと同じ物は、車体設計時に 光軸の自動調整や運転席からの手動調整機能を 想定していなかった車種に使われているようで、 アコード、アコードワゴン、旧インスパイア、エリシオン、 旧ステップワゴン、レジェンドに使われています。 シビックやストリーム、クロスロード等には別のユニットが 採用されており、コネクタ形状も違います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
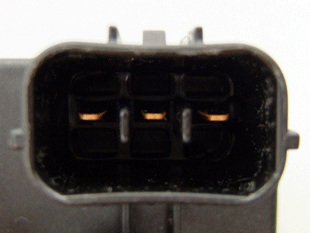 |
この、コネクタに適合する防水コネクタを 探しているのですが見つかりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
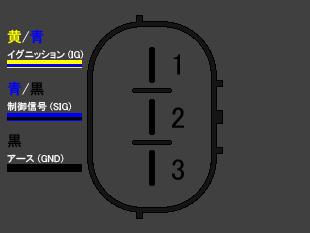 |
配線は左図のようになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
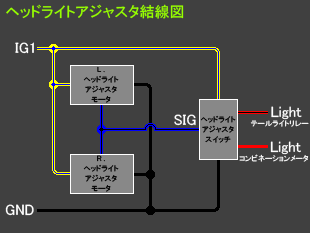 |
オートレベリングにはセンサやコントローラが必要ですが 手動調整ならば12Vとアースを繋ぎ、 信号線を運転席まで配線をしてしまえば2000ccモデル 等に使われている手動調整用のスイッチを付けるだけで 制御できます。 エンジンルームから運転席までの配線で、 水漏れせずに楽な場所を探さなければなりません。 助手席側のドア辺りはどうかなっと考えています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
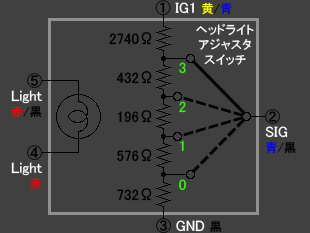 |
ヘッドライトアジャスタスイッチの回路です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
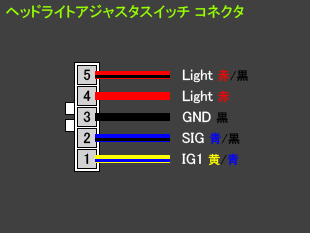 |
コネクタはディーラーには無かったので、 類似したものを大須で購入します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
2008.01.13
スイッチ部分を購入しました。
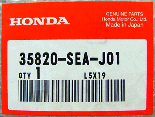 |
|||||||||||||||||||||||||||||
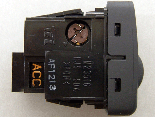 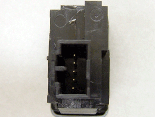 |
側面と背面です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
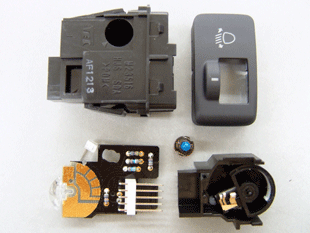 |
中身を出してみました。 ぼちぼちと、配線してみたいと思っています。 2008.02.22 エンジンルームから助手足元迄の配線をしました。 リアフォグの配線と一緒に配線したので、 詳細は「リアフォグ」に記載しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
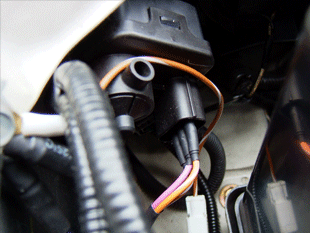 |
20080323 室内からのIGとSIGの線を防水コネクタ経由で接続し、 GNDは最寄りのアースポイントに共締めして 左側の配線が出来ました。 右側への配線は防水コネクタの手前で 分岐してあります。 この部分のコネクタが入手出来なかったので ピンを差し込んで、ピンごと熱収縮チューブで 覆ってあるだけですが多分、大丈夫でしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
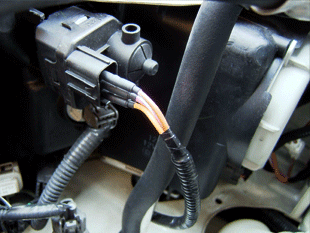 |
右側へはラジエータの前を経由して配線しました。 こちらも、アースは最寄りのアースポイントに 共締めしました。 後はコルゲートチューブを巻いたらエンジンルーム側は 出来上がり。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
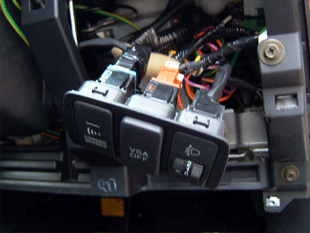 |
スイッチ周りの配線をハンダ付け。 配線がごちゃごちゃしてきました。 Lightの+と−は隣にあったVSAスイッチから分岐。 スイッチとアジャスタモータへのIG信号は 「電源について」を参照して下さい。 エンジンをかけて、ヘッドライトを点灯して つまみをグリグリ。 動く動く! スイッチが固定されていませんが、動作確認OK。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
2008.04.05 デッドニング等の為に外してあった ドライバインストルメントロアカバーを戻して完成。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
光軸はヘッドライトユニット取付け時に調整した位置を
「0」として下方向に「1」「2」「3」と下がっていきます。
調整の目安は以下の通りです。
写真は、水平な場所で壁面から約10m離れて撮影しました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
 |
連続して目盛を動かすとこんな感じに動きます。 0から1は動きが大きく、 1から2は動きが小さいのがわかりますか? 重量バランスに合わせて調整されているようで、 各目盛の移動間隔は均等ではありません。 |