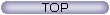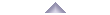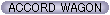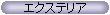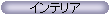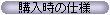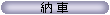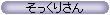|
2005.01.10 ハイビームを交換しました。 Bosch Thunder Moon H1 55W 高効率 マルチコートの黄色です。 |
||||||
 |
2005.11.15 ハイビームを、また買って来ちゃいました。 IPF X13 H1 60W 高効率 マルチコートの黄色です。 60Wという魅力的な数字に惹かれ、購入しましたが、 黄色は流行らないらしく、カタログ落ちしています。 これで一寸遊んでみようと思っています。 2006.08.15 これ、あまり明るく感じられません。 元のBoschに戻そうかな。 |
||||||
 |
1.2Wのウェッジ球(メータや灰皿照明に使われるもの)も、 買ってきました。 |
||||||
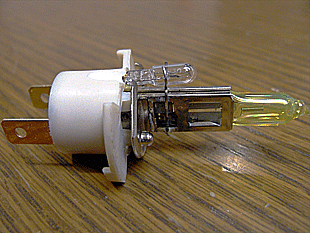 |
2005.11.20 ステーを鑞付けして、2階建てを企んでいます。 バルブに近いので普通にハンダ付けしたのでは 溶けちゃいます。 気に入らないことに、フラックスを付けてもウェッジ球の リード線に半田も鑞も乗りません。 スポット溶接するつもりです。 ちなみに、ここにLEDを使うと、ハイビームを点灯したときに 盛大に煙を出しながら燃えます。 LEDのモールド材は、耐熱樹脂ではありません。 |
||||||
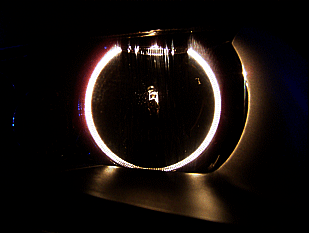 |
ヘッドライトユニットのハイビームの上側を少し削って 中に入れてみました。 車幅灯に結線すると、こんな感じに点灯します。 BMWのエンジェルリング風? 一寸暗いのですが、これ以上の明るさを望むと、 電球のサイズが大きくなっちゃうのと、 電球の寿命が縮むので諦めます。 |
||||||
 |
2005.08.01 ロービームを交換しました。 PIAA HH87 プラズマイオンイエロー D2S 3000Kです。 マルチコートの黄色って商品は現状では これしか選べません。 バルブに黄色い色がついている物よりも透過効率が 良さそうなので選びました。 昔のPIAAって球が切れやすいイメージがあるので、 ちょっと怖い・・・ |
||||||
 |
2005.08.06 正面から見るとこんな感じ。 霧の濃い日だったので、光の拡散状態が見えます。 普通のHIDでは、真っ白に、前が見えなくなる程、 フレアが広がります。 ましてや、最近流行の青いHIDは霧が出たら前、 全く見えなくなっちゃうんじゃぁないのかなと思います。 |
||||||
| 2005.08.07 コンクリートの壁面から約15メートル離れて 車内から点灯状態を撮影しました。 左の動画を再生してみてください。 |
|||||||
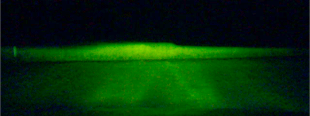 |
点灯直後は青が混じって緑色に見えます。 | ||||||
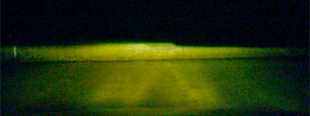 |
時間の経過と共に黄色になりますが、 少し緑色が残ります。 蛍光色の黄色っていう感じです。 |
||||||
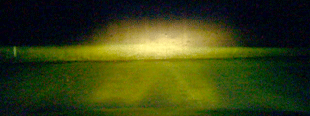 |
ハイビームとの併用です。 ハイビームは左右へ広がっていません。 |
||||||
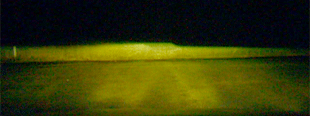 |
フォグとの併用です。 フォグは左右の路面に広く照射されています。 |
||||||
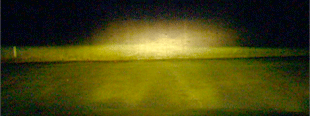 |
ハイビーム及びフォグとの併用です。 満艦飾状態です。 |
||||||
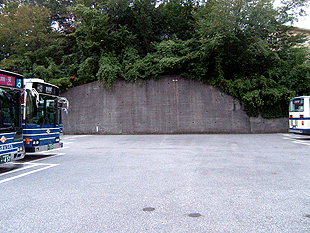 |
2005.08.12 昼間の撮影場所です。 壁面があまり綺麗じゃないのですが、 撮影に適した場所ってなかなかありませんね。 |
||||||
 |
こうやって見ると、黄色いことはあまりわかりませんね。 対向車からは普通のハロゲン球のプロジェクタライトに 見えるかも。 普通の白いハロゲン球と比べると、輝度は高いけれど 色温度はあまり変わらないんです。
|
||||||
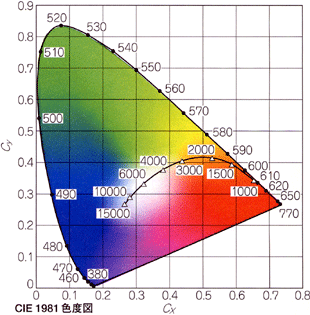 |
ご参考までに、色温度と波長の図です。 外周部の380〜770は単波長光の色相を示す波長です。 波長 単位:ナノメートル(nm) 虹に代表される、人間の目に見える色を表しています。 380nm以下は紫外線、770nm以上は赤外線です。 もっとずっと波長が長くなると電波、更には音波になります。 中央部の1000〜15000は色温度です。 色温度 単位:ケルビン(K) 鉄を加熱すると赤黒い色になり、更に温度を上げると赤く、 そしてオレンジから黄色、白くなることや、 ガスの炎が、酸素不足で燃焼温度が低い時は、 ライターの炎のように赤っぽく、 適正な酸素が供給されて温度が高くなると ガスコンロの炎のように青く見えることを指して、 色と温度の関係を結びつけた表現の単位です。 6000K付近が最も色みのない、白く見える部分です。 太陽光は4800K、平均的な屋外の昼光は6500K程度だそうです。 実際の温度や明るさではなく、色の単位として認識して下さい。 CIEカラーモデルに関する解説は、 Adobe SystemsのTechnical Guides Web Siteを ご覧頂くと良いと思います。 |
||||||
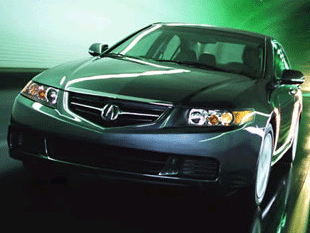 |
この画像、カナダのACURA TSXの ウェブサイトにありました。 ロービームが黄色く見えませんか? 他の写真では白いのですが、 これだけは黄色に見えます。 何かが、単に映り込んでいるだけ? 伝統的にヘッドライトが黄色だったフランスでも、 最近の車はどれも白くなっているようですが、 カナダってフランス語圏でもあるので・・・? |
||||||
 |
2006.06.25 雨の中を出かけて、帰って来たら左のヘッドライトユニット がこんなに曇っていました。 2005年10月にぶつかった猫の影響で、 ヘッドライトユニットにもヒビが入っていたようです。 ディーラーに行ったら、即、「猫の祟り」と 片付けられちゃいました。 フォグは交換したのですが、実用上差し支えなかった為、 バンパーはまだ交換していなかったので、ヘッドライト ユニットの下の方の状態を確認していませんでした。 高圧回路に水が入ると厄介なので、ヘッドライトユニットと バンパーの交換準備に取り掛かります。 ディーラーで、2006.07.07にバンパー交換の予約を しました。それまでに準備しなくっちゃ。 |
||||||
 |
2006.06.26 デッドニングを優先して作業していたので、思いっきり 後回しになっていたのですが、慌てて作業を始めました。 まず、車幅灯にLEDを入れます。 上向きと、横向きにLEDを並べ、奥の方には前向きに LEDを配置しました。 |
||||||
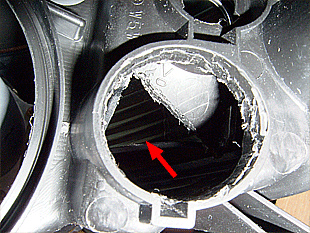 |
2006.06.27 納車前から購入してあったEuroR用ヘッドライトユニット (リフレクタの周りの銀色のメッキ部分がスモーク塗装されて いますが、はっきり言って、殆ど違いがわかりません) の、スモールの下をくり抜きます。 ここに、上記の棒状に並べたLEDを入れました。 元々、ここには21Wクラスの電球が入る様な構造に なっているのですが、何処の国向けの仕様なんでしょう かね?用途のよく判らない部分です。 |
||||||
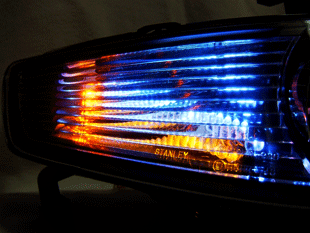 |
妙に青っぽく写っちゃいましたが、 LEDは横向きに黄色、前向きにオレンジ、上向きに白を 使っています。これって違法? 橙か白の単色じゃなきゃだめだったっけ? 両方はダメ? 遠くから見れば混ざって見えるかな? |
||||||
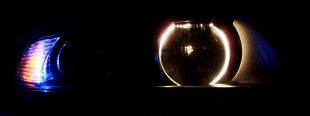 |
右側ヘッドライトユニット全体を前方から見た状態。 変? |
||||||
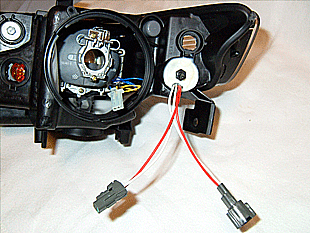 |
配線は、防水コネクタで車幅灯から分岐し、 ここからフォグライトにも分岐するようにしました。 ロービーム右下に見える白いコネクタは、 ハイビームの上にある電球に接続する為の物です。 |
||||||
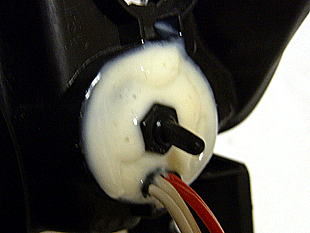 |
防水スイッチでOFFにできるようにしてあります。 これを左右とも切れば、正規の車幅灯と、 フォグライトの部分だけの点灯になります。 |
||||||
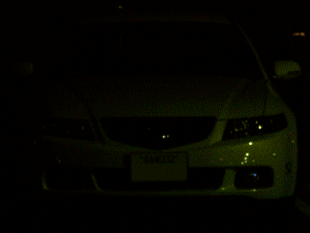 |
200607.07 バンパー交換時にヘッドライトユニットも交換しました。 夜、点灯状態を撮りましたが、水銀灯の照明が当たって、 緑色がかってしまいました。 三脚で固定して、約15mからマニュアルで撮影しました。 遠くから見れば問題ないかも? |
||||||
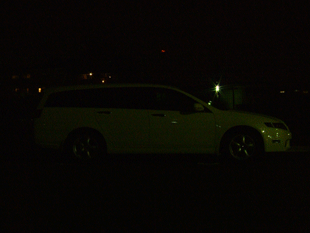 |
横からはこんな感じです。 Motion GIFで作ったので画像容量が 大きくなってしまいました。 |
||||||
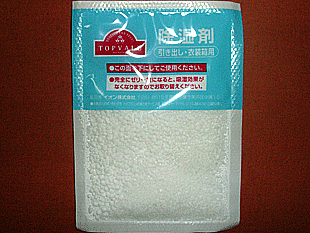 |
2006.07.14 交換直後から、左右共内側に曇りが出ていたのですが、 エステー化学の塩化カルシウム系乾燥剤の小さな物を ロービームの後ろに入れておいたら曇らなくなりました。 元々、ヘッドライトユニット内には、乾燥剤が入っている のですが、1年半も室内に置いてあったので、吸湿して しまっていたようです。 |
||||||
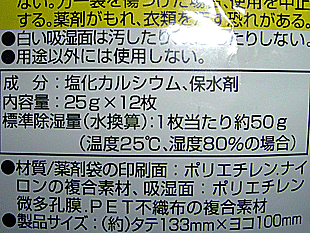 |
塩化カルシウム系の乾燥剤は、 シリカゲルや、粘土系の乾燥剤よりも吸湿能力が 数十倍高いので、乾燥剤を乾燥させる為には最適です。 折角吸収した水分がエンジンルームやロービームの 熱で再放出されるのを防ぐ為に、エンジンをかける前には 外して密封容器に入れました。 ジェル状の部分が出てきたら吸水能力が劣り始めるので 新しい物と交換して下さい。 この状態でも、普通の用途には充分な除湿能力なの ですが、乾燥剤を乾燥させる為には能力不足になります。 |
||||||
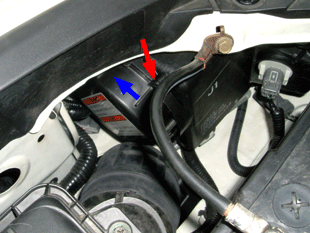 |
赤矢印の部分にある弄り止め付きのトルクスネジを 外して青矢印方向に回すとロービームのカバーが 外れます。 カバーの周りに付いているパッキングを傷つけない様に して下さい。 |
||||||
 |
中に乾燥剤を入れ、元に戻しました。 トルクスネジは、このカバーが回らないように付いている だけなので、強く締める必要はありません。 曇りがなくなるまでの間は、カバーを何度か外す必要が あるので、トルクスネジは作業が完了するまで外した ままでも支障が無いと思います。 乾燥剤は不織布側を前に向けて下さい。 こちらの面から吸湿します。 |
||||||
 |
2007.02.16 国土交通省リコール届出番号1826で、 ヘッドライトユニットの曇り対策が出てきました。 ディーラーには既に部品があるそうなので、 早速「止め金具」を付けて貰う予定です。 2007.02.18 ヘッドライトフックプレート(06336-SEA-305)を片側に2個 ずつ、合計4個付けて貰いました。 ボンネットのシールがヘッドライトユニットの前端を押して、 接合部が外れてくるのだそうです。 柔らかいブチルゴムで、接合部を覆っていたのですが、 洗車後等に曇っていたんですよ。 これで直るかな? |
||||||
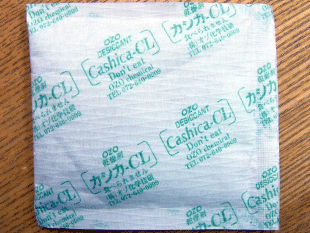 |
これが、ヘッドライトユニット内に入っていた乾燥剤です。 MC後のヘッドライトユニットには付いていません。 乾燥剤は株式会社 オゾ化学技研の商品でした。 ホームページ上では再放出しないと記載されていますが、 元々、気密状態ではないので、充分に飽和してしまった 上に、ロービームの真横で高温になれば当然、水分を 放出してしまうのだと思います。 もしかすると、この吸湿してしまった乾燥剤を 外した方が曇りにくいのかもしれません。 紙袋がブチル系の両面テープで張り付けられているので 力を入れ過ぎて破ってしまわないように気を付けなければ なりませんが・・・ ヘッドライトユニット内で破れると最悪の事態が・・・ 怪しい白い粉まみれになります。 |
||||||
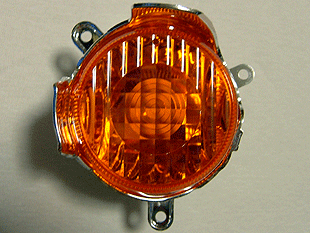 |
2007.06.26 ディーラーのゴミ箱に入っていた傷の付いたアコードの ヘッドライトユニットを貰いました。 ウインカーのオレンジ色のレンズって外せないのかなと 思っていたので、バラバラにしてウインカー部分を 外してみました。 |
||||||
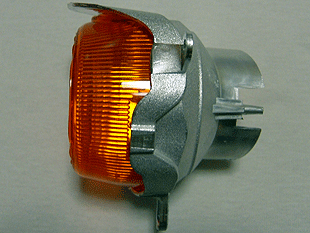 |
これだけ奥行きがあると裏側からつついた程度では 到底外れませんし、レンズを止めてある爪を外しても 後ろ側に引きずり出す空間はありません。 |
||||||
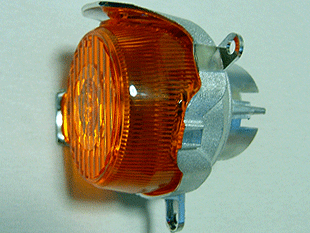 |
内側から、下の方にあるネジを一つ外して、 ヒートガンで温めながら表側の透明なカバーを外せば 取り出せますが、戻す時に余程しっかりと 防水しておかないと雨の日や洗車時に簡単に曇るように なってしまいます。 |
||||||
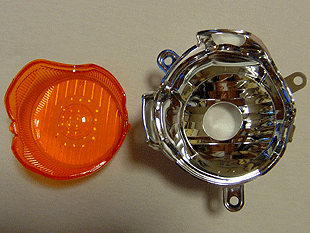 |
安直な手段が無いことがわかったので、 オレンジ色のまま使うことにしました。 |
||||||
 |
2007.12.19 岡崎に仕事に行った時、 3台隣に止まっていたアコードワゴン。 右のヘッドライトだけ、見事に曇っていました。 この位酷いとロービームは点灯しないんじゃないかな? |