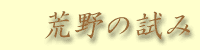 |
(第4回)
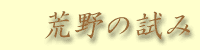 |
(第4回)
|
|
|
今日は、マタイの福音書4章1節〜11節に記されている、イエス・キリストが、荒野で、悪魔からお受けになった試みのうち、5節〜7節に記されている、第二の試みに焦点を合わせてお話しいたします。 五節では、 すると、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせた。 と言われています。この「聖なる都」は、エルサレムのことです。悪魔はイエス・キリストをエルサレムにある主の神殿に連れて行って「神殿の頂に立たせた」のです。(1) 六節にありますように、悪魔は、 あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。「神は御使いたちに命じて、その手にあなたをささえさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。」と書いてありますから。 と言いました。 この第二の試みに限りませんが、イエス・キリストにとって、この悪魔の言葉がどのような意味において試みとなったのかは、私たちには分かりにくいところです。それで、これに対するイエス・キリストのお答えを見ることによって、その意味を判断したいと思います。 イエス・キリストは、七節にありますように、 「あなたの神である主を試みてはならない。」とも書いてある。 とお答えになりました。 このことから、この悪魔の試みは、イエス・キリストに「あなたの神である主を試みてはならない。」という神である主の戒めに背かせて、主を試みさせることを狙ったものであったことが分かります。 「あなたの神である主を試みてはならない。」という戒めは、申命記6章16節からの引用です。そこには、 あなたがたがマサで試みたように、あなたがたの神、主を試みてはならない。 と記されています。 「あなたがたがマサで試みたように」というのは、出エジプト記17章1節〜7節に記されている出来事を指しています。そのことについて簡単にお話ししましょう。 イスラエルの民が主の力強い御手によってエジプトの奴隷の状態から贖い出され、最終的にエジプトの地を脱出したことを記す記事は出エジプト記15章21節で終わります。 続く15章22節からは、イスラエルの民の、主に対する不信仰から出た「つぶやき」の記録です。 15章22節〜27節には、マラという所の水が「苦くて飲むことができなかった」ので、民がモーセに向かってつぶやいたことが記されています。これに対して主は、モーセを通してそこの水を飲むことのできるものに変えてくださいました。そして、その機会を捉えて、主の戒めに従い主を信頼すべきであることをお教えになりました。 続く16章全体には、シンの荒野において、イスラエルの民が、食べ物がないので飢えて死んでしまうと言って、つぶやいたことが記されています。 これに対しても、主は、マナとうずらを与えてくださって、イスラエルの民を養ってくださいました。それは一時的なことではなく、35節に「イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで、四十年間、マナを食べた。」と言われているように、主は、荒野の旅の間ずっとイスラエルの民を養い続けてくださいました。 このことが、第一の試みにおいてイエス・キリストが引用された、申命記8章3節の それは、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あなたにわからせるためであった。 という主の教えの根底にあります。 これら二つの出来事は、イスラエルの民の不信仰から出たつぶやきから始まっています。彼らは、主が力強い御手をもって自分たちをエジプトの地から導き出してくださったことを経験していますから、どのような場合においても主を信頼し、その御手に頼るべきでした。 しかし、神である主は、そこから始まる旅路の初めにおいて、イスラエルの民の不信仰を忍んでくださり、かえって、彼らを教える機会としてくださいました。そして、主が導いてくださる道に従う時には、荒野を通っての旅のように、人の目には不可能と見えることであっても、主がともにいてくださって、その道において支え続け、目的の地まで導いてくださることを教えてくださいました。 そのように主が忍耐深く教えてくださった後は、イスラエルの民は「ともにおられる主」を信頼して、荒野の旅路を進むべきでした。 しかし、それに続く、出エジプト記17章1節〜7節においては、レフィディムで宿営した時、そこに飲む水がなかったために、イスラエルの民は再びつぶやき、モーセと争って、モーセを石で打ち殺そうとするほどになりました。 それは、もう弁解の余地のないほどの、イスラエルの不信仰の現われでした。このことのゆえに、そこの地名は「マサ、またはメリバ」と名付けられました。「マサ」は、新改訳欄外注釈にありますように「試み」という意味であり、「メリバ」は「争い」という意味です。7節では、 それで、彼はその所をマサ、またはメリバと名づけた。それは、イスラエル人が争ったからであり、また彼らが、「主は私たちの中におられるのか、おられないのか。」と言って、主を試みたからである。 と言われています。 そして、このことが後の世代においてもイスラエルの民の不信仰の典型的な事例として覚えられることとなって行きます。それが、先ほど触れた申命記6章16節の、 あなたがたがマサで試みたように、あなたがたの神、主を試みてはならない。 という戒めに表わされています。 また、詩篇95篇8節、9節では、 メリバでのときのように、 荒野のマサでの日のように、 あなたがたの心をかたくなにしてはならない。 あのとき、あなたがたの先祖たちは すでにわたしのわざを見ておりながら、 わたしを試み、わたしをためした。 と言われています。 もう一度、出エジプト記17章7節を見てみましょう。 それで、彼はその所をマサ、またはメリバと名づけた。それは、イスラエル人が争ったからであり、また彼らが、「主は私たちの中におられるのか、おられないのか。」と言って、主を試みたからである。 ここでは、イスラエルの民が「『主は私たちの中におられるのか、おられないのか。』と言って、主を試みた」と言われています。 彼らは、神である主の力強い御手による救いの御業に接していました。また、13章21節、22節に、 主は、昼は、途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は、彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んで行くためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。 と言われていますように、主の御臨在のしるし 主がともにいてくださることを表わすしるしに常に接していましたし、実際、毎日マナによって養われておりました。 それなのに、目前の問題が迫ってきた時に、主がともにいてくださることを信じて主に信頼する代わりに、モーセと争い、彼を殺そうとしました。 そのことが、「『主は私たちの中におられるのか、おられないのか。』と言って、主を試みた」と言われています。つまり、イスラエルの民は、主が彼らとともにおられて、自分たちを導いてくださっておられることを信じていなかったので、(見える形としては)自分たちをここに連れて来たモーセと争い、彼を殺そうとしたのです。自分たちの不信仰は、いっさい視野の中に入っていません。 しかし、このようなイスラエルの姿を笑うわけにはいきません。私たちは、荒野のイスラエルよりはるかに優る救いにあずかっています。 出エジプトの出来事さえもその影でしかない、イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いは、私たちにとっては確かな歴史の事実です。みことばによって、私たちの目で見るよりも確かにイエス・キリストの十字架を示されています。しかも、その死によって、罪を赦されているばかりでなく、私たちの間に、また私たち一人一人のうちに御臨在してくださっている、主の御霊が与えられています。 そのような私たちが、目の前に問題が迫って来ますと、「主は私たちの中におられるのか、おられないのか。」と疑い始めます。その問題に対して何の心配もしてはいけない、不安を持ってはいけないということではありません。心配や不安があるなら、なおのこと、その心配や不安を「ともにいてくださる主」にお委ねして行けばよいのです。その経験の中で、私たちの信仰は少しずつ強められて行きます。 このようなことを踏まえて見ますと、イエス・キリストがお受けになった試みの意味が少しずつ見えてきます。 イエス・キリストは、四十日四十夜にわたる断食の後、第一の試みにおいて、「このような荒野においてこのままでいては飢えて死んでしまうから、ここにある石をパンに変えて食べなさい。」という試みをお受けになりました。その悪魔の提案には、そこに主がともにいてくださるという事実が外されています。それは、まさに、荒野において食べるものがなくなったイスラエルと同じ試みです。 イスラエルの民は、主が自分たちとともにいてくださることを信じないで、つぶやきました。 しかし、イエス・キリストは「人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる」という主の教えをもって、主に信頼する姿勢をお示しになりました。人の目に不可能と見える状態にあっても、その荒野に導かれたのが主のみこころであれば、そこに主はともにいて支えてくださるというみことばの約束に従って、主を信頼して待つ姿勢をお示しになりました。 これに対して悪魔は、第二の試みにおいて、 あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。「神は御使いたちに命じて、その手にあなたをささえさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。」と書いてありますから。 と言いました。ここで悪魔は詩篇91篇11節、12節を引用しています。 悪魔は、イエス・キリストの、神である主を信頼して待つ姿勢に付け込んで、詩篇91篇の約束を示し、「神殿の頂」から「下に身を投げ」るよう提案しているのです。 この悪魔の言葉は二つの意味に解釈できます。 一つは、《あなたがそれほどまでに神に信頼していても、神が答えてくれるとは限らないでしょう。ひとつ、ここから「下に身を投げてみなさい。」そうしたら、神が、本当に「神は御使いたちに命じて、その手にあなたをささえさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。」という約束の通りに、あなたを支えてくれるかどうかはっきりするでしょう。万一、支えてくれなくても、「あなたが神の子なら」自分で支えられるから大丈夫でしょう。》というような意味になるでしょうか。 「神が約束の通りにしてくれるか分からないから、ひとつ試してみよう。」という姿勢は、しるしを求める姿勢です。それは、真実な主のみことばを不真実なものとすることです。みことばの約束だけでは疑わしいから、もっと自分に納得できるものを与えてくれるようにと要求することです。自分の不信仰はそのままにして、信じていない自分を納得させるようにと要求することです。 私たちの信仰には、このようなみことばの約束に対する疑いの影が潜んでいます。それで、私たちは、みことばに対する疑いのゆえに、しばしば主を試みてしまいます。「本当に主が私たちとともにおられるのなら、こんなことにはならないはずだ。(あるいは、こうなるはずだ。)」「本当に主が私たちとともにおられるのなら、このようにしてください。」というように、「本当に主が私たちとともにおられるのなら」というのが、その合言葉です。 しかし、これは、私たちにはそのまま当てはまっても、イエス・キリストには当てはまらなかったのではないでしょうか。第一の試みで明らかなように、イエス・キリストのうちには、主のみことばの約束に対する疑いはなく、悪魔もそのことはよく分かっていたはずです。 そうであるしますと、その悪魔の言葉は、《あなたが主のみことばの約束を信じて、主に信頼していることが分かりました。それなら、ひとつ、ここから「下に身を投げてみなさい。」「神は御使いたちに命じて、その手にあなたをささえさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。」という約束の通りに、主はあなたを支えてくださるはずです。》というような意味になるでしょう。「神のみことばに約束されているのだから、やってみよう。」ということです。 これは、一見すると信仰から出ている行いのように見えます。しかし、信仰の本質は、みことばによって示されている、主のみこころに従い続けることにあるのであって、無謀なことをあえてすること自体にあるのではありません。この場合には、イエス・キリストが「神殿の頂」から「下に身を投げ」るべき理由はどこにもありません。 よく言われますように、その当時のラビの教えの伝統の中に、王であるメシヤが来ると、神殿の上に立つという考え方がありました。悪魔がイエス・キリストを「神殿の頂に立たせて、」「下に身を投げ」るように誘ったことには、そうすれば、人々がイエス・キリストをメシヤとして迎えるようになるというような、「下に身を投げ」るための「理由」を生み出すためであったかも知れません。 その点については何とも言い難いのですが、たとえそうであったとしても、その「理由」は父なる神さまのみこころから出たものではありません。 悪魔が引用している、「神は御使いたちに命じて、その手にあなたをささえさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。」という約束は、本来、私たちが主のみことばのうちに示されているみこころのうちを歩む時に、私たちに適用されるものです。 しばしば、悪魔の詩篇91篇の引用の中で、11節の「すべての道で」という言葉が抜けていることから、悪魔は、この約束が主のみこころに従うすべての道での支えと保護を約束していることを、イエス・キリストに意識させないようにしていると言われることがあります。 しかし、このことは、あまり強調されてはなりません。主の約束が主のみこころのうちを歩む者に適用されるということは、詩篇91篇のこの約束に限らず、みことばの一般的な原則であり、イエス・キリストは、まさにそのことを第一の試みではっきりさせたばかりです。ですから、悪魔は、イエス・キリストが、このような小手先のごまかしにだまされてしまうとは、決して思っていなかったはずです。 いずれにしましても、信仰によって、主のみこころに従って歩んで行く時、私たちは、しばしば困難に直面いたします。そのような時に、みことばの約束に基づいて主を仰ぎ、主を待ち望むことは、信仰の正常な姿です。確かに、主は、私たちの心をご自身に向けてくださるために、困難な問題を用いてくださいます。 しかし、たとえば、「主は私たちの必要をすべて満たしてくださる」というみことばの約束があるからということで、浪費をすることは、主を試みることです。暴飲暴食や不節制な生活を続けながら、主は私を守ってくださると信じるのは、信仰の表現ではなく、主を試みることに他なりません。 私たちが、無謀なことをしたのに主が守ってくださったのは、主の深いあわれみによることであって、それが主を試みることであることには変わりありません。 ここで悪魔がイエス・キリストを試みた時には、みことばの約束を盾に取って、主のみこころとは関係なく無謀なことをすることを求めたと考えられます。 しかし、私たちとしましては、みことばの約束を盾に取って、主のみこころを無視した無謀なことをすることも、みことばの約束だけでは不十分であるといって、それ以上の「しるし」を求めることも、主を試みることであると、心に銘記しておきたいと思います。 そして、ただそのようなことを避けるというだけでなく、むしろ積極的に、みことばを通して示されている、主のみこころを探り求めつつ、みこころに従って歩む時には、どのような場合にも、主が、約束の通りに、私たちとともにいてくださることを信じて歩みたいと思います。また(その逆にということになるでしょうか)、主が約束の通りに私たちとともにいてくださることを信じて、みことばを通して示されている、主のみこころに従って歩み続けたいと思います。 (1) これが、実際に、悪魔とイエス・キリストが荒野からエルサレムに行ったということなのか、それとも、このすべては幻の中で起こっていることなのか、はっきりしません。 |
|
|
||