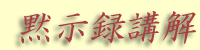
|
(第170回)
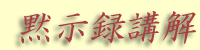
|
|
説教日:2014年7月27日 |
|
まず、ユダヤ人の聖書学者であるウンベルト・カッスート(Umberto Cassuto)という方の「いのちの木」についての見解を紹介したいと思います[創世記への注解(英訳)109頁]。 カッスートはいのちの木について論じる中で、創世記3章22節に記されている、 神である主は仰せられた。「見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。」 という神である主のみことばに注目しています。そして、ここに記されていることから、いのちの木が、その実を食べる人に永遠のいのちを与える奇跡的な力をもった木であるとしています。さらに、これと同じようなものがイスラエル以外の国々においても見られるとして「いのちの草」の例を挙げています。 このような、いのちの木そのものの中に永遠のいのちを与える力があるという考え方には問題があります。 第一に、すでに繰り返しお話ししてきましたように、聖書のみことばは、神のかたちに造られている人のいのちの本質は契約の神である主との愛の交わりにあると教えています。カッスートの主張はこのようなみことばの教えと対立しています。 エデンの園は、神である主がそこにご臨在されて、そこに置かれた人をご自身との交わりに生きることができるようにしてくださるために、神である主が設けてくださったものです。 そのように、神である主の御臨在の御許において、神である主との愛の交わりに生きることにあるいのちはとても豊かないのちでした。人のいのちの豊かさが具体的にどのようなものであったかは、創世記2章の記事からうかがうことができます。 人はエデンの園で、神である主の御臨在に伴う豊かな賜物としての「見るからに好ましく食べるのに良いすべての木」を与えられていました。また、19節に、 神である主は土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形造り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、人のところに連れて来られた。人が生き物につける名はみな、それがその名となった。 と記されていますように、生き物たちと出会って親しい関係を築きました。人が生き物たちに名をつけたことは、生き物たちそれぞれの特質を観察して理解し、その特質を表す名をつけたということを意味しています。それによって、人は一つ一つの生き物との関係を築いていきました。 さらに、18節に、 神である主は仰せられた。「人が、ひとりでいるのは良くない。わたしは彼のために、彼にふさわしい助け手を造ろう。」 と記されており、21節ー23節に、 神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして、彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉をふさがれた。神である主は、人から取ったあばら骨をひとりの女に造り上げ、その女を人のところに連れて来られた。人は言った。 「これこそ、今や、私の骨からの骨、 私の肉からの肉。 これを女と名づけよう。 これは男から取られたのだから。」 と記されているように、「彼にふさわしい助け手」との出会いにおいて、神のかたちとして造られている人格的な存在としての愛の交わりを始めました。あらゆる生き物たちに名をつけて、それらの生き物たちとの関係が築かれましたが、人は自分の愛のすべてを表すことも、その愛をそのまま受け止めてもらうこともできませんでした。「彼にふさわしい助け手」に出会って初めて、そのような愛の交わりができるようになりました。 また、先ほど触れましたように、人はエデンの園を耕していました。豊かに潤っている園では植物はどんどん育ちますから、人が手入れをしていかないとジャングル状態になってしまいます。それで、人は園にあるそれぞれの植物の特性を理解し、それにふさわしい手入れをしていたと考えられます。これによって、豊かに潤っているその土地をさらに実り豊かなものとし、より豊かな収穫をもって生き物たちのいのちがさらに豊かに育まれるようにしたと考えられます。人が生き物たちと出会ってそれぞれに名をつけたことは、生き物たちとの交わりの中で生き物の本質的な特性を理解し、その名をつけたということです。そして、名をつけるということは、権威を発揮することですが、この場合は、人が生き物たちの本質的な特性理解し、それが生かされるようにお世話をすることであったと考えられます。 このように、エデンの園における人のいのちは、神である主が造られたものと深く関わりつつ、その本質的な特性を理解し受け止めたうえで、さらにそれにかかわっていくというように、神の創造の御業を受け継ぐような形で発揮されていたと考えられます。それは神のかたちに造られて歴史と文化を造る使命を委ねられている者としてのいのちの営みでした。そのすべての核心に、そこにご臨在してくださっている神である主への礼拝があり、礼拝を中心とした神である主との愛の交わりがありました。 神のかたちに造られた人のいのちは、このように豊かなものでした。このように豊かな人のいのちが「いのちの木」という名がついているとしても、そのような木そのものによって支えられるということは考えられないことです。 第二に、今お話ししたことから分かりますように、人のいのちは単なる力ではありません。また、動物的ないのちでもなく、神のかたちとしての人格的な特性をもっているいのちです。その本質的な特性は愛であり、倫理的な面があり、道徳的な性格がありますし、知恵や真理の把握とも結びついています。人のいのちは単なる生命力の持続ではありません。 食べるのによい木であったと考えられる「いのちの木」そのものには、人の肉体的ないのちを支える力はあったでしょうが、愛を本質的な特質としている神のかたちとしての人のさまざまな人格的な特性そのものを支える力はありえません。 第三に、いのちの木そのものに、人に永遠のいのちを与える力があるという考え方は、神である主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまっている人間の発想から生み出されたものです。そのような考え方は、カッスートが指摘していますように、イスラエル以外の国々の神話に見られますし、東洋の不老長寿の薬というものに、同じ考え方が見られます。それは神さまに対して罪を犯して、御前に堕落してしまっている人が考え出したことであって、神である主が「いのちの木」をそのようなものとしてお造りになったのではありません。 そのような考え方は人のいのちが造り主である神ではなく、「もの」に依存しているという発想からきています。そこには、死からの救いも、その「もの」を手に入れるか入れないかによっているという発想があります。このような発想は、主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまっている状態の人間に共通したもので、人が神さまの創造の御業によって神のかたちに造られていること、それなのに、神である主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまっているために、死の力に捕らえられてしまっていることを否定するものです。 このように、「いのちの木」そのものに、人に永遠のいのちを与える力があるという考え方は退けられなければなりません。そうしますと、創世記3章22節に記されています、 神である主は仰せられた。「見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。」 という、神である主のみことばはどのように理解したらいいのかという問題が生じてきます。これは、同じ3章の14節ー19節に記されています、神である主が「蛇」とエバとアダムに対するさばきを宣告された後に記されています。それで、神である主が、ご自身に対して罪を犯して、御前に堕落してしまった人の現実を踏まえて語られたことを記していると考えられます。 前半の、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。 という神である主のみことばは、3章5節に記されている、 あなたがたがそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、あなたがたが神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。 という、「蛇」の背後で働いていたサタンがエバに語ったことばを反映していると考えられます。神である主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまった人は、3章19節に、 あなたは、顔に汗を流して糧を得、 ついに、あなたは土に帰る。 あなたはそこから取られたのだから。 あなたはちりだから、 ちりに帰らなければならない。 と記されていますように、神のかたちとしての栄光と尊厳性を失い、死の力に捕らえられてしまった、「ちり」に過ぎないものになってしまいました。それなのに、人は自らの罪によって欺かれて、自分が神のようになったと思っていますし、罪の自己中心性に突き動かされて自分を神の位置に据えようとしています。これはまことに「皮肉な現実」です。神である主はこのような堕落後の人の現実を、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。 という皮肉を込めたことばもって表していると考えられます。 陶芸家が粘土から見事な器を造ったとき、その器は芸術作品であって、単なる「粘土」ではありません。それと同じように、2章7節において、 神である主は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。 と記されていますように、人は「土地のちり」すなわち細かい粒子で形造られたと言われていますが、人は神のかたちとしての栄光と尊厳性を与えられている神さまの御手の作品です。単なる「土地のちり」ではありません。けれども、その神のかたちとしての人が神である主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまったときに、人は「土地のちり」から取られたものとして「ちり」に帰るという、神である主の御手のお働きに逆行するもの、それを無にするものになってしまっています。 ここで問題となるのは、神である主が皮肉を言われることはないのではないかということです。けれども、神さまが人の高ぶりに対して皮肉を込めた対応をしておられることはほかにも見られます。たとえば、よく知られていることですが、創世記11章1節ー9節には人々がバベルの塔を築いたことが記されています。4節と5節に記されていることに注目したいのですが、4節には、人々が、 さあ、われわれは町を建て、頂が天に届く塔を建て、名をあげよう。 と言ったことが記されています。そして、続く5節には、 そのとき主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りて来られた。 と記されています。人々は「頂が天に届く塔を建て」たと思っていたのですが、主は「はるか下の方にあってよく見えない」ということで降りてこられたというのです。もちろん、天に座しておられる主は始めからすべてをご覧になっておられます。これは、主による皮肉を込めた対応です。ですから、神である主が人の高ぶりに対して、皮肉を込めた対応をされることはありえます。 これに対しまして、神である主のみことばは皮肉を込めたものではないと考えておられる方々によって、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。 という神である主のことばは、人が神さまから独立して物事を考え、独立して生きる者となったという意味で「神のようになった」ということを伝えていると言われることがあります。 もしこのことが、神さまに対して罪を犯して、御前に堕落する前の人は神さまの「言いなりになっていた」とまでは言わないとしても、神さまの「指示通りに生きていた」幼子のような存在であったというようなことを意味しているのであれば、最初に造られた時の人の状態をまったく誤解しています。最初に神のかたちとして造られた状態の人は、真の意味で人格的に成熟していましたので、堕落した後の人にはるかにまさる真の自由と主体性をもっていました。具体的な状況の中で神のかたちの本質的な特性である愛を現すことができる真の自由のうちにあったのです。けれども、罪によって堕落した後の人は、ヨハネの福音書8章34節に、 イエスは彼らに答えられた。「まことに、まことに、あなたがたに告げます。罪を行っている者はみな、罪の奴隷です。」 と記されていますように、罪の奴隷であって、真の意味での自由も主体性ももっていません。パウロも、ローマ人への手紙7章19節で、そのような人の現実を、自分のこととして、 私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています。 と告白しています。 また、人が神さまから独立して考え、生きる者となったということは、実際には、神さまを否定し、自らを神の位置に据えようとする罪の力に縛られてしまっていることを意味しています。そのことが「神のようになった」ことを意味しているのであれば、最も「神のようになった」存在はサタンであり、次に、悪霊たちであるということになります。仮に、神である主がこのような意味で、人がご自身のようになったということをおっしゃっておられるのであれば、それこそまさに皮肉であると言うほかはありません。 ですから、人が善悪の知識の木から取って食べて神である主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまったことによって、何らかの意味で「神のようになった」と考えることはできません。 創世記3章22節の神である主のみことばの後半の、 今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。 というみことばも、前半の、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。 というみことばと同じように、神である主の皮肉を込めたことばであると考えられます。先ほどのカッスートの見解の問題点を取り上げたときにお話ししましたように、罪を犯して堕落した後の人は「いのちの木から」取って食べれば、不老長寿の薬草を食べれば永遠に生きられるというようなとんでもない考え方をするようになってしまいました。ここではそのような人の現実を踏まえて、それに対する神である主の対処を、皮肉を込めた言い方で表していると考えられます。 神である主のみことばの後半の、 今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。 というみことばは、明らかに、ご自身に対して罪を犯して、御前に堕落してしまった人の考え方を反映しています。このことからも、前半の、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。 というみことばも、堕落後の人の考え方を反映していると考えられます。つまり、ここに記されている、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。 という神である主のみことばは(前半も後半も)堕落後の人の考え方を踏まえていて、それを反映しているということです。 神である主はこのように言われた後、24節に、 こうして、神は人を追放して、いのちの木への道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。 と記されていますように、人が「いのちの木」に近づくことがないようにされました。それは、人が罪あるままで「いのちの木」が表示している神である主の御臨在の御許に近づくなら、主の聖さを冒す者として、滅ぼされてしまうことになるからです。人が神である主の栄光の御臨在の御許に近づくことができるようになるのは、15節に記されている「最初の福音」に約束されている「女の子孫」として来られる贖い主による、罪の贖いにあずかることによっています。 このようなことから、「いのちの木」そのものに、人に永遠のいのちを与える力があったという見方は退けられなければなりません。 いのちの木がどのようなものであるかについては、先主日と先々主日に、聖餐式において用いられるパンと杯になぞらえてお話ししましたように、それは「礼典的」(サクラメンタル)なものであると考えることがいちばんよいと思われます。これは伝統的な理解の仕方です。つまり、「いのちの木」そのものに奇跡的な力があって、人に永遠のいのちを与えるというのではなく、神である主がその木を「礼典的」な意味をもつものとして指定されたので、その木は、その役割を果たすようになったということです。 この場合、「礼典的」ということは、神である主が、目に見えない霊的な祝福を与えてくださるに当たって、物質的な手段を用いられるということです。とはいえ、その物質的な手段そのものに祝福を伝える力はありません。けれども、その物質的な手段は単なる象徴ではなく、神である主が与えられた役割を果たします。この場合の「礼典的」ということばは、「内的かつ霊的な祝福を表し、約束するものとして、神である主によって指定された、外的で見えるしるし」という、ことばのより広い意味で用いられます。それで、神である主がエデンの園で聖礼典を制定されたというようなことではありません。この場合は、目で見ることができない神である主との愛にある交わりという、神のかたちに造られている人のいのちの本質を表すものでした。そして、先ほどもお話ししましたように、食べ物といのちを支えることの関係は、人が実感していることです。また、実際に、人は食べ物をいただく時に、特に、それを与えてくださっている神である主を思い起こすということがあって、それが神である主との交わりを指し示すのに適しています。それで、神である主は、ご自身との交わりという、人のいのちの本質を表すための手段として、食べ物としてよい実を結ぶ木をお用いになったと考えられます。 最後に一つの問題を取り上げておきます。それは、エデンの園において人は「いのちの木」から取って食べていたかということです。 これにつきましては、否定的に考えておられる方が多いようです。それは、先ほどから引用しています、創世記3章22節に記されています、 見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった。今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。 という神である主のみことばは、人が「いのちの木」から取って食べるなら、永遠に生きるようになることを示していると理解することの上に成り立っています。そして、もし人がエデンの園で「いのちの木」から取って食べていたとしたら、人は永遠のいのちを獲得していたはずなのに、実際には、人は永遠のいのちを得てはいません。それで、人はエデンの園で「いのちの木」から取って食べてはいなかったと考えるわけです。 けれども、これまでお話ししましたように、人が「いのちの木」から取って食べるなら、永遠に生きるようになるということは、罪によって堕落してしまっている人が考えていることであって、それが神である主のみことばに反しています。それで、このことに基づいて、人がエデンの園で「いのちの木」から取って食べていなかったと主張することはできません。けれども、このことから、人がエデンの園で「いのちの木」から取って食べていたと結論できるわけでもありません。 また、 今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。 という神である主のみことばにおいて、「いのちの木からも取って食べ」と言われているときの「からも」ということばは、それまで「いのちの木」からは取って食べてはいなかったことを意味すると言われていることがあります。 しかしこれは、善悪の知識の木から取って食べてしまって、いのちの木そのものに永遠のいのちを与えるような力があると考えるようになってしまった人が、「さらに」「いのちの木からも取って食べる」という意味でしょう。そうであれば、これは、人がそれまで「いのちの木」から取って食べてはいなかったことを示すものではありません。 これに対して、この時より前に、人が「いのちの木」から取って食べていたことを示していると思われることがあります。 一つは、2章16節ー17節に記されています神である主の戒めのことばです。それは、 神である主は人に命じて仰せられた。「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。」 というものです。 ここでは、神である主がエデンの園の「どの木からでも思いのまま食べてよい」けれど、 善悪の知識の木からは取って食べてはならない。 と戒めておられます。これを自然に読めば、「いのちの木」から取って食べることは禁じられていなかったと理解できます。 このことをさらに考えるためには、もう一つのことを考え合わせる必要があります。それは、「いのちの木」という名の「いのち」ということばが示しているのは、永遠のいのちのことではないということです。 永遠のいのちは、神のかたちに造られて歴史と文化を造る使命を委ねられている人が、歴史と文化を造る使命を忠実に果たして、完全に神である主のみこころに従った時に、そのことへの報いとして与えられる、より豊かな栄光における神である主との交わりに生きるいのちです。それは創造の御業とともに人に与えられている契約において約束されているものです。それは最初の人アダムが神である主のみこころに従いとおして獲得すべきものでしたが、アダムは神である主に対して罪を犯して、御前に堕落してしまいました。 永遠のいのちは、イエス・キリストがその地上の生涯において、十字架の死に至るまで父なる神さまのみこころに従いとおされて、そのことへの報いとして、父なる神さまから受けた、復活のいのちであり、被造物としての限界の中で許される最も豊かな栄光に満ちたいのちです。その永遠のいのちにある神である主との交わりは、黙示録22章1節ー5節に記されています、 御使いはまた、私に水晶のように光るいのちの水の川を見せた。それは神と小羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には、いのちの木があって、十二種の実がなり、毎月、実ができた。また、その木の葉は諸国の民をいやした。もはや、のろわれるものは何もない。神と小羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また、彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。 というみことばに示されています。ここに示されている永遠のいのちは、エデンの園の中央に1本だけ生えていた「いのちの木」が指し示していたものより、はるかに豊かで栄光に満ちた状態にある、主との愛によるいのちの交わりです。黙示録2章7節に記されています、 勝利を得る者に、わたしは神のパラダイスにあるいのちの木の実を食べさせよう。 というイエス・キリストのみことばは、私たちをこのような豊かで栄光に満ちた状態にある、主との愛によるいのちの交わりとしての永遠のいのちにあずからせてくださることを約束しています。 ですから、エデンの園にあった「いのちの木」は永遠のいのちを表示していたわけではありません。 先ほどお話ししましたように、「いのちの木」は「礼典的」な意味での役割を負っていて、神である主との愛の交わりという、人のいのちの本質を表示していました。そして、そのために「いのちの木」が用いられたのは、人は食べ物をいただく時に、特に、それを与えてくださっている神である主を思い起こすということがあって、それが神である主との交わりを指し示すのに適しているということが考えられます。そうであるとしますと、エデンの園ではそこにご臨在しておられる神である主との交わりは、人にとっては現実であったのですから、そのことを表示する「いのちの木」から取って食べることも実際になされていたと考えられます。 |
|
|
||