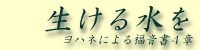 |
(第5回)
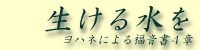 |
|
説教日:2000年10月8日 |
|
このように、この時、ガリラヤに行かれたイエス・キリストは、このサマリヤ人の女性と彼女が住んでいるスカルの町の人々を、みこころに留めておられました。 ところが、イエス・キリストがガリラヤに向けての旅を始められたことには、1節〜3節で、 イエスがヨハネよりも弟子を多くつくって、バプテスマを授けていることがパリサイ人の耳にはいった。それを主が知られたとき、── イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、── 主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。 と記されているような事情がありました。 先週は触れることができませんでしたが、この個所から、イエス・キリストがガリラヤに行かれたのは、ガリラヤに何かがあるからというより、ユダヤを去ること自体が当面の目的であったことが分かります。まして、ガリラヤに急いで行かなければならないというような事情は、まったく見受けられません。このことからも、4節で、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 と言われていることは、イエス・キリストが近い方の道をお選びになったということを意味しているという見方を取ることはできません。 いずれにしましても、イエス・キリストがガリラヤに行かれたことには、このような事情がありました。それで、スカルの町で一人のサマリヤ人の女性に出会われたのは、たまたまのこと、ついでのことであるように見えます。 しかし、それは限界のある人間の目で見ると、そのように思えるということです。 サマリヤを通って行かなければならなかった。 という言葉が示していますように、神さまのみこころのうちには、そのサマリヤ人の女性のことがしっかりと覚えられていたのです。また、彼女のあかしを聞いてイエス・キリストに心を開いて、さらに、イエス・キリストご自身から聞いて、その御言葉によってイエス・キリストを「世の救い主」であると信じるようになる、スカルの町のサマリヤ人たちのことが覚えられていたのです。 このことのうちに、神さまの摂理の御手のお働きの不思議さを見るような思いがいたします。御言葉が全体的に示している教理的なことから考えますと、これらのことのさらに奥には、エペソ人への手紙1章4節、5節で、 神は私たちを世界の基の置かれる前からキリストのうちに選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされました。神は、ただみこころのままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられたのです。 とあかしされている、神さまの「永遠のみこころ」(聖定的なご意志)があります。 私たちも、そのような、神さまの摂理のお御手の働きの不思議なお導きの中で、イエス・キリストに出会っていただき、イエス・キリストの御言葉を聞き、イエス・キリストを知り、イエス・キリストを信じることができるように導いていただいています。私たちひとりひとりが、神さまのみこころのうちに、しっかりと覚えていただいているのです。 ただ、心に留めておかなくてはならないことは、そのような神さまの摂理の御手は、機械的に働くものではないし、私たちの感覚では感じられないものであるということです。 このサマリヤ人の女性の場合、彼女は、旅の途中で疲れて井戸の傍らに座っているイエス・キリストに出会いました。着ているものから、ユダヤ人のラビであることは分かりましたが、喉が渇いているのに汲むものがないために、水を飲むことができないで困っている状態にありました。そのイエス・キリストの貧しさに触れた彼女の心は、自然とイエス・キリストに対して開かれていました。そして、皮肉を込めて、 あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリヤの女の私に、飲み水をお求めになるのですか。 と言うほどの余裕も与えられていました。そこから、イエス・キリストとの一連のやり取りが生まれてきています。 この記事を読んでいる私たちには、そこに神さまの摂理の御手が、イエス・キリストのご配慮という形を取って働いているということが分かります。けれども、この時、サマリヤ人の女性には、自分が神さまの摂理の御手に導かれていることは感じられなかったはずです。彼女には、何か「変わった力」が自分に対して働いているというような感覚(違和感)がないからです。 そのように、神さまの摂理の御手のお導きは、私たちにとっては、ごく自然なものとして働きます。もちろん、このサマリヤ人の女性も、後になって振り返って見たときに、自分が神さまの摂理の御手に導かれていたことを理解するようになったはずです。それは、この記事を読んでいる私たちに、そこに神さまの摂理の御手がイエス・キリストのご配慮という形をとって働いていることが分かるのと同じです。 神さまの摂理の御手の働きが、ごく自然なものであると言いますと、ある人々は「なぁーんだ」と失望されるかもしれません。その人々にとっては、それでは、あまりにも当たり前すぎて「つまらない」と感じられるのでしょう。何か、危機一髪のところで助け出されたというような形で働いたほうが「ありがたい」と感じられるということでしょう。実際に、危機一髪のところで助け出されたというような、劇的な出来事のことが、神さまの摂理の御手の典型的なお働きであるかのようにあかしされることが多いのです。 神さまの摂理の御手が、そのような危機一髪というような状況で、私たちのために働くことがあるということを否定するつもりはありません。私自身も、そのような「すんでのところで」という状況で、不思議に守っていただいたということがあります。しかし、そのような危機一髪というような状況に追い込まれる前に、私たちが自分の判断力を働かせることを通して、すなわち、私たちが自分で危険に気がついて、それを回避するように導いてくださることの方が、はるかに多く、また、一般的な導きです。 たとえば、不摂生な生活を続けている人が、このようなことをしていては大変なことになってしまう、ということに気がつくというようなことです。その際に、実際に誰かが大変なことになったというお話を聞いたとか、本を読んだとかいうこともあるでしょうが、そのようなことがないまま、気がつくということもあります。 さらに言いますと、神さまの摂理の御手は、もっと日常的なところで働いています。私たちはきょうもご飯を食べることができました。そのためには、ちょうどよい時に日が照り雨が降るように導いてくださっている神さまの御手のお働きがあります。また、治安が守られているために、流通が円滑に行われているというようなこともあります。そのようなすべてのことに、神さまの摂理の御手のお働きがあります。 これらのことで、私たちが神さまの御手のお働きを「感じる」ことは、まずありません。ですから、私たちは、神さまの摂理の御手のお働きを、自分の感覚に感じられる「感じ」や「特別な力」が働いていると感じられる「感覚」で受け止めるのではありません。御言葉に示されている神さまの摂理の御手のお働きが、そのようなものであることを信じて、それを絶えず自分に当てはめるのです。それが、危機一髪の状況のことでなく、毎日の普通の歩みの中で、当たり前のように起こっていることであっても、その中に、神さまの摂理の御手が働いていることを信じるのです。 これに対しまして、そのようなことであれば、別にクリスチャンでなくても、誰にでも起こることではないか、というような反論があるかも知れません。もちろん、それは、誰にでも起こっていることです。しかし、だからといって、それが神さまの摂理の御手のお働きではないということはできません。御言葉は、神さまの摂理の御手は、神さまがお造りになったすべてのものを支えるものとして働いていることを示しています。イエス・キリストは、 空の鳥を見なさい。種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしません。けれども、あなたがたの天の父がこれを養っていてくださるのです。あなたがたは、鳥よりも、もっとすぐれたものではありませんか。あなたがたのうちだれが、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、わたしはあなたがたに言います。栄華を窮めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。きょうあっても、あすは炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなたがたに、よくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。 マタイの福音書6章26節〜30節 と教えてくださいました。「クリスチャン(実は自分)だけに都合の良いように働くのが神さまの摂理の御手のお働きである」というのは、人間の勝手な考え方であって、御言葉に基づく考え方ではありません。 神さまの摂理の御手は、神さまがお造りになったすべてのものを支えてくださっています。それでは、神さまを信じている人々と、信じていない人々に違いはないのでしょうか。もちろんあります。神さまを知らない人々は、自分がそのように支えられていることを認めることはありません。そのようにして、罪を積み上げていってしまいます。これに対しまして、神の子どもたちは、その御手に信頼して、神さまのみこころを求めます。イエス・キリストが、 だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。 マタイの福音書6章33節 と教えてくださったとおりです。これを、神さまの「永遠のみこころ」の実現ということから言いますなら、神さまは、そのように、神さまの摂理の御手のお働きを信頼して、ご自身のみこころを求め、御言葉に従って歩む者たちを、「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」として整えていってくださるのです。 神さまの摂理の御手の働きが、このように、何か「特殊な力」が働いているのとは違って、ごく自然なものであり、私たちには感じ取ることができないものであることは、大きな意味をもっています。そのことも、このサマリヤ人の女性と彼女のあかしを通してイエス・キリストに心を開いて、イエス・キリストの教えを聞くようになったサマリヤ人たちのことから考えることができます。 先週お話ししましたように、43節〜45節に、 さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 と記されていることには、イエス・キリストに対するガリラヤのユダヤ人たちの姿勢と、スカルの町のサマリヤ人たちの姿勢の対比が見て取れます。 ここには、ガリラヤのユダヤ人たちが、イエス・キリストを歓迎したということが記されています。しかし、それは、イエス・キリストが「祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていた」からのことであったとも言われています。ガリラヤのユダヤ人たちは、「祭りの間にエルサレムで」さまざまな奇跡的な御業をなさったイエス・キリストを歓迎しただけでした。それは、自分たちの目を引き、自分たちの「眼鏡」にかなうと見えるイエス・キリストを歓迎したということです。実際、多くの人々が、イエス・キリストが自分たちの思うように動いてくれないことが分かると、イエス・キリストのもとから去っていきました。 それで、このことは、イエス・キリストにとっては、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」ということがご自身の上に実現しただけのことでしかありませんでした。 イエス・キリストは、 悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。 マタイの福音書16章4節 と言われました。それは、パリサイ人やサドカイ人たちが、イエス・キリストが自分たちの「眼鏡」にかなうかどうかを試そうとして「天からのしるし」を要求したことに対して語られたものです。そのように「しるし」を求めることが、ガリラヤのユダヤ人たちの変わらない姿勢でした。 これに対しまして、ヨハネの福音書4章43節の冒頭で、「二日の後、イエスはここを去って」と言われているのは、その少し前の40節、41節で、 そこで、サマリヤ人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは二日間そこに滞在された。そして、さらに多くの人々が、イエスのことばによって信じた。 と言われていることを受けています。 スカルの町のサマリヤ人たちは、進んでイエス・キリストからお聞きして、イエス・キリストの「ことばによって」イエス・キリストを信じました。しかも、わずか「二日間」のうちにです。そして、イエス・キリストを紹介してくれた女性に向かって、 もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方がほんとうに世の救い主だと知っているのです。 とあかしするまでになりました。 初めのうちは、彼女が言った「私のしたこと全部を私に言った人がいる」という「不思議なこと」からイエス・キリストに興味を持ったのでしょう。しかし、この人々は、そこから進んで、直接イエス・キリストにお聞きして、イエス・キリストの「ことばによって」イエス・キリストを信じるようになったというのです。 このように、ガリラヤのユダヤ人たちは、「しるし」という、感覚で捉えることができるし、自分たちを驚かせ、感激させることはできても、自分たち自身を根本から変えることはできないものによって、イエス・キリストを信じていました。これに対しまして、スカルの町のサマリヤ人たちは、イエス・キリストの「ことば」を聞いて、その「ことばによって」イエス・キリストを信じました。 ガリラヤのユダヤ人たちが「しるし」によってイエス・キリストを信じていたことは、先ほどお話しした、危機一髪のところで、神さまが奇跡的な方法で助け出してくださったというようなことこそまさに、神さまの御手のお働きであると感じる信仰の姿勢── 何か「特別な力」が働いていると感じるときに、神さまの摂理の御手のお働きがあると感じるという信仰の姿勢につながっています。そのような信仰の姿勢は、さらなる「しるし」を求めるようになります。「しるし」が与えられなくなると不安になることさえあります。 これに対しまして、サマリヤ人たちがイエス・キリストの「ことばによって」信じたときには、どういうことが起こったのでしょうか。そこでは、イエス・キリストの「ことば」がサマリヤ人たちのものとなっています。それは、イエス・キリストの御霊のお働きによることです。 イエス・キリストの「ことば」がこの人々のものとなっているのであれば、当然、イエス・キリストの「ことば」が、この人々の思いと言葉と生き方を導くようになっています。これによって、この人々は、根本から変えられていくようになります。このように現れてくる御霊のお働きこそが、イエス・キリストが、サマリヤ人の女性に、 この水を飲む者はだれでも、また渇きます。しかし、わたしが与える水を飲む者はだれでも、決して渇くことがありません。わたしが与える水は、その人のうちで泉となり、永遠のいのちへの水がわき出ます。 と言われたことの実現に他なりません。 このサマリヤ人の女性を初めとする、スカルの町のサマリヤ人たちは、ごく自然な形でイエス・キリストの教えに耳を傾けて、その御言葉そのものを理解し受け入れました。そして、その御言葉に基づいて、イエス・キリストを信じました。神さまの摂理の御手は、イエス・キリストとの自然な出会いと語らいの中に、最も豊かな形で働いていたのです。 |
|
|
||