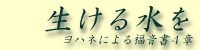 |
(第4回)
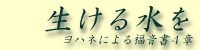 |
|
説教日:2000年10月1日 |
|
このことをどう考えるべきかということですが、私は、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 という言葉は、このサマリヤ人の女性とお会いすることがイエス・キリストのご意志であり、目的であることを示すために記されていると考えています。 その当時、ユダヤ人がサマリヤを通ってガリラヤに行くことは、ごく普通のことであったことは認められなければなりません。その意味では、サマリヤ人の女性と出会うために、ユダヤ人が避けている道を通られた、ということではなかったことも認められなければなりません。 しかし、ユダヤ人がサマリヤを通ってガリラヤに行くことは、ごく普通のことであったのであれば、ここで、わざわざ、「 ・・・・ しなければならない」という言葉を使って、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 と言われている理由は何でしょうか。 これに対しては、「この言葉は、イエス・キリストが、何かの事情があって近い道をお取りになったことを伝えているのだ。」と言われることでしょう。 けれども、ヨハネの福音書の最初の読者たちには、「サマリヤを通って行かれた」と言うだけでも、イエス・キリストが近い方の道をお取りになったことは伝わるのに、わざわざ「 ・・・・ しなければならない」という言葉を使ってまで、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 と言うことによって、近い方の道をお取りにならなければならなかったことを表わしているというのであれば、その事情か理由がどこかで示されていそうなものですが、そのようなことはどこにも示されていません。 それどころか、どうも、イエス・キリストは、急いでガリラヤに行こうとしてはおられなかったのではないか、と思える節があります。 40節では、 そこで、サマリヤ人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは二日間そこに滞在された。 と言われています。ここには、旅を急いでおられるイエス・キリストを、サマリヤ人たちが、しいてお引き止めしたというような意味合いはありません。 これに対して、「イエス・キリストが滞在されたのは、たったの二日間だけではないか。」というような反論があるかもしれません。確かに、「二日間」というのは短いような気がします。やはり、イエス・キリストは急いでおられたのではないだろうか、というような疑問がわいてきます。 けれども、41節、42節では、 そして、さらに多くの人々が、イエスのことばによって信じた。そして彼らはその女に言った。「もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方がほんとうに世の救い主だと知っているのです。」 と言われています。これは、サマリヤ人たちが、イエス・キリストの「ことばによって」、イエス・キリストが「ほんとうに世の救い主だと」信じるようになったということを伝えています。ですから、その「二日間」の滞在は、決して短すぎるものではありませんでした。進んでイエス・キリストの「ことば」聞こうとしていたサマリヤ人たちにとっては、その「二日間」は十分なものだったのです。 やはり、イエス・キリストは、ガリラヤへの旅を急いでおられたわけではないと思われます。 そのようなわけで、わざわざ、「 ・・・・ しなければならない」という言葉を使って、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 と言われているのは、近い方の道を通って行かなければならなかったということを表わしていると考えることはできません。それで、この言葉は、イエス・キリストがサマリヤ人の女性に出会われたことが、そして、後ほどお話ししますが、彼女のいる町のサマリヤ人の人々と出会われることが、イエス・キリストのご意志によることであり、目的であったことを表わしていると考えられます。 その当時、サマリヤを通ってガリラヤに行くことは、ごく普通のことでした。もちろん、ヨルダン川の向こう岸に行ってそこを北上してガリラヤに行くことも、珍しいことではありません。このありふれた、普通の道筋をイエス・キリストは歩んでおられました。それが、サマリヤ人と反目しているためにユダヤ人が極力避けている道であったとしたら、イエス・キリストが、あえて、そのような道をお選びになったということになります。そうすれば、このことのうちに、サマリヤ人の女性と出会ってくださろうとしたイエス・キリストのみこころが現れているということは、もっと受け止めやすかったことでしょう。 けれども、イエス・キリストは、この普通の道筋を、普通の旅人と同じように歩んでおられました。しかし、そのように当たり前で、何の変哲もないことのうちに、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 というイエス・キリストのご意志が働いていたのです。 私たちが、今朝、起きて、ご飯を食べたことは、当たり前のことでしたでしょう。このように、礼拝に来ることができて、イエス・キリストの御名によって神さまを礼拝することができるのも、いつも通りのことでしょう。でも、このことのうちに、確かに、私たちの主であるイエス・キリストのご意志が働いていることを受け止めることができますか。このいつもどおりの礼拝の時に、イエス・キリストが私たち一人ひとりをみこころに留めて、御顔を向けてくださるとともに、私たちの罪や弱さを十分に知っていてくださる大祭司として、父なる神さまの右の座でお働きになっていてくださることを受け止めることができますか。 さらに、イエス・キリストが、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 ことは、サマリヤ人の女性を初めとするサマリヤ人の人々と出会ってくださるためであった、という見方を補強することがあります。43節〜45節では、 さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 と言われています。 ここには、特に、44節の、 イエスご自身が、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたからである。 という言葉と、それに続く45節の、 そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 という言葉がうまくつながっていないのではないかという問題があります。「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」というイエス・キリストの言葉を引用した後で、 そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。 と言われているのはおかしいのでは、ということです。 これを理解する鍵は、ガリラヤの人々がイエス・キリストを歓迎したということの意味です。ヨハネは、それについて、 彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 と注釈しています。確かに、ガリラヤの人々はイエス・キリストを歓迎しました。しかし、それは、 彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 というのです。ガリラヤの人々は、イエス・キリストが多くの奇跡を行なったから、そして、そのような人が自分たちの所に来てくれたからということで、歓迎したのです。 そのような人々の姿勢について、ヨハネは、2章23節で、 イエスが、過越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々が、イエスの行なわれたしるしを見て、御名を信じた。 と述べた後、続く24節、25節で、 しかし、イエスは、ご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜなら、イエスはすべての人を知っておられたからであり、また、イエスはご自身で、人のうちにあるものを知っておられたので、人についてだれの証言も必要とされなかったからである。 という注釈を加えています。 この時、イエス・キリストがなさった奇跡的な御業を見た人々は、イエス・キリストの御名を信じました。けれども、その信仰は、自分たちの「眼鏡」にかない、自分たちの要求に応えてくれるイエス・キリストを信じるだけのものでした。やがて、イエス・キリストが十字架におつきになる道を歩まれるようになりますと、イエス・キリストから離れ去ってしまうようになる信仰です。 しかし、イエスは、ご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜなら、イエスはすべての人を知っておられたからであり、また、イエスはご自身で、人のうちにあるものを知っておられたので、人についてだれの証言も必要とされなかったからである。 という言葉は、イエス・キリストが、人々のそのような信仰の本質を見抜いておられて、それとして人々に接しておられたことを示しています。 後に、ガリラヤのユダヤ人たちは、イエス・キリストが、男だけでも五千人の人々を、五つのパンと二匹の魚をもって養ってくださったことにあずかりました。その人々が、ご自身をを探し求めてやってきたときに、イエス・キリストは、 まことに、まことに、あなたがたに告げます。あなたがたがわたしを捜しているのは、しるしを見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠のいのちに至る食物のために働きなさい。それこそ、人の子があなたがたに与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。 ヨハネの福音書6章26節、27節 とお教えになりました。 そして、イエス・キリストは、「永遠のいのちに至る食物」について教えてくださいました。けれども、その教えを聞いた人々は、その教えにつまずいて、すでにイエス・キリストの弟子であることを自任していた人々も含めて、イエス・キリストのもとから去っていってしまいました。 それが、 そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 とあかしされている、ガリラヤのユダヤ人たちの信仰の現実でした。この人々は、自分たちの「眼鏡」にかなうと見えるイエス・キリストを信じていただけでした。 イエス・キリストがガリラヤに行かれた時、ガリラヤの人々がイエス・キリストを歓迎したという、目に見えるところだけを見ますと、イエス・キリストが受け入れられ、敬われているように見えます。しかし、それは、「ご自身で、人のうちにあるものを知っておられたので、人についてだれの証言も必要とされなかった」イエス・キリストにとっては、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」ということの現れでしかありませんでした。 4章43節〜45節で、 さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 と言われていることには、さらに、43節で、 さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリラヤへ行かれた。 と言われていることと、続く44節で、 イエスご自身が、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたからである。 と言われていることとのつながりがあります。 「二日の後」ということは、40節で、 そこで、サマリヤ人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは二日間そこに滞在された。 と言われていることを受けています。そして、先ほども取り上げましたが、これに続く、41節、42節では、 そして、さらに多くの人々が、イエスのことばによって信じた。そして、さらに多くの人々が、イエスのことばによって信じた。そして彼らはその女に言った。「もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方がほんとうに世の救い主だと知っているのです。」 と言われています。 もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方がほんとうに世の救い主だと知っているのです。 という言葉は、一見すると、サマリヤ人の女性のあかしを退けているかのように見えますが、そういうことではありません。ことの流れを見ていきますと、39節で、 さて、その町のサマリヤ人のうち多くの者が、「あの方は、私がしたこと全部を私に言った。」と証言したその女のことばによってイエスを信じた。 と言われていますように、このサマリヤ人の女性のあかしはしっかりと用いられています。それによって、その町の人々の心も、イエス・キリストに対して開かれたのです。そうであるからこそ、その人々は、イエス・キリストからもっと教えを聞きたいと願ったのです。そして、その結果、その人々は、「イエスのことばによって」イエス・キリストが「ほんとうに世の救い主だと」知るようになりました。ちなみに、この「イエスのことばによって」の「ことば」(ホ・ロゴス)は単数形で、全体的にひとまとまりとなっているイエス・キリストの教えを指しています。 ですから、 もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方がほんとうに世の救い主だと知っているのです。 というサマリヤ人たちの言葉のポイントは「自分で聞いて」(「私たち自身で聞いて」)ということにあります。これは、サマリヤ人の女性のあかしを聞くことから始まって、イエス・キリストの「ことば」を聞いて信じた、サマリヤ人の信仰の確かさをあかしするものです。 ですから、4章43節〜45節で、 さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。 と言われていることには、イエス・キリストに対するサマリヤ人の信仰と、ユダヤ人の信仰にある本質的な違いが暗示されています。 サマリヤの人々は、イエス・キリストの教えに耳を傾けて、イエス・キリストの御言葉に基づいて、イエス・キリストを約束のメシヤであると信じました。しかも、イエス・キリストはわずか「二日間」そこに滞在されただけでしたのに、確かにイエス・キリストを信じました。40節で「二日間そこに滞在された。」と言われており、そんなに離れていない43節で、それを受けて「二日の後」と言われているのは、イエス・キリストの滞在が「二日間」であったことを強調するものと思われます。 これに対しまして、ガリラヤのユダヤ人たちは、イエス・キリストが「祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたから」イエス・キリストを歓迎しただけであったことが述べられています。 イエス・キリストが自分たちの所に来てくださったのに、そして、ずっとそこにいてくださっているのに、イエス・キリストの「ことば」を聞いて、イエス・キリストを信じることはありませんでした。ヨハネが、1章11節で、 この方はご自分のくにに来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。 とあかししていることは、ガリラヤのユダヤ人たちの間の現実であったのです。 ローマ人への手紙10章17節では、 そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです。 と言われていますが、サマリヤ人たちの信仰は、まさに、「聞くこと」から始まっています。 人が心を開いて語ってくださらなければ、私たちは聞くことができません。信仰において「聞くこと」は、語ってくださる方が語ってくださることを待つ姿勢から始まっています。聞くことにおいては、語ってくださる方の方が中心となっています。これに対して、見ることでは、自分が中心になりやすいものです。自分の「眼鏡」があって、その「眼鏡」にかなうかどうかの判断が働きやすいのです。 イエス・キリストが「祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていた」ガリラヤのユダヤ人たちは、自分たちの「眼鏡」にかなうからということで、イエス・キリストを歓迎しました。しかし、そこには、自分たちの「眼鏡」がしっかりとかかっています。そのため、この歓迎は、イエス・キリストには、「預言者は自分の故郷では尊ばれない。」ということの現れでしかありませんでした。 一方、サマリヤ人たちは、イエス・キリストが「祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを」何一つ見てはいませんでした。ただ、旅の疲れと喉の渇きで困って、井戸の傍らに座っていて、町でも「評判の悪い女」に助けを求めたユダヤ人のラビのお姿をしているイエス・キリストしか知りませんでした。それでも、サマリヤの人々は、イエス・キリストの言葉に耳を傾け、その「ことば」に基づいて、イエス・キリストを約束の救い主として信じました。 もちろん、サマリヤの人々が初めからそうであったのではありません。イエス・キリストは、まず、このサマリヤ人の女性に近づいてくださり、彼女の信仰の姿勢を、イエス・キリストの教えを聞くものに変えてくださいました。(このことにつきましては、すでに、ある程度お話ししましたが、時を改めて、お話ししたいと思います。)そして、彼女のあかしを用いてくださいました。彼女のあかしに触れたサマリヤ人たちが、それによって、イエス・キリストに対して心を開いて、イエス・キリストの「ことば」を聞く者となるように導いてくださっていたのです。 このように見ますと、イエス・キリストがガリラヤに行かれるのに、サマリヤを通って行かれたことには、大きな意味があったことが分かります。それで、4節で、 サマリヤを通って行かなければならなかった。 と言われているのは、やはり、このサマリヤ人の女性を初めとして、彼女の住む町のサマリヤ人の人々と出会ってくださることがイエス・キリストのご意志によることであり、サマリヤを通ってガリラヤに行かれたことの目的であったことを示すものであると考えられます。 |
|
|
||