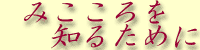 |
(第43回)
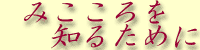 |
|
説教日:2000年3月26日 |
|
ですから、「神のかたち」に造られている人間の心に記された「愛の律法」は、人間の自由な意志が愛にあって働くための原理であって、決して、人間の自由な意志を制限したり、妨げたりするものではありません。 ところが、しばしば、神さまの律法は、人間の自由な意志を制限したり、時には、その自由な意志の働きを妨げたりするものであると思われています。 なぜ、そのように思われるようになってしまったのでしょうか。その理由は、これまでお話ししてきたことからお分かりのことと思いますが、改めて整理しておきましょう。 その根本的な理由は、言うまでもなく、人間が造り主である神さまに対して罪を犯して堕落してしまい、人間の心(本性)が罪によって腐敗してしまっていることにあります。人間の心そのものが罪によって腐敗してしまっているために、心に記されている律法も腐敗してしまっています。人間の心に記された神さまの律法は、自らの罪の自己中心性によって歪められてしまっているのです。 そのために、現在の状況においては、人間の心に記されている律法が、本来の神さまの律法である「愛の律法」に対立するようになってしまっています。 罪を犯して堕落してしまっている人間の心に記されている律法は、心の腐敗とともに腐敗し、自己中心的に歪んでしまっています。そうではあっても、人間が、自律的な存在であり、自分の心に記されている律法── すなわち、自分自身の律法── にしたがって自分の意志を働かせて、ものごとを考えたり決断したり行なったりするということには変わりありません。それで、人間は、自己中心的に歪んでしまっている自分自身の律法にしたがって自分の意志を働かせて、ものごとを考えたり決断したり行なったりするわけです。 人間は、罪を犯して堕落した後でも、自分の心に記されている自分自身の律法にしたがって自分の意志を働かせて、ものごとを考えたり決断したり行なったりするという点では、自由で自律的な存在です。けれども、心に記されている自分の律法そのものが罪によって腐敗し、自己中心的に歪んでしまっているために、自分の意志が自己中心的に働いてしまうという点では、不自由な存在です。 このことを指して、聖書は、自分のうちに罪を宿している人間は、罪の力に縛られていると教えています。 ヨハネの福音書8章34節には、 まことに、まことに、あなたがたに告げます。罪を行なっている者はみな、罪の奴隷です。 というイエス・キリストの言葉が記されています。また、ローマ人への手紙7章14節〜17節では、 私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行なっているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行なっているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。 と言われています。 このように、人間が、自己中心的に歪んでしまっている自分の律法にしたがって自分の意志を働かせて、ものごとを考えたり決断したり行なったりしているのであれば、それは、本来の神さまの律法である「愛の律法」と対立することになります。それが、罪によって堕落してしまっている人間の側からしますと、自分の自由が制限されているとか、妨げられていると感じられるのです。 けれども、本当に、人間の自由を制限し、妨げているのは、自分自身のうちに宿っている罪です。その罪が、心に記されている自分の律法を自己中心的に腐敗させてしまっているので、人間の意志は罪に縛られてしまっており、人間は罪の奴隷となってしまっているのです。 神さまの律法が人間の自由な意志を制限したり、時には、その自由な意志の働きを妨げたりするものであると感じられたりすることには、もう一つの事情があります。 以前お話ししたことですが、神さまの律法は、聖書に書き記されているさまざまな戒めから成り立っているというのが、私たちの間の一般的なイメージです。 確かに、現在の私たちの現実においては、神さまの律法は、神さまの御言葉である聖書に記されている律法を通して、最もはっきりと、また正しく知ることができます。けれども、それも、人間が造り主である神さまに対して罪を犯して堕落してしまい、人間の心が罪によって腐敗してしまっているからです。 本来、神さまの律法は「神のかたち」に造られている人間の心に記されているものです。しかし、人間が罪を犯して堕落し、人間の心そのものが罪によって腐敗してしまっているために、心に記されている律法も自己中心的に腐敗してしまっています。それで、改めて、外側から、文書の形で(客観的に)神さまの律法が与えられたのです。それが聖書に記されている神さまの律法です。 その意味では、聖書に記されている神さまの律法は、本来、「神のかたち」に造られている人間の心に記されているものなのに、いわば、人間から切り離して、それだけを「独立」させたものです。しかし、それは、人間が罪を犯して堕落してしまったための「応急措置」です。あるいは、神さまの律法がまったく見失われてしまうことがないようにと取り計らってくださった、神さまの「応急措置」です。 聖書に記されている神さまの律法は、そのような応急措置的な意味をもっていますので、罪を犯して神さまの御前に堕落してしまっている人間の現実を踏まえています。 たとえば、先週も引用しましたが、『ウェストミンスター小教理問答書』の問40〜問42には、 問40 神は、人の服従の基準として、何を最初に啓示されましたか。 答 神が人の服従のために最初に啓示された基準は、道徳律法でした。 問41 道徳律法は、どこに要約的に含まれていますか。 答 道徳律法は、十戒の中に要約的に含まれています。 問42 十戒の要約は、何ですか。 答 十戒の要約は、心をつくし、精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、主なる私たちの神を愛すること、また自分を愛するように私たちの隣人を愛することです。 と記されています。 これは、神さまの律法の全体は、十戒によって要約的にまとめられ、さらに十戒は、 心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。 という第一の戒めと、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。 という第二の戒めにまとめられるという理解を示しています。この点は、すでにお話ししたところです。 しかし、十戒の一つ一つの戒めは、第4戒の、 安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。 という戒めと、第5戒の、 あなたの父と母を敬え。 という戒めを除いては、「あなたは ・・・・ してはならない。」という禁止の戒めです。それで、これらの戒めが、契約の神である主を愛する第一の戒めと、隣人を愛することを求める第二の戒めとに、結びつかないような気がするということもあるのではないでしょうか。 十戒の戒めのほとんどが、そのように禁止の戒めであるのは、いわば、「神のかたち」に造られている人間の本来の姿を指し示す「愛の律法」を背景にして、人間の現実をはっきりと映し出しているからです。たとえば、第6戒は、 [あなたは]殺してはならない。 というものです。これは、ただ単に、殺人をしてはならないというだけの戒めではありません。 この戒めは、「神のかたち」に造られている人間は、本来、その心に記されている「愛の律法」に沿って、お互いを「神のかたち」としての栄光と尊厳性を担うものとして尊重することにおいて、生かすものである、ということを大前提としています。その上で、実際には、造り主である神さまに対して罪を犯して堕落している人間は、罪によって自己中心的に腐敗しているために、自分の「利益」ために隣人の尊厳性を踏みにじってしまう── その極端な現われの一つが殺人ですが── という、人間の現実を映し出しています。 ですから、この「[あなたは]殺してはならない。」という戒めは、「あなたは殺す者である。」という告発を含んでいます。同時に、そのさらに奥に、人間は、本来、お互いを「神のかたち」としての栄光と尊厳性を担うものとして尊重することにおいて、生かすものであるという、本来の「愛の律法」の要求が響いています。 このように、聖書に記されている神さまの律法において、しばしば、本来の「愛の律法」の戒めが背後に退いて、さまざまな禁止の戒めが前面に出てきています。 それは、人間が罪を犯して堕落してしまったための「応急措置」として、あるいは、神さまの律法がまったく見失われてしまうことがないようにと取り計らってくださった、神さまの「応急措置」として、聖書に記されている神さまの律法が、いわば、人間から切り離されて、それだけを「独立」させたものであるからです。 このように、本来は「神のかたち」に造られている人間の心に記されている神さまの律法を、人間から切り離して、それとして独立させることは、人間が罪を犯して堕落してしまっているために、必要なことですが、それによって、神さまの律法の本来の精神が見失われる危険も生じてきました。 完全なたとえにはなりませんが、そのことを、一つのたとえをもってお話ししたいと思います。 この数年の間に、私たちの国でも、心臓の移植が行なわれるようになりました。 いわば、聖書に記されていて、私たちの外側から与えられている神さまの律法は、摘出された心臓のようなものです。摘出された心臓は、確かに心臓ですから、医学的な標本として、心臓の仕組みがどうなっているか調べたり、それを通して教えたりすることに用いることができます。聖書に記されている神さまの律法も、確かに、神さまの律法です。それで、それを調べることによって、神さまの律法がどのような戒めから成り立っているかを知ることができます。 けれども、摘出された心臓は、その状態では、心臓として機能しません。心臓は、その人の体の中にあって血液を循環させる働きをしていて初めて、心臓としての本来の機能を果たします。同じように、神さまの律法が神さまの律法として本来の働きをするのは、それが、「神のかたち」に造られている人間の心に記されているときなのです。 繰り返しになりますが、「神のかたち」に造られている人間の本来の状態におきましては、人間が自らの自由な意志にしたがって思うことや決断することや行なうことが、自然と、神さまの「愛の律法」と、一致し調和していました。 「神のかたち」に造られている人間の本来の状態においては、心に記されている神さまの律法は、「愛の律法」として、人間の自由な意志が愛にあって働くための原理であって、決して、人間の自由な意志を制限したり、妨げたりするものではありません。 さて、これまで、数週間にわたって、コリント人への手紙第二・3章3節に記されている、 あなたがたが私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。 という御言葉に基づいて、神さまの律法が神の子どもたちの心に書き記されていることについてお話ししてきました。 神さまの律法が神の子どもたちの心に記されるのは、御子イエス・キリストが十字架の死と死者の中からのよみがえりを通して成し遂げてくださった贖いの御業に基づいてお働きになる「生ける神の御霊」によることです。 それは、きょう、これまでお話ししてきたこととの関わりで言いますと、ちょうど、摘出された心臓が元の体にぴったりとつなぎ合わせられて本来の機能を回復するように、神さまの律法が、再び、神の子どもたちの心に記されるようになったということです。それによって、本来の「愛の律法」として回復され、神の子どもたちの自由な意志が愛にあって働くように導く原理として機能するようになったのです。 そして、コリント人への手紙第二・3章の結論の部分に当たる17節、18節では、 主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。 と言われています。 神さまの律法が神の子どもたちの心に記されると、神の子どもたち自身が、御霊のお働きによって、御子イエス・キリストの栄光のかたちに造り変えられていくというのです。それは、先ほどのたとえで言いますと、本来の機能を回復した心臓だけが元気であるのではなく、体全体が本来の健康を回復しているょうなものです。先週お話ししましたように、神さまの律法が神の子どもたちの心に記されるのは、神の子どもたち自身が御子イエス・キリストの栄光のかたちに造り変えられていくことの中でなされることです。 その際に、 主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。 と言われています。 「主は御霊です。」ということは、十字架の死を通して私たちのために罪の贖いの御業を成し遂げてくださった栄光の主であるイエス・キリストが、そのお働きにおいて「生ける神の御霊」と一つとなられたことを示しています。 同じことは、コリント人への手紙第一・15章45節で、 聖書に「最初の人アダムは生きた者となった。」と書いてありますが、最後のアダムは、生かす御霊となりました。 と言われています。 「最後のアダム」とは、もちろん、イエス・キリストのことです。イエス・キリストが「生かす御霊」となったということは、イエス・キリストが変化して、御霊になってしまわれたということではなく、「生かす御霊となりました」という言葉が示していますように、ご自身の血によって確立された新しい契約の民を生かしてくださるお働きにおいて、御霊と一つとなられたことを意味しています。 十字架の死をもって私たちのために罪の贖いを成し遂げてくださり、死者の中からよみがえって栄光をお受けになったイエス・キリストは、父なる神さまの右の座に着座しておられます。その、栄光の主であるイエス・キリストは、御霊によって、私たちのうちにご臨在してくださり、御霊によって私たちを生かしてくださいます。 これを御霊の側から言いますと、御霊は、栄光の主であるイエス・キリストの御霊として、イエス・キリストがご自身の十字架の死をもって成し遂げられた贖いの御業に基づいて、イエス・キリストの贖いを私たちに当てはめて、私たちを生かしてくださるようにお働きになるのです。 それで、コリント人への手紙第二・3章17節の 主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。 という言葉の、「主の御霊のあるところ」とは、栄光の主であるイエス・キリストの御霊がご臨在されるところ、あるいは、同じことですが、御霊において、栄光の主であるイエス・キリストがご臨在されるところのことです。 「主の御霊のあるところには自由があります」と言われています。なぜなら、栄光のキリストの御霊が、イエス・キリストの贖いを私たちに当てはめてくださるからです。あるいは、栄光のキリストが、御霊によって、ご自身の贖いを私たちに当てはめてくださるからです。 それによって、私たちは、消極的には、先ほどお話ししました、罪ある者を告発する律法、そして、死に定める律法ののろいから解放されています。また、なお私たちのうちに残っている罪の力からも解放されていきます。 そして、積極的には、「神のかたち」に造られている人間の本来の自由、あるいは、神の子どもの自由の中に生かされています。そのことの中で、再び、神の子どもたちの心に記されるようになった神さまの律法が、本来の「愛の律法」として、神の子どもたちの自由な意志が愛にあって働くように導く原理として機能するようになっているのです。 |
|
|
||