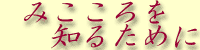 |
(第40回)
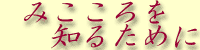 |
|
説教日:2000年3月5日 |
|
3節で、「墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ」ということは、コリントのクリスチャンたちが「キリストの手紙」となったのは、「生ける神の御霊」のお働きによることであるということを意味しています。 御霊は、御子イエス・キリストが十字架の死によって成し遂げてくださった罪の贖いを私たちに当てはめてくださり、私たちを新しく生かしてくださり、御子イエス・キリストの栄光のかたちに造り変えてくださいます。 これに対して、「石の板にではなく、人の心の板に書かれた」の「石の板」は、出エジプト記31章18節で、 こうして主は、シナイ山でモーセと語り終えられたとき、あかしの板二枚、すなわち、神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。 と言われていることを受けています。したがって、「石の板」に書かれたものとは、エジプトの奴隷であったイスラエルの民を救い出してくださった神である主が、シナイの山の上でモーセを通して与えてくださった律法を指しています。 「石の板」に律法を書き記したのは神さまです。出エジプト記32章15節、16節に、 モーセは向き直り、二枚のあかしの板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち、表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の作であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。 と記されているとおりです。 ですから、そこで与えられた律法は、確かに神さまのみこころを示す律法でした。それ自体には何の問題もありません。けれども、それは、主の民にとっては、外から「このようでありなさい。」とか「このようにしなさい。」というように戒められるものです。 その場合でも、イスラエルの民に罪がなかったのであれば、神さまの律法は、イスラエルの民にとっては自然な導きの光となったことでしょう。けれども、現実には、イスラエルの民の側に罪があり、神である主に対する根本的な不信仰がありました。そのために、イスラエルの民は、結果的に、常に主に背いてしまうことになりました。 そのことが、エレミヤ書31章31節、32節で、 見よ。その日が来る。── 主の御告げ。── その日、わたしは、イスラエルの家とユダの家とに、新しい契約を結ぶ。その契約は、わたしが彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。わたしは彼らの主であったのに、彼らはわたしの契約を破ってしまった。── 主の御告げ。── と言われています。 このように、「石の板」に書かれたというのは、神さまの律法が神の民の外側から与えられたことを示しています。それとともに、神さまの律法そのものは神さまのみこころを示すものではあっても、それが神の民の外から与えられて、外から指示するだけのものであるので、神の民を内側から造り変えることはできないという限界を意味しています。 このことは、パウロが自分のこととして告白していることです。ローマ人への手紙7章14節〜24節で、 私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行なっているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行なっているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。私は、私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は、自分でしたいと思う善を行なわないで、かえって、したくない悪を行なっています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行なっているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は、善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見いだすのです。すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです。私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。 と記されているとおりです。 14節では、 私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。 と言われています。また、16節では、 もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。 と言われています。さらに、22節、23節では、 すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです。 と言われています。 ここにはいろいろ難しい問題がありますが、まず、これは、御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いにあずかって神の子どもとされているパウロの状態を述べていると考えられます。パウロは御子イエス・キリストと、その十字架の死による罪の贖いを信じて、神さまの御前に義と認められています。ここでは、それなのに、そのパウロが罪の力に縛られているという現実を述べています。 パウロ自身は、そのいちばん深いところでは、神さまの律法を良いものであると認めているし、それに従いたいと願っています。けれども、パウロは、自分の「からだの中には異なった律法」があるというのです。それを、「からだの中にある罪の律法」と呼んでいます。そして、パウロは、自分が「からだの中にある罪の律法」のとりこになってしまっていると告白しています。 この「からだの中にある罪の律法」ということは、「罪の律法」がからだから生まれたという意味ではありません。「罪の律法」は「罪が生み出した律法」です。それが「からだの中にある」というのは、「罪の律法」に縛られて生きてきたそれまでの生き方が、習慣化してしまって、すっかり身に付いてしまっているということです。そのような生き方や、ものの見方や考え方や感じ方を「からだで覚えてしまっている」ということでしょう。 先週お話ししました、律法学者やパリサイ人たちは、神さまの律法を「守る」ための「実際的な指針や規定」を考え出しました。そして、それらの、「実際的な指針や規定」を守ることによって、神さまの律法を守っていると考えてしまう錯覚に陥ってしまっていました。律法学者やパリサイ人たちは、神さまの律法を、自分たちが守ることができるさまざまな規定にすり替えてしまっていたのです。 けれども、ローマ人への手紙7章14節以下の告白をしているパウロは、贖い主である御子イエス・キリストに出会って、そのようなパリサイ人の律法の理解と生き方から贖い出されていました。そして、神さまの律法を本来の精神において理解するようになっていました。 そうであっても、それは外から与えられた律法でした。外から与えられた律法は、パウロを「からだの中にある罪の律法」から解放することはありませんでした。同じことは、すべての神の子どもたちに当てはまります。 御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いにあずかって、罪を赦されている神の子どもたちでも、そして、贖い主であるイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められている神の子どもたちであっても、なお、罪の本性が残っています。そのために、いくら外側から与えられた神さまの律法を、その本来の精神において知ったとしても、それで、自分自身を内側から変えて、神さまの律法に従うようになることはできないのです。 そうしますと、根本的な解決のためには、神さまの律法に従うのに先立って、また、神さまの律法を守るという方法とは別の方法で、パウロが、 私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。 と告白しているときの、「私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者です。」という状態から解放される必要があります。 それこそが、パウロが、ローマ人への手紙8章1節〜4節で述べていることです。そこでは、 こういうわけで、今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と同じような形でお遣わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。 と言われています。 ここで、注目したいのは、2節の、 なぜなら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。 という言葉です。 この「罪と死の原理」の「原理」と訳された言葉(ホ・ノモス)は、先ほどの7章23節の「からだの中にある罪の律法」の「律法」と訳された言葉と同じです。ギリシャ語では、8章2節の「罪と死の原理」(ホ・ノモス・テース・ハマルティアス・カイ・トゥー・サナトゥー)は、7章23節の「罪の律法」(ホ・ノモス・テース・ハマルティアス)に、「そして死の」(カイ・トゥー・サナトゥー)という言葉を付け加えているだけです。── 8章2節で「そして死の」という言葉を付け加えたのは、7章24節で、 私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。 という嘆きの問いかけをしたので、それに答えるためであると考えられます。 ですから、8章2節の「罪と死の原理」は、7章23節の「罪の律法」のことです。それで、この二つのつながりを生かして、「罪と死の原理」を「罪と死の律法」と訳しますと、その前の「いのちの御霊の原理」(ホ・ノモス・トゥー・プニューマトス・テース・ゾーエース)も「いのちの御霊の律法」と訳すべきことになります。 意味の上からは、「罪の律法」や「罪と死の律法」も、「いのちの御霊の律法」も、人を導き動かす力── 人を罪と死へと引っ張っていくか、いのちへと導くかの違いはありますが── 、そのような力を示すと考えられますから、すべてを「原理」と訳すこともできるわけです。ただ、その場合は、その「原理」と訳される言葉が、7章14節〜25節に出てくる、神さまの「律法」と同じ言葉であることが分からなくなります。 このように、8章2節では、「いのちの御霊の原理(律法)」によって、神の子どもたちが、自分の罪が生み出した「罪の律法」から解放されていることが宣言されています。 その際、「キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理(律法)が」と言われています。この「キリスト・イエスにある」は、その前の1節の、 こういうわけで、今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。 ということの「キリスト・イエスにある」と同じ言葉で、それを受けています。それで、「キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理(律法)が」という言葉は、「いのちの御霊の原理(律法)」が、キリスト・イエスにあって働くものであることを示しています。 1節からのつながりで言いますと、私たちがイエス・キリストと一つに結ばれていて、キリスト・イエスにある者なので、「いのちの御霊の原理(律法)」が私たちのうちに働いてくださり、私たちを「からだの中にある罪の律法」から解放してくださるということです。 このように言いますと、7章14節〜25節で言われているパウロを代表する神の子どもの姿と、8章1節〜4節で言われている神の子どもの姿の、どちらが本当の神の子どもの姿なのか分からなくなるかも知れません。 もちろん、そのどちらも、私たちの現実を映し出しています。7章14節〜25節の嘆きは、嘆きで終わりません。それは、御子イエス・キリストの贖いの恵みによって、必ず、8章1節〜4節に記されている、「いのちの御霊の原理(律法)」による解放へと導かれるのです。 そして、「いのちの御霊」は、私たちをそこからさらに導いてくださって、御子イエス・キリストの栄光のかたちに造り変えてくださいます。 それが、地上にある神の子どもの正常な姿です。 3節では、 肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と同じような形でお遣わしになり、肉において罪を処罰されたのです。 と言われています。 「肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていること」の「肉」は、先ほどの「からだ」のことではなく、罪を犯して神さまの御前に堕落してしまっている人間を動かしている力のことです。それは、御子イエス・キリストの贖いに基づいて働かれる御霊と真向から対立します。自分のうちに罪を宿している人間に働きかけて、「からだの中にある罪の律法」によって縛りつけているのが「肉」です。 神さまの律法は、本来、「神のかたち」に造られている人間をいのちにあって導くものです。その場合、人間は、「神のかたち」に造られていることによって、いのちのうちにあります。言い換えますと、神さまとの愛の交わりのうちにあります。律法は、すでにいのちのうちにある人間を、さらに豊かな実を結ばせるように導くものです。 けれども、神さまの律法は、神さまに対して罪を犯して堕落し、「罪と死のの原理(律法)」に縛られて罪を犯す人間をさばき、死に定める働きをしますが、罪と死の中からから解放して生かすことはできません。「罪と死のの原理(律法)」に縛られている者を解放するのは、 神はご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と同じような形でお遣わしになり、肉において罪を処罰されたのです。 と言われていますように、父なる神さまが御子イエス・キリストを通して成し遂げてくださったことです。 ここで「肉によって無力になったため、律法にはできなくなっている」と言われていることが、コリント人への手紙第二・3章3節の言葉でいう「石の板」に書き記された神さまの律法の限界です。 さらに、ローマ人への手紙8章4節では、 それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。 と言われています。 3節では、御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いに基づいてお働きになる「いのちの御霊」が、私たちを「罪と死のの原理(律法)」から解放してくださったと言われていました。4節では、「いのちの御霊」が、さらに、私たちの歩みを導いてくださることが示されています。そして、このことによって、神さまの律法が私たちのうちに全うされると言われています。 これは、コリント人への手紙第二・3章3節で、神さまの律法が「生ける神の御霊によって」「人の心の板に書かれた」と言われていることと、互いに補い合うことであると考えられます。御霊は、御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いに基づいて、私たちを「罪と死のの原理(律法)」から解放してくださるとともに、私たちの心に神さまの律法を記してくださるわけです。 御霊のこの二つのお働き── 私たちを「罪と死のの原理(律法)」から解放してくださって、新しいいのちに生かしてくださるお働きと、私たちの心に神さまの律法を記してくださるお働きは、同時並行的になされるものです。それは、私たちが、御子イエス・キリストの栄光のかたちに造り変えられていくために必要なことです。 これまで繰り返しお話ししてきましたように、私たちが、御霊の導きに従って歩むときに、御霊は、私たちを御子イエス・キリストの栄光のかたちに造り変えてくださいます。そして、私たちの心に神さまの律法がより確かに記されるにしたがって、私たちは、御霊の導きに従うことができるようになります。 |
|
|
||