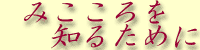 |
(第39回)
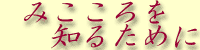 |
|
説教日:2000年2月27日 |
|
ただ単に、言葉や行ないが変わるということだけであれば、新約聖書の時代のパリサイ人たちが律法学者たちの言い伝えとしての戒めをきちんと、また、落ち度なく守っていたように、自分自身の意志と努力によって変えることができます。しかし、それは、決して、その人自身が心の奥底から造り変えられたということではありません。 イエス・キリストは、律法の教師たちの伝統的な言い伝えとして保存されてきたさまざまな規定を、きちんと守っていた律法学者やパリサイ人たちのことを、 目の見えぬ手引きども。あなたがたは、ぶよは、こして除くが、らくだはのみこんでいます。忌わしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなたがたは、杯や皿の外側はきよめるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります。忌わしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなたがたは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなたがたも、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。 マタイの福音書23章24節〜28節 と言われました。 ここで、イエス・キリストは、律法学者やパリサイ人たちのことを「偽善の律法学者、パリサイ人たち」(直訳・「偽善者である律法学者たちとパリサイ人たち」)と呼んでおられます。イエス・キリストは、今日私たちが考えている「偽善者」のイメージとは少し違った意味で、律法学者やパリサイ人たちのことを「偽善者」と呼んでおられます。 今日私たちが考えている偽善者は、本当の自分はそのようなものではないのに、そして、そのことを自分で知っているのに、いかにも善い者であるかのように振舞い、人にそのように見せかけている人のことです。私たちは、意識的に、自分を善い者に見せかけて、他人を欺いている人を偽善者と呼んでいます。そこには、その人が知っている自分の本当の姿と、人に見せている自分の姿にずれがあります。自分の本心と行ないの間にずれがあります。私たちは、その「ごまかし」を非難して、偽善者と呼んでいるわけです。 しかし、律法学者やパリサイ人たちは、そのような人々ではありませんでした。律法学者やパリサイ人たちは、心の底から、律法学者たちの伝統的な言い伝えとして保存されてきた戒めを大切に考えていました。それで、それらの戒めをきちんと守っていたのです。その点で、たとえば、今日の政治家のある人々が、選挙の前に、自分は本当はそう思ってはいないのに、選挙で票を獲得するために、「よさそうなこと」を並べる── そして、選挙が終わるとそれらのことを忘れてしまったり、「実はこういう意味であった」と解釈を変えてしまう、というのとは違います。律法学者やパリサイ人たちにあっては、自分の本心と実際の行ないの間に、ずれやごまかしはないのです。 それで、イエス・キリストは、律法学者やパリサイ人たちの本心と、実際の行ないの間に、ずれやごまかしがあるということで、律法学者やパリサイ人たちのことを「偽善者」と呼んでおられるのではありません。 イエス・キリストは、律法学者やパリサイ人たちのことを「目の見えぬ手引きども」とか「目の見えぬパリサイ人たち」と呼んでおられます。これが、律法学者やパリサイ人たちの「偽善」の本質です。律法学者やパリサイ人たちにあっては、自分の本心と実際の行ないの間に、ずれやごまかしはないのですが、彼らは、自らの本当の姿が見えなくなっていました。そのために、自分たちの行ないによって他の人々を欺いていたという以上に、自分たち自身を欺いていたのです。 イエス・キリストは、そのような自分の現実に気がつかないままに、自分たちのことを「社会の良心」であると自任し、自分たちの教えと行ないによって、人々を導こうとしている律法学者やパリサイ人たちのことを、「偽善者」と呼んでおられるのです。 自分の本心と実際の行ないの間に、ずれやごまかしがあるという意味の偽善は、いわば、意識的な偽善です。それは、他人を欺く偽善です。これに対しまして、律法学者やパリサイ人たちの偽善は、神さまの律法の教師や模範であることを自任していることと、その実、神さまの律法の本質が分かっていないということの間にずれがある、という意味の偽善です。それは、他人ばかりでなく、自分たち自身をも欺く偽善であり、その偽善性は、神さまだけが完全にお分かりになっておられるものです。その意味で、これは、意識的な偽善よりもはるかに危険なものです。 マタイの福音書23章が、律法学者やパリサイ人たちの偽善に対する、イエス・キリストの糾弾の言葉に満ちているのは、それが本当に危険なものであるからに他なりません。また、そのことを、何とかして、律法学者やパリサイ人たちに気づいてもらいたいという、イエス・キリストの強い思いが表わされているからでもあります。 律法学者やパリサイ人たちが、そのような危険な偽善の中に陥ってしまったことの原因は、神さまの御言葉、特に、神さまの律法についての理解が歪んでしまっていたことにあります。イエス・キリストは、そのことを、 目の見えぬ手引きども。あなたがたは、ぶよは、こして除くが、らくだはのみこんでいます。 と述べておられます。これは、聞いている人々が思わず噴き出してしまうユーモアのある言葉ですが、律法学者やパリサイ人たちの問題の根を鋭くえぐり出す言葉です。 すでに、いろいろな機会に、お話ししたことですが、バビロンの捕囚から帰還した時の指導者であったエズラの時代から、律法の教師たちが教えてきたさまざまな教えが『ミシュナー』という書物にまとめられています。そこでは、律法の教師たちの務めは、神さまの律法の周りに、柵を巡らすことであるとされています。 ひところ、中学校や高校には服装に関するさまざまな規定がありました。それには「心の乱れは服装の乱れから始まる」というような大義名分がありました。今そのことの善し悪しを論ずるつもりはありませんが、少なくとも建前の上では、生徒たちの心を大切にするはずの規定でした。しかし、実際には、スカートの長さやズボンの形や髪形などを監視し、守らせることが指導の中心になってしまっていた観があります。指導する側も、自ら欺かれて、そのようなことをすることが、大義名分である、生徒たちの心を守ることであるというような錯覚に陥ってしまっていたわけです。 モーセを通して与えられた神さまの律法の中には、いわば、視聴覚教育的に、汚れを避けるべきことを教える規定があります。そのために用いられている事柄(視聴覚教材)は、その当時の文化の中で偶像に結びついていたために避けるべきことや、衛生上の理由などによって避けるべきことなど、いろいろな理由によって選ばれています。中には、はっきりとした理由は分からないものもあります。その中には、汚れたものに触れたときには、その汚れをきよめるために水で洗うという規定があります。 それで、市場など人込みに出かけたときには、いつどこで汚れたものに触れたか分からないので、帰ってきたら水でからだを洗ってきよめるようにと教えられていました。マルコの福音書7章3節、4節に、 パリサイ人をはじめユダヤ人はみな、昔の人たちの言い伝えを堅く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また、市場から帰ったときには、からだをきよめてからでないと食事をしない。まだこのほかにも、杯、水差し、銅器を洗うことなど、堅く守るように伝えられた、しきたりがたくさんある。 と記されているとおりです。 本来、汚れを避けるべきことを教える規定ですが、そのことを守るという名目で設けられたさまざまな規定や方策が前面に出てきて、戒めの本来の意味や目的が見失われてしまうことがありました。具体的には、市場から帰ってきたときにからだを洗うかどうかが問題となってしまうのです。 そのような場合、市場からかえって来たらからだを水で洗い、食事の前には手を洗ったりしていれば、汚れに関する神さまの戒めを守っていることになってしまいます。汚れに関する神さまの戒めを手がかりとして、さらに自分自身のうちにある汚れの問題を見つめ、その汚れが単なる水の洗いではきよめられないものであることを認めて、神さまの備えを信じて待ち望む姿勢は失われていってしまいます。 ローマ人への手紙3章20節では、 なぜなら、律法を行なうことによっては、だれひとり神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。 と言われています。神さまの律法に照らして自分を見つめると、自分自身のうちにある罪と汚れが映し出されてしまうのです。それが、真に神さまの律法に向き合ったときに人間が感じる、本来の感じ方です。それなのに、律法学者やパリサイ人たちは、神さまの律法を守るために設けられたさまざまな規定や方策を守ることで、神さまの律法そのものを守っていると錯覚してしまって、律法の行ないによって義を立てていると感じてしまっていました。 お気づきのように、律法の教師たちの伝統による、さまざまな規定は、神さまの律法を守るために設けられた実際的な方策です。それで、その規定は、人間が守ることができる規定です。厳格に自分のことを律する人であれば、すべての規定をも守ることができるものです。 そして、律法学者やパリサイ人たちは、そのような規定をきちんと守っていることが、そのまま神さまの律法を守っているという錯覚に陥っていました。それで、自分たちが、律法の教師であり模範であると自任してしまっていたのです。それが、イエス・キリストが、 目の見えぬ手引きども。あなたがたは、ぶよは、こして除くが、らくだはのみこんでいます。 と言われた現実を生み出していました。 これは、律法学者やパリサイ人たちだけの問題ではありません。すでにお話ししましたが、形は違っても、本質的にこれと同じ問題は、いわゆる「クリスチャン生活の心得」という形で、クリスチャンの間に言い伝えられてきた、さまざまな方策や規定を守ることによって、神さまにしたがっていると感じることにも起こります。それらの方策や規定を守っていることで、神さまの御前に心安んじていたり、その逆に、それらが守れないということで落ち込んだり、人をさばいたりするようなことがあります。 また、「クリスチャン生活の心得」のようなものではなくとも、神さまの律法を自分の現状に合わせて解釈して、「こんなものだろう」と言って、それで済ませてしまうこともあります。それも同じ問題に陥ってしまっています。 では、一体、どうしたらいいのでしょうか。 先ほど引用した御言葉の中で、イエス・キリストは、律法学者やパリサイ人たちに、 目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります。忌わしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなたがたは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなたがたも、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。 と言っておられます。 この「まず、杯の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります。」というイエス・キリストの言葉は比喩的な表現ですが、これに、私たちの取るべき道筋が示されています。「まず、杯の内側をきよめなさい。」という順序が大切なのです。 律法学者やパリサイ人たちは、「外側」をきよめようとしています。しかし、律法の教師たちを通して言い伝えられてきたさまざまな規定をきちんと守っても、あるいは、神さまの律法の条文に自分なりの解釈を施して、いくらそれを守ったとしても、それでは、イエス・キリストが、 あなたがたは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなたがたも、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。 と言われる状態を造り出すだけです。 ここでは、罪によって本性が腐敗し、神さまの御前に汚れてしまっている人間が「墓」にたとえられています。そのような人間が、いくら律法の条文を守ってみても、それで、自分の罪の本性をきよめることができるわけではありません。それらの行ないは「墓」を白く塗り固めるだけのことで、それで「墓」が「墓」でなくなるわけではありません。 「内側は偽善と不法でいっぱいです」ということは、律法学者やパリサイ人たちだけでなく、すべての人間の現実です。罪によって自分自身の本性が腐敗し、神さまの御前に汚れてしまっている人間の姿です。この場合は、律法学者やパリサイ人たちが自ら欺かれてしまって、それに気づいていないので指摘されているだけのことです。 そうしますと、「まず、杯の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります。」ということは、行ないを改めなさいということではありませんし、心を入れ替えなさいということでもありません。そうではなく、「墓」を「墓」でなくすることです。それは、罪によって腐敗し、神さまの御前に汚れてしまっている自分自身の本性をまったく新しく造り変えることを意味しています。 エレミヤ書13章23節では、 クシュ人がその皮膚を、 ひょうがその斑点を、変えることができようか。 もしできたら、悪に慣れたあなたがたでも、 善を行なうことができるだろう。 と言われていますが、それは、人間の皮膚の色を変えたり、豹の斑点を変えることに匹敵することで、造り主である神さまでなければできないことです。 そうではあっても、イエス・キリストは、「まず、杯の内側をきよめなさい。そうすれば、外側もきよくなります。」と教えておられます。それは、不可能なことを命じておられるように思われます。 しかし、そのように教えてくださっておられるイエス・キリストご自身が、御霊のお働きを通して、私たちをまったく新しく造り変えてくださるのです。それが、コリント人への手紙第二・3章18節の、 私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。 という御言葉の示すところです。 イエス・キリストが私たちを心の奥底からまったく新しく造り変えてくださるに従って、「そうすれば、外側もきよくなります」という御言葉のとおりに、私たちの言葉や行ないも変わっていきます。 |
|
|
||