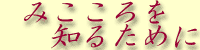 |
乮戞3夞乯
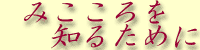 |
|
愢嫵擔丗1999擭5寧2擔 |
|
丂偙傟傑偱丄巹偨偪偺娫偵丄恄偝傑偺傒偙偙傠傪媮傔傞偙偲偼丄恄偝傑偐傜捈愙揑側乽巜帵乿傪庴偗傞偙偲偱偁傞偲偄偆峫偊曽偑偁傞偨傔偵惗傑傟偰偔傞丄偝傑偞傑側栤戣偵偮偄偰偍榖偟偟傑偟偨丅 丂愭廡偼丄偙偺傛偆側恄偝傑偺塱墦偺傒偙偙傠乮惞掕揑側偛堄巙乯偑偁傞偺偱丄巹偨偪恖娫傪娷傔偰丄偙偺悽奅偵懚嵼偡傞偡傋偰偺傕偺偑丄堄枴偲壙抣傪傕偭偰偄傞偲偄偆偙偲傪偍榖偟偟傑偟偨丅 丂傕偟丄恄偝傑偑偍傜傟側偄偲偟偨傜丄偙偺悽奅偼丄偦傟帺懱偲偟偰偼壗偺栚揑傪傕偨側偄丄廬偭偰丄壗偺堄枴傕側偄慺棻巕偺摦偒偺傑傑偵擟偣傜傟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偆偱偁傟偽丄巹偨偪恖娫偲偙偺悽奅偺偡傋偰偺傕偺偵偲偭偰偺嵟廔揑側恀幚偼丄偡傋偰偺傕偺偼丄偦傟帺懱偲偟偰偼壗偺栚揑傕堄枴傕側偄慺棻巕偺摦偒偺拞偐傜嬼慠偵惗偠偨傕偺偱偁傝丄昁偢偟傕偙偺傛偆側宍偱懚嵼偟側偗傟偽側傜側偐偭偨傢偗偱偼側偄偟丄偦傕偦傕弶傔偐傜懚嵼偟側偔偰傕傛偐偭偨傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅(1) 丂偦偆偱偁傟偽丄偦偺傛偆側悽奅偺拞偵丄栚揑堄幆傪傕偪丄帺傜偺懚嵼偺堄枴偲壙抣傪峫偊傞恖娫偺傛偆側懚嵼偑乽敪惗偟偨乿偲偄偆偙偲帺懱偑丄偍偐偟側偙偲偱偁偭偨偲尵傢側偗傟偽側傝傑偣傫丅偮傑傝丄尰幚偵丄偙偺悽奅偵恖娫偑懚嵼偟偰偄傑偡偺偱丄偙偺悽奅偵恖娫偑懚嵼偡傞偙偲偼摉偨傝慜偺偙偲偵側偭偰偄傑偡偑丄恖娫偺懚嵼偼丄暔幙揑側悽奅偦偺傕偺偺摦偒偐傜偼愢柧偱偒側偄傕偺偱偡丅 丂偙傟偵懳偟偰丄巹偨偪偼丄 恄偺惞掕偲偼丄恄偺屼堄巙偺弉椂偵傛傞塱墦偺寛堄偱偡丅偙傟偵傛偭偰恄偼丄屼帺恎偺塰岝偺偨傔偵丄偡傋偰偺弌棃帠傪偁傜偐偠傔掕傔偰偍傜傟傞偺偱偡丅 偲崘敀偟偰偄傑偡丅巹偨偪恖娫傪娷傔偰偙偺悽奅偺偡傋偰偺傕偺偼丄柍尷丄塱墦丄晄曄偺恄偝傑偵傛偭偰掕傔傜傟偨傒偙偙傠偵傛偭偰懚嵼偟偰偄傞偺偱丄堦偮堦偮偺傕偺偑懚嵼偡傞堄枴偲壙抣傪傕偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅摉慠丄栚揑堄幆傪傕偪丄帺傜偺懚嵼偺堄枴偲壙抣傪峫偊傞恖娫偺傛偆側懚嵼偑偄偰傕偍偐偟偔偼側偄傢偗偱偡丅 丂偙偺傛偆偵丄恄偝傑偺塱墦偺傒偙偙傠乮惞掕揑側偛堄巙乯偼丄偙偺悽奅偵懚嵼偡傞偡傋偰偺傕偺偺懚嵼偵丄妋偐側堄枴偲壙抣偑偁傞偙偲傪曐徹偡傞傕偺偱偡丅偙偺悽奅偵懚嵼偡傞偡傋偰偺傕偺偼丄恄偝傑偺塱墦偺傒偙偙傠乮惞掕揑側偛堄巙乯偵廬偭偰懚嵼偡傞傛偆偵側傝傑偟偨偺偱丄懚嵼偡傞堄枴偲壙抣傪傕偭偰偄傞偺偱偡丅 憂悽婰堦復嶰堦愡偵偼丄 偦偺傛偆偵偟偰恄偼偍憿傝偵側偭偨偡傋偰偺傕偺傪偛棗偵側偭偨丅尒傛丅偦傟偼旕忢偵傛偐偭偨丅偙偆偟偰梉偑偁傝丄挬偑偁偭偨丅戞榋擔丅 偲婰偝傟偰偄傑偡丅 丂憂悽婰堦復堦愡乣擇復嶰愡偵婰偝傟偰偄傞恄偝傑偺憂憿偺屼嬈偵偍偄偰丄恄偝傑偑偍憿傝偵側偭偨傕偺傪乽傛偄乿偲偛棗偵側偭偨偙偲偼幍夞婰偝傟偰偄傑偡丅偙傟偼丄偦偺幍夞栚偺偙偲傪婰偡傕偺偱偡丅 丂偙傟偵愭棫偭偰丄恄偝傑偼丄偁傞傕偺傗忬懺傪偍憿傝偵側偭偰丄偦傟傪乽傛偄乿偲偛棗偵側偭偨偙偲偑婰偝傟偰偄傑偡丅憂憿偺屼嬈偺夁掱偺拞偱憿傝弌偝傟偨傕偺偺偦傟偧傟偑丄恄偝傑偺屼栚偵乽傛偄乿偲擣傔傜傟偨偲偄偆偺偱偡丅 丂偙傟偵懳偟傑偟偰丄偙偺嶰堦愡偱偼丄乽恄偼偍憿傝偵側偭偨偡傋偰偺傕偺傪偛棗偵側偭偨丅乿偲尵傢傟偰偄傑偡丅憂憿偺屼嬈偺夁掱偺拞偱憿傝弌偝傟偨傕偺偺堦偮堦偮偑乽傛偄乿偩偗偱側偔丄憿傜傟偨傕偺偺偡傋偰偑丄偍屳偄偵怺偔娭傢傝崌偭偰偄傞偙偲偵尒傜傟傞慡懱揑側挷榓偵偍偄偰傕丄乽傛偄乿偲尒傜傟傞忬懺偵偁偭偨偲偄偆偙偲偱偡丅 丂偨偲偊偰尵偄傑偡偲丄崌彞偺僷乕僩楙廗偱丄僜僾儔僲丄傾儖僩丄僥僫乕丄僶僗偺偦傟偧傟偺僷乕僩偑旤偟偔壧偆偙偲偵偼丄偦傟偲偟偰偺旤偟偝偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄偦傟偧傟偺僷乕僩偑偍屳偄偵嬁偒崌偄側偑傜壧偆偲偒偵偼丄堦偮堦偮偺僷乕僩偺旤偟偝傪墇偊偨僴乕儌僯乕偺旤偟偝偑惗傑傟偰偒傑偡丅恄偝傑偑偍憿傝偵側偭偨悽奅傕丄偦偺傛偆側丄慡懱偲偟偰偺挷榓偺旤偟偝傪旛偊偰偄傞傢偗偱偡丅 丂偲偙傠偱丄恄偝傑偼丄憂憿偺屼嬈傪悑峴偝傟傞偲偒偵丄偍憿傝偵側偭偨傕偺傪偟偭偐傝偲偛棗偵側偭偰偍傜傟偨偼偢偱偡丅偦傟側偺偵丄乽恄偼尒偰丄偦傟傪傛偟偲偝傟偨丅乿偲偐丄乽恄偼偍憿傝偵側偭偨偡傋偰偺傕偺傪偛棗偵側偭偨丅乿偲偄偆傛偆偵丄偛帺恎偑丄偍憿傝偵側偭偨傕偺傪夵傔偰偛棗偵側傞偲偄偆偙偲偼丄偳偆偄偆偙偲偱偟傚偆偐丅 丂偙傟偼丄恖娫偑丄帺暘偺憿偭偨傕偺偺弌棃塰偊傪妋偐傔傞偨傔偵丄夵傔偰乽専嵏乿傪偡傞偺偲摨偠傛偆偵峫偊傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅偲偄偆偺偼丄恄偝傑偑捈愙丄偛帺恎偺屼庤偵傛偭偰偍憿傝偵側偭偨傕偺偵偼幐攕偑側偄偐傜偱偡丅 丂偱偡偐傜丄乽恄偼偍憿傝偵側偭偨偡傋偰偺傕偺傪偛棗偵側偭偨丅乿偲偄偆偙偲偼丄偳偙偐偵栤戣偑偁傝偼偟側偄偐偲挷傋偨偲偄偆偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅傓偟傠丄恖娫揑側尵偄曽傪偟傑偡偑丄恄偝傑偑怱傪崬傔偰偍憿傝偵側偭偨傕偺偵丄夵傔偰怺偄娭怱傪婑偣偰偔偩偝偭偨偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅 丂偐偮偰丄恄偝傑偼丄偛帺恎偑偍憿傝偵側偭偨悽奅傪丄偦傟偑尒帠偵拋彉棫偰傜傟惍偊傜傟偰偄傞悽奅偱偁傞偺偱丄偦偺悽奅帺懱偺朄懃偵擟偣偰摦偄偰偄偔傛偆偵偝傟偨丅偦偺堄枴偱丄恄偝傑偼捈愙偙偺悽奅偵娭傢傞偙偲偐傜庤傪堷偐傟偨丄偲峫偊傜傟偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偪傚偆偳丄偆傑偔慻傒棫偰傜傟偨帪寁偺偹偠傪姫偄偨傜丄屻偼帪寁偑帺摦揑偵摦偄偰偄偔偲偄偆偙偲偵偨偲偊傜傟傞傛偆側偙偲偱偡丅 丂偟偐偟丄恄偝傑偼丄偛帺恎偑偍憿傝偵側偭偨偙偺悽奅傪丄側傞偑傑傑偵擟偣傞偲偄偆宍偱乽曻抲乿偝傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅偙偺悽奅偵怺偔怱傪拲偄偱偍傜傟傞偽偐傝偱側偔丄偛帺恎偑怺偔娭傢偭偰偔偩偝偭偰偍傜傟傑偡丅偦傟偑丄憂憿偺屼嬈偺夁掱偺拞偱憿傝弌偝傟偨傕偺偵偮偄偰乽恄偼尒偰丄偦傟傪傛偟偲偝傟偨丅乿偲尵傢傟偰偄傞偙偲丄摿偵丄嵟屻偵丄 偦偺傛偆偵偟偰恄偼偍憿傝偵側偭偨偡傋偰偺傕偺傪偛棗偵側偭偨丅尒傛丅偦傟偼旕忢偵傛偐偭偨丅 偲尵傢傟偰偄傞偙偲偵昞傢偝傟偰偄傑偡丅 丂偦偆偟傑偡偲丄乽尒傛丅偦傟偼旕忢偵傛偐偭偨丅乿偲偄偆偙偲偼丄扨偵丄偪傖傫偲弌棃忋偑偭偰偄偨 劅劅 堦偮堦偮偑慺惏傜偟偔丄慡懱偲偟偰偺挷榓傕庢傟偰偄傞傕偺偲偟偰憿傜傟偰偄偨丄偲偄偆偙偲傪堄枴偟偰偄傞偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅偪傖傫偲弌棃忋偑偭偰偄傞偙偲偼丄偦傟偑恄偝傑偛帺恎偑偍憿傝偵側偭偨傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲偐傜丄弶傔偐傜暘偐偭偰偄傞偙偲偱偡丅 丂傑偢丄偙偙偱乽傛偐偭偨乿偲栿偝傟偰偄傞尵梩乮僩乕僽乯偺偙偲偱偡偑丄偙偺尵梩偼丄旕忢偵堄枴偺峀偄尵梩偱偡丅椣棟揑偵乽慞偄乿偙偲傗丄偨偲偊偽乽椙幙偱偁傞乿偙偲傗乽忋弌棃側乿偙偲側偳丄堦斒揑偵乽椙偄乿偙偲傪昞傢偡偽偐傝偱側偔丄乽旤偟偄乿偙偲傗乽惓妋偱偁傞乿偙偲傕昞傢偟傑偡偟丄乽婌偽偟偄乿偙偲側偳傕昞傢偟傑偡丅 丂偦傟偱丄偙傟偼丄恄偝傑偛帺恎偺偆偪偵婌傃偑偁偭偨偙偲傪昞傢偡傕偺偱偁傞偲峫偊傜傟傑偡丅偙傟偵偮偒傑偟偰偼丄偐偡偐側偨偲偊偱偟偐偁傝傑偣傫偑丄堦偮偺偨偲偊傪梡偄偰偍榖偟偟傑偟傚偆丅 丂嶌嬋壠偑庤捈偟偺昁梫偺側偄傑偱偵悑峴傪廳偹偰姰惉偝偣偨嬋偼丄偳偙偐偵栤戣偑偁傝偼偟側偄偐偲丄乽専嵏乿傪偡傞昁梫偼偁傝傑偣傫丅偦偟偰丄偦偺嬋傪嶌偭偨嶌嬋壠偼丄偦傟偑偳偺傛偆側嬋偱偁傞偐傪廫暘棟夝偟偰偄傑偡丅偦偆偱偁偭偰傕丄幚嵺偵偦偺嬋偑墘憈偝傟傞偲偒偵偼丄偦偺嶌嬋壠傕丄夵傔偰丄偦偺旤偟偝偵姶摦偟傑偡丅 劅劅 杮摉偵桪傟偨乽傛偄乿傕偺偲偼丄偦偺傛偆側傕偺偱偡丅偦偺乽傛偄乿傕偺偑尰幚偵懚嵼偡傞偙偲偑婌傃偲側傝傑偡丅 偦偺傛偆偵偟偰恄偼偍憿傝偵側偭偨偡傋偰偺傕偺傪偛棗偵側偭偨丅尒傛丅偦傟偼旕忢偵傛偐偭偨丅 偲尵傢傟偰偄傑偡偺偼丄偦偺傛偆側偙偲偱偟傚偆丅 丂恄偝傑偼丄偛帺恎偺塱墦偺傒偙偙傠偵廬偭偰丄旤偟偔惍偊傜傟偨悽奅傪偍憿傝偵側傝傑偟偨丅偙偺悽奅偑丄恄偝傑偺塱墦偺傒偙偙傠偺偲偍傝偵憂憿偝傟偨乽傛偄乿悽奅偱偁傝丄偦偺拞偵偁傞堦偮堦偮偺傕偺傕乽傛偄乿傕偺偱偁傞偙偲偼丄弶傔偐傜暘偐偭偰偄傑偟偨丅偗傟偳傕丄偛帺恎偺憂憿偺屼嬈傪捠偟偰丄幚嵺偵偦傟偑懚嵼偡傞傛偆偵側偭偨偙偲偵丄恄偝傑偼怺偄婌傃傪妎偊傜傟偨偲偄偆偙偲偱偡丅 劅劅 偙偺傛偆側悽奅偑懚嵼偡傞傛偆偵側偭偨偙偲傊偺婌傃偱偡丅 丂偱偼丄恄偝傑偼丄偙偺悽奅傪憿傝弌偝傟偰丄堦懱丄壗傪摼偨偲偄偆偺偱偟傚偆偐丅偦偺傛偆側丄乽懝摼偺寁嶼乿偐傜尵偄傑偡偲丄恄偝傑偵偼乽懝摼乿偼偁傝傑偣傫丅乽懝摼乿偼丄巹偨偪偺傛偆偵丄偡傋偰偺揰偵偍偄偰尷傝偺偁傞傕偺偩偗偵摉偰偼傑傞偙偲偱偡丅摿偵丄嵾偵傛偭偰懧棊偟偰偟傑偭偨偨傔偵丄懠偺懚嵼傪嶏庢偟偰偱傕帺暘傪旍傗偦偆偲偡傞傛偆偵側偭偰偟傑偭偨恖娫偑偡傞乽懝摼乿偺姩掕偼丄恄偝傑偵偼摉偰偼傑傝傑偣傫丅 丂恄偝傑偼丄偦偺懚嵼偲偡傋偰偺懏惈偵偍偄偰丄柍尷丄塱墦丄晄曄偺曽偱偡丅恄偝傑偼丄偁傜備傞揰偵偍偄偰柍尷偵朙偐側曽偱偁傝丄壗偺晄懌傕偁傝傑偣傫丅偙偺悽奅偑憿傜傟偨偐傜偲偄偭偰丄恄偝傑偵壗偐偑憹偟壛偊傜傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅傑偨丄恄偝傑偑偛帺恎偺屼椡傪傕偭偰丄巹偨偪恖娫偼婥偺墦偔側傞傛偆側峀戝側悽奅傪憿傝弌偝傟丄偦偺偡傋偰傪巟偊偰偍傜傟傞偐傜偲偄偭偰丄恄偝傑偐傜壗偐偑弌偰偄偭偰彮側偔側偭偰偟傑偆偲偄偆偙偲傕偁傝傑偣傫丅 丂偱偡偐傜丄恄偝傑偼丄巹偨偪恖娫傪娷傔偰丄偙偺悽奅傪偍憿傝偵側偭偨偙偲偵傛偭偰丄偛帺恎偺朙偐偝偵壗偐傪憹偟壛偊傟傜傟偨偲偄偆偙偲偼偁傝傑偣傫丅偐偊偭偰丄偛帺恎偺朙偐偝傪傕偭偰丄偍憿傝偵側偭偨悽奅傪枮偨偟偰偔偩偝偭偰偍傜傟傑偡丅偟偐偟丄恄偝傑偼惗偒偰偍傜傟傑偡丅恄偝傑偼丄偛帺恎偑怱傪拲偄偱偍憿傝偵側偭偨偙偺悽奅偑懚嵼偡傞偙偲傪婌傫偱偔偩偝偄傑偡丅摿偵丄偛帺恎偲偺垽偺岎傢傝偵惗偒傞傕偺偲偟偰丄乽恄偺偐偨偪乿偵偍憿傝偵側偭偨恖娫偺懚嵼傪婌傫偱偔偩偝偭偰偍傜傟傑偡丅 劅劅 偦傟偼丄偙偺悽奅傗恖娫偑恄偝傑偺栶偵棫偮偐傜偲偐丄恄偝傑偵壗偐傪壛偊傞偐傜偱偼側偔丄偙偺悽奅偺懚嵼偦偺傕偺傪丄摿偵丄巹偨偪恖娫偺懚嵼偦偺傕偺傪偍婌傃偔偩偝傞偺偱偡丅 丂愭廡傕丄暿偺娤揰偐傜丄偙傟偲摨偠偙偲傪偍榖偟偟傑偟偨偑丄偙偺偙偲偼丄恄偝傑偺傒偙偙傠傪抦傞偨傔偵丄巹偨偪偑廫暘偵傢偒傑偊偰偍偐側偔偰偼側傜側偄偙偲偱偡丅偙偺偙偲偼丄壗偱傕側偄偙偲偺傛偆偵巚傢傟傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄幚嵺偵偼丄僋儕僗僠儍儞傕丄恄偝傑偲偺娭學傪乽庢傝堷偒乿偺娭學偱峫偊偰偟傑偄偑偪偩偐傜偱偡丅 丂恖娫偑乽恄乿偲偺娭學傪乽庢傝堷偒乿偺娭學偲峫偊偰偟傑偆偙偲偵偮偄偰丄堦偮偺椺偲偟偰丄惞彂偺暥壔揑側攚宨偲側偭偰偄傞丄屆戙惣傾僕傾乮屆戙僆儕僄儞僩乯偺暥壔偺拞偱婰偝傟偨恄榖偺堦偮偱偁傞丄僶價儘僯儎偺憂憿恄榖亀僄僰乕儅丂僄儕僔儏亁偵昞傢偝傟偰偄傞丄恄偲恖娫偲偺娭學偵偮偄偰偺婎杮揑側峫偊曽傪尒偰傒傑偟傚偆丅 丂偦偺拞偱偼丄恖娫偼恄乆傊偺曭巇傪偡傞偨傔偵憿傜傟偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅 丂偦偺亀僄僰乕儅丂僄儕僔儏亁偺叅斅偺屲峴乣敧峴偵偼師偺傛偆偵婰偝傟偰偄傑偡丅 巹偼寣傪屌傑傝偲偟偰廤傔丄崪傪憿傝弌偦偆丅巹偼栰斬側傕偺傪憿傝忋偘傛偆丅偦偺柤偼乽恖娫乿偲偟傛偆丅妋偐偵丄巹偼栰斬側傕偺偱偁傞恖娫傪憿傠偆丅恖娫偵偼恄乆偵曭巇偡傞偲偄偆柋傔傪梌偊傞偙偲偵偡傞丅偦傟偵傛偭偰丄恄乆偑埨妝偵夁偛偡傛偆偵側傞偨傔偱偁傞丅(2) 偦偺乽寣乿偼丄斀媡幰乮夦廱乯僥傿傾儅僩傪儅儖僪僁僋乮僶價儘僯儎偺庡恄乯偵斀媡偝偣偨楑偱曔偊傜傟偰張孻偝傟偨丄僥傿傾儅僩偺孯戉偺嵟崅巜婗姱乮僉儞僌僂乯偺寣偱偡丅恖娫偼丄斀媡幰偺寣偐傜憿傜傟丄恄乆傊偺曭巇偺柋傔傪晧傢偝傟偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅偙傟偵傛偭偰丄恄乆偑妝偵側偭偨偲偄偆偺偱偡乮嶰嶰峴乣嶰榋峴嶲徠乯丅 丂偙偺傛偆側恄榖偼丄懧棊屻偺恖娫偑書偄偰偄傞丄恄偲恖娫偺娭學偵偮偄偰偺峫偊曽傪傛偔昞傢偟偰偄傑偡丅偦傟偼丄恄偲恖娫偺娭學偼丄婎杮揑偵丄乽庢傝堷偒乿偺娭學偱偁傞偲偄偆偺偱偡丅恖娫偑恄偵曭巇偡傞偲丄恄偼偦傟偵墳偊偰乮曬偄偰乯丄恖娫偺偨傔偵摥偄偰偔傟傞偲偄偆偺偱偡丅偙偺傛偆側恄偼丄恖娫偺曭巇傪昁梫偲偟偰偄傞恄偱偡丅 丂偙偺悽偺敪憐偱偼丄恄偲恖娫偺娭學偼婎杮揑偵偼乽庢傝堷偒乿乮曭巇乯偺娭學偱偡丅偦傟偧傟偺摥偒偑丄屳偄偵偲偭偰昁梫偱偁傞偲偄偆偙偲偺忋偵惉傝棫偭偰偄傞娭學偱偡丅 丂愭傎偳傕尵偄傑偟偨傛偆偵丄偦偺懚嵼偲偡傋偰偺懏惈偵偍偄偰丄柍尷丄塱墦丄晄曄偺曽偱偁傞恄偝傑偼丄偁傜備傞揰偵偍偄偰柍尷偵朙偐側曽偱偡丅偙偺悽奅傪偍憿傝偵側偭偨偲偄偭偰丄偛帺恎偵壗偐偑憹偟壛偊傜傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅傓偟傠丄恄偝傑偼偛帺恎偺朙偐偝傪傕偭偰丄憿傜傟偨傕偺傪枮偨偟偰偔偩偝偭偰偄傑偡丅 丂恄偝傑偑偙偺傛偆側曽偱偁傞偲偄偆偙偲傪丄扨偵抦幆偲偟偰抦偭偰偄傞偩偗偱偼廫暘偱偼偁傝傑偣傫丅偦偺傛偆側抦幆傪傕偭偰偄側偑傜丄幚嵺偵偼丄傎偲傫偳柍堄幆偺偆偪偵丄恄偝傑偲帺暘偨偪偑乽庢傝堷偒乿偺娭學偵偁傞偐偺傛偆偵庴偗巭傔偰偟傑偭偰偄傞恖乆偼傔偢傜偟偔側偄偐傜偱偡丅 丂偦偺傛偆側丄榗傫偩庴偗巭傔曽偑帺暘偺偆偪偵偁傞偙偲偵婥偯偐側偄傑傑偵丄恄偝傑偺傒偙偙傠傪媮傔傑偡偲丄傒偙偙傠偺棟夝偑崻杮揑偵岆偭偰偟傑偄傑偡丅 丂偨偲偊偽丄偳偺傛偆側曭巇傪偡傋偒偐偲偄偆慜偵丄恄偝傑偲偺娭學偑乽庢傝堷偒乿偺傛偆偵庴偗巭傔偰偄傞偲偟偨傜丄偦偺傛偆側庴偗巭傔曽傪偟側偑傜曭巇傪偡傞偲偄偆偙偲帺懱偑丄傒偙偙傠偐傜奜傟偰偟傑偭偰偄傑偡丅 丂恄偝傑偲偺娭學傪偦偺傛偆偵庴偗巭傔傞偙偲偐傜偼丄擇偮偺栤戣偑惗傑傟偰偔傞偲峫偊傜傟傑偡丅 丂堦偮偼丄恄偝傑偼帺暘偨偪偺曭巇傪昁梫偲偟偰偄傞偲偄偆敪憐偑傕偲偵側偭偰丄曭巇傪偟側偄偲丄恄偝傑偺搟傝傪彽偔偙偲偵側傞丄偲偄偆傛偆側乽嫲晐姶乿偑偦偺恖偺偆偪偵惗傑傟偰偒傑偡丅偦傟偼丄偙偺悽偺乽恄乿偑乽偨偨傞乿偲偄偆傛偆側偙偲偲摨偠偱偡丅尵偆傑偱傕側偔丄恄偝傑傪乽堌傟傞偙偲乿偲丄乽恄乿偺婡寵傪懝偹傞偺偱偼側偄偐偲乽嫲傟傞偙偲乿偼傑偭偨偔堘偄傑偡丅 丂巆擮側偙偲偵偼丄巜摫幰偨偪偑丄偦偺傛偆側乽嫲晐姶乿傪慀偭偰丄恖乆傪曭巇傊偲嬱傝棫偰傛偆偲偡傞応崌傕偁傝傑偡丅偟偐偟丄偦偺傛偆側乽嫲晐姶乿偵婎偯偔乽曭巇乿偼恄偝傑偑媮傔偰偍傜傟傞曭巇偱偼偁傝傑偣傫丅丂丂 偙偺揰偵偮偒傑偟偰偼丄擔傪夵傔偰偍榖偟偟傑偡丅 丂傕偆堦偮偺栤戣偼丄偦偺媡偺偙偲偱偡丅傗偼傝丄恄偝傑偼帺暘偨偪偺曭巇傪昁梫偲偟偰偄傞丄偲偄偆敪憐偑偁傞偨傔偵丄擬怱側曭巇傪偟偰偄傞恖乆偑丄帺暘偺曭巇偺幚愌偵棅傞傛偆偵側傞偲偄偆偙偲偱偡丅帺暘偺乽幚愌乿偵棅偭偰偄傞恖乆偺椺偼丄儅僞僀偺暉壒彂幍復擇擇愡丄擇嶰愡偱丄 偦偺擔偵偼丄戝偤偄偺幰偑傢偨偟偵尵偆偱偟傚偆丅乽庡傛丄庡傛丅巹偨偪偼偁側偨偺柤偵傛偭偰梐尵傪偟丄偁側偨偺柤偵傛偭偰埆楈傪捛偄弌偟丄偁側偨偺柤偵傛偭偰婏愔傪偨偔偝傫峴側偭偨偱偼偁傝傑偣傫偐丅乿偟偐偟丄偦偺帪丄傢偨偟偼斵傜偵偙偆愰崘偟傑偡丅乽傢偨偟偼偁側偨偑偨傪慡慠抦傜側偄丅晄朄傪側偡幰偳傕丅傢偨偟偐傜棧傟偰峴偗丅乿 偲尵傢傟偰偄傞恖乆偱偡丅 丂偙偺擇偮偺栤戣偺尰傢傟偨宍偼丄恄偝傑偵懳偡傞乽嫲晐姶乿偲乽戝抇偝乿偲偄偆傛偆偵丄惓斀懳偺傕偺偱偡偑丄偦偺墱偵偁傞丄恄偝傑偲恖娫偺娭學偵偮偄偰偺敪憐偼摨偠偱偡丅偦偟偰丄偦傟偑丄恄偝傑偺傒偙偙傠偵偮偄偰偺棟夝傪丄崻杮偐傜岆傜偣偰偄傑偡丅 丂傕偟丄偛帺恎偺拞偵丄偙偺傛偆側乽嫲晐姶乿偐乽戝抇偝乿偑偁傞偙偲偵婥偯偐傟傑偟偨傜丄偝傜偵丄怺偄偲偙傠偱丄恄偝傑偲偺娭學傪乽庢傝堷偒乿偺娭學偱峫偊偰偄傞傛偆側偙偲偼側偄偐偲丄怳傝曉偭偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅偦偺傛偆側敪憐傪帩偪懕偗偨傑傑偱丄恄偝傑偺傒偙偙傠傪媮傔偰傕丄崻杮揑側偲偙傠偱岆偭偰偟傑偄傑偡丅 侾 偙偺塅拡偺慡懱偵傢偨傞暔幙揑側悽奅傪棩偟偰偄傞朄懃偲偟偰峫偊傜傟偰偄傞偺偼丄堦斒偵乽僄儞僩儘僺乕憹戝偺朄懃乿偲偟偰抦傜傟偰偄傞乽擬椡妛偺戞擇朄懃乿偱偡丅偙傟偼丄乽奜偐傜壗偺僄僱儖僊乕偺壛偊傜傟側偄偲偙傠乮暵偠傜傟偨宯乯偱偼丄僄儞僩儘僺乕偼憹戝偡傞丅乿偲偄偆朄懃偱偡丅乽僄儞僩儘僺乕偑憹戝偡傞乿偲偄偆偙偲偼丄抔偐偄傕偺傗椻偨偄傕偺偑暯嬒壔偝傟偰偄偒丄嵟廔揑偵乽擬暯峵偺忬懺乿偵側偭偰偟傑偆偲偄偆偙偲偱偡丅偦傟偵傛偭偰丄拋彉棫偰傜傟偰偄傞傕偺偺拋彉偼曵夡偟偰丄柍拋彉傗崿棎偑憹偊偰偄偒傑偡丅側偤丄乽僄儞僩儘僺乕憹戝偺朄懃乿偑惉傝棫偮偺偐偲偄偄傑偡偲丄暔幙偺嵟彫扨埵偱偁傞慺棻巕偺摦偒偑堦掕偟偰偄側偔偰丄慡懱偲偟偰偼暯嬒壔偡傞傕偺偱偁傞偐傜偱偁傞偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅乮杮暥偵栠傞乯 俀 J.B.Pritchard ed., Ancient Near Eastern Texts. 3rd ed., 1969. (Princeton: Prenceton University Press) p.68 乮杮暥偵栠傞乯 |
|
|
||