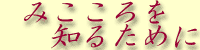 |
(第33回)
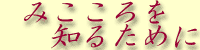 |
|
説教日:2000年1月16日 |
|
きょうは、いくつか質問をいただいたこともありまして、「良心の自由」についてのお話を休んで、「神のかたち」に造られている人間の心に記されている「愛の律法」について、これまでお話ししたことを補足したいと思います。 先週お話ししましたように、私たちが何をどのように考え、何をどのように知り、何をどのように感じるかということは、いろいろな条件によって左右されますが、最終的には私たちが自由な意志によって選び取っています。「神のかたち」の本来の姿においては、心に記されている「愛の律法」に沿って、物事を考え、感じ、決断していました。言い換えますと、人間の本来の姿においては、考えることと感じることと決断することのすべてを根本から動機づけているのは、造り主である神さまに対する愛であり、同じく「神のかたち」に造られている隣人への愛なのです。 人間は物事を確かに知ろうとして、学問を構築してきました。物事の根源にまで遡って、その根本にある事柄を扱うのは「哲学」です。その「哲学」という言葉は、英語ではフィロソフィー philosophy です。これは、よく知られていますように、ギリシャ語で「 ・・・・を愛すること」を表わすフィロと、「知恵」や「知性」を表わすソフィアからなるフィロソフィアという言葉を語源としています。それで、哲学は、知を愛すること、物事を確かに知ることを願い求めること、から始まっていると言われたりします。 「神のかたち」に造られている人間の本来の姿においては、物事の真の姿を知りたいという願いのさらに奥に、造り主である神さまへの愛があります。自分たちと、自分たちの住んでいる世界の真の姿を知りたいと願うことには変りありませんが、その願いは、自分たちと世界の造り主である神さまを愛する愛から出ています。神さまを愛することがまずあって、その愛から、神さまがお造りになった自分自身とこの世界をよりよく知りたいという願いが生まれてきます。 そのようにして、知的で、一見冷徹に見える人間の学問的な営みも、本来、造り主である神さまに対する愛と隣人に対する愛を根本的な動機として成り立つものです。御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いにあずかって、「神のかたち」の本来の姿を回復されつつある神の子どもたちにとっては、そのような営みであるのです。 「神のかたち」に造られている人間の本来の姿においては、知的な活動も、造り主である神さまへの愛と隣人への愛によって動機づけられ、導かれてなされます。その場合、知的な活動をする時に働いている知性や、神さまの御手のわざをよりよく知ったときの喜びに関わる感情の動きなども、「神のかたち」に造られている人間の心に記されている「愛の律法」に導かれています。 ですから、「神のかたち」に造られている人間の自由な意志が「愛の律法」に導かれるということは、道徳的なことだけに限られているのではありません。私たちは「愛の律法」とか、単に、律法といいますと、それが、ただ道徳的な行ないに関わるものであると考えがちです。もちろん、神さまの律法は、私たちの行ないに関する道徳的なことと深く関わっています。けれども、それに限らないで、私たちの本性の在り方から始まって、心の在り方、ものの見方や考え方、感じ方、そして、外に現われてくる行ないに至るまで、私たちのすべてに深く関わっています。 それというのも、この世界のすべてのものが神さまの御手の作品であり、造り主である神さまとの関係において存在しているからです。すべてのものは、神さまの御手の作品として、それぞれに固有の特性や本性を与えられています。造り主である神さまは、それぞれのものを、その特性と本性にふさわしく保っていてくださいます。その意味で、すべてのものが、神さまとの関係にあって存在しています。 そのように、すべてのものが、それぞれに固有の特性や本性を発揮していることに神さまの知恵が表わされていますが、それらの特性や本性がそのまま保たれていることに、また、それがそれぞれの特性や本性にふさわしく表現されていることに、広い意味での律法── 一般的な言葉で言いますと、「法」あるいは「法則」が見られます。ちなみに、聖書が記されているヘブル語やギリシャ語では、「律法」も「法」も「法則」も同じ言葉(ヘブル語ではトーラー、ギリシャ語ではノモス)で表わされます。 天体がそれぞれの軌道を持っており、それに沿って運行することも、生き物たちが群れをつくり、子を産み育てることも、渡り鳥がその行く道と帰る道を知っていることも、植物が、それぞれに固有の花を咲かせ、実をならせることも、みな、造り主である神さまのご意志の表現である法に従って起こっています。また、一つ一つのことが、それぞれに固有の特性や本性に従ってなされていながら、全体として見事な調和のうちに展開していることにも、造り主である神さまがお定めになった法の現われがあります。 主よ。あなたのことばは、とこしえから、 天において定まっています。 あなたの真実は代々に至ります。 あなたが地を据えたので、 地は堅く立っています。 それらはきょうも、あなたの定めにしたがって 堅く立っています。 すべては、あなたのしもべだからです。 詩篇119篇89節〜91節 このように、すべてのものが造り主である神さまがお定めになった法、すなわち、律法に従って存在しており、それぞれの特性と本性を発揮して、全体としての調和をを保っています。それを、私たち人間は、さまざまな方法で発見して、世界の法則として理解したり、物事の原理や原則として理解したりしています。先ほどのお話では、その際に、「神のかたち」に造られている人間は、その本来の姿においては、造り主である神さまへの愛が動機となって、すべてのことを理解し受け止めていくということになります。 さらに言いますなら、それぞれの存在に固有な本性や特性が、固有な本性や特性であるのは、それが、一時的なものではなく、ずっと保たれているからです。その意味では、それぞれの存在に固有の本性や特性も、造り主である神さまのご意志の表われである法(律法)の表現であるのです。 これらのことから分かりますが、造り主である神さまの法(律法)は、それぞれの存在に固有の本性や特性を生み出し、それを生かし、支えるものであって、決して、それを妨げるものではありません。 すべてのものが造り主である神さまがお定めになった法(律法)に従って存在しており、それぞれの特性と本性を発揮しています。その中でも特に、「神のかたち」に造られている人間は、自由な意志を持つ人格的な存在として造られています。そして、「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性は愛です。このことを。先ほどのお話ししたことに当てはめますと、私たち人間を「神のかたち」としての本質と特性において保ち、「神のかたち」としての本質と特性において生かしているのは、造り主である神さまの法、すなわち、律法です。 人間以外の存在の場合には、造り主である神さまの法は、たとえば動物などの生き物では、その本能的な本性に刻まれています。植物などでは、植物それぞれの特性に刻まれています。最近では、その仕組みが遺伝子情報として知られるようになってきました。── それが遺伝子情報という形で伝えられるということも、造り主である神さまがお定めになった法で、人間がそれを発見したということです。 これに対して、「神のかたち」に造られている人間の場合はどうでしょうか。人間は、肉体と霊魂から成り立っていますので、その他の生き物たちと共通する側面があります。その意味では、神さまがお定めになった法は、人間の肉体的な本性にも刻まれています。 けれども、「神のかたち」としての人間の本質は、人格的な存在であることにあります。人間は、造られたものの限界の中においてではありますが、造り主である神さまが人格的な方であることを映し出すものです。それで、神さまの法は、人間の人格に記されていて、人格的な法です。それを、私たちは「律法」と呼んでいるわけです。言い換えますと、神さまは、「神のかたち」に造られている人間がご自身の本質的な特性である愛を映し出すようにと、人間の心に「愛の律法」を記してくださったのです。 ですから、神さまが私たちの心に記してくださった「愛の律法」は、私たちを「神のかたち」としての栄光と尊厳性において生かすものであって、決して、私たちを束縛するものではありません。 そのことを、御言葉は、繰り返し述べています。 私はあなたの戒めを決して忘れません。 それによって、あなたは 私を生かしてくださったからです。 詩篇119篇93節 互いに愛し合うべきであるということは、あなたがたが初めから聞いている教えです。 ・・・・ 私たちは、自分が死からいのちに移ったことを知っています。それは、兄弟を愛しているからです。愛さない者は、死のうちにとどまっているのです。 ヨハネの手紙第一・3章11節、14節 律法が私たちを生かすというのは、律法主義ではないかという疑問が出さされるかもしれません。しかし、そのような疑問は、律法についての誤解と、律法主義についての誤解から出ています。律法主義は、神さまに対して罪を犯して堕落してしまった人間が、義と認められ、救われるためには、律法を守り行なわなければならないという考え方のことです。あるいは、神さまに対して罪を犯して堕落してしまった人間も、律法を守り行なうことによって、義と認められ救われる、という考え方です。 これは、神さまの律法について根本的に誤った考え方です。 第一に、先週お話ししましたように、「神のかたち」に造られている人間の心に「愛の律法」が記されているということは、「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性(本性)が愛であることと、その愛が思いや考え方の段階から表現されることを意味しています。それを、きょう、これまでお話ししてきましたことに合わせて言いますと、「愛の律法」は「神のかたち」としての本性の本来の在り方を生み出し、それを支えるものです。 ところが、神さまに対して罪を犯して堕落してしまっている人間は、罪のために、「神のかたち」としての本性が腐敗してしまっています。その「愛の律法」が生み出していた「神のかたち」の本性の本来の在り方を、自らの自由な意志において、腐敗させてしまっている状態にあるのです。言い換えますと、神さまに対して罪を犯して堕落し、本性を腐敗させてしまっている人間は、自らの心に記されている「愛の律法」を腐敗させてしまっているのです。 ですから、神さまに対して罪を犯して堕落し、本性を腐敗させてしまっている人間は、根本的なところで、すなわち、「神のかたち」としての在り方の段階で神さまの律法に違反した状態にあります。それで、たとえ、人間の目に見える行ないを整えるだけでなく、思いや考えの段階から精一杯整えてみても、それは、自分たちの目に良いと感じられる状態を生み出しているだけであって、「神のかたち」としての本性の在り方からすべてを見通しておられる神さまの御前には、本性の腐敗を隠すことはできません。 第二に、以前お話ししたことですが、律法を守り行なうと言っても、律法の全体は、「あなたの神である主」すなわち契約の神である主を愛することと、同じく「神のかたち」に造られている隣人を愛することに集約されます。それで、神さまの律法を守り行なうためには、何よりも、神さまとの関係が、神である主の契約に基づく本来の関係になければなりません。ところが、神さまに対して罪を犯して堕落した状態にある人間は、神さまの契約を破っている状態にあります。神さまを神として愛することも敬うこともありません。この点でも、罪を犯して堕落している人間は、そもそもの出発点から、神さまに背いているのであって、とても、神さまの律法を守り行なうことはできないのです。 これらのことから分かりますように、律法主義は、一種の錯覚の上にしか成り立ちません。罪を犯して堕落し、本性が腐敗している人間は、神さまの律法を守り行なうことはできません。当然、それによって義と認められることはありません。人が義と認められるのは、御子イエス・キリストが十字架の死をもって成し遂げてくださった罪の贖いの御業を信仰によって受け入れることによっています。 なぜなら、律法を行なうことによっては、だれひとり神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によってあかしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです。 ローマ人への手紙3章20節〜24節 ですから、罪を犯して堕落してしまっている人間が、神さまの律法を守り行なうことによって義と認められて、救われるという、律法主義の考え方は、聖書の教えではありません。律法主義は、神さまの律法を根本的に誤解していますので、神さまの律法を根底から傷つけて損なってしまいます。 しかし、律法主義を断固拒否するということは、神さまの律法についての律法主義という考え方を拒否するということであって、神さまの律法そのものを否定することではありません。神さまの律法そのものを否定することは、神さまに対する愛を否定することにつながってしまいます。 「神のかたち」に造られた人間の本来の状態にあっては、人間の本質的な特性(本性)は愛であり、それが心に記された「愛の律法」を通して表現されます。また、人間は、心に記されている「愛の律法」に従って生きるときに、「神のかたち」としての栄光と尊厳性を保つ状態にあり、本当のいのちの状態にあります。 私たちは、福音の御言葉によってあかしされている御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いを、信仰によって受け入れています。それで、その信仰によって義と認められています。それとともに、イエス・キリストが成し遂げてくださった罪の贖いに基づいて働かれる御霊によって、「神のかたち」の本来の姿を回復されています。さらに、私たちのうちには、心に記されている「愛の律法」も回復されています。それで、私たちは、御霊に導かれて、自分の心に回復されている「愛の律法」に沿って歩むときに、本来のいのちに生きるようになります。 こういうわけで、今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と同じような形でお遣わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。 ローマ人への手紙8章1節〜4節 ここで、私たちは、「キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理」によって「罪と死の原理」から解放されており、「肉に従って歩まず、御霊に従って歩む」ものである、と言われています。そして、神さまが御子イエス・キリストをお遣わしになって、その十字架の死をもって贖いの御業を成し遂げてくださったのは、「肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるため」である、と言われています。 これまでのお話からお分かりのように、「肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされる」ということは、私たちが外側から規定や決まりを押し付けられて縛られることではありません。むしろ、御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いにあずかっている私たちが「神のかたち」の本来の姿に回復されている(過程にある)ので、その愛の特性が「愛の律法」によって表現されるようになるということです。それによって、私たちが、造り主である神さまとの愛の交わりと、隣人との愛の交わりに生きるようになるということです。── そして、それが、私たちに対する神さまのみこころの最も基本的なことです。 |
|
|
||