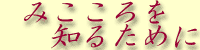 |
(第32回)
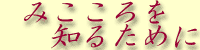 |
|
説教日:2000年1月9日 |
|
普通、自由といいますと、何にも束縛されないで、好きな時に好きなことができるというような、「行動の自由」を考えます。しかし、それだけですと、人間より動物の方が自由であると言えるかもしれません。 私たちの行ないは、私たちの思いや考えを表現します。もちろん、私たちは、自分の思いや考えを隠してしまうことがあります。その意味では、私たちの行ないが、私たちの思いや考えを表現していないということになります。しかし、自分の思いや考えを隠すという行ないも、私たちの考えによることですので、別の意味で、私たちの思いや考えを表現しています。その意味では、人間の自由の出発点は、自由に考えることや思うことにあります。 しかし、私たちが何を考えるかということも、どのように考えるかということも、私たち自身の意志で決定することです。人間は、自分が何をどのように知るかということも、また、何をどのように考えるかということも、自分の意志で選び取っています。 たとえば、私たち神の子どもにとって、神さまの御言葉は決定的に大切なものです。神さまは、私たちが成長するに従って、さらに豊かにご自身を知らせてくださり、ご自身の愛と恵みを悟らせてくださいます。その際に神さまがお用いになるのが御言葉です。御霊が御言葉を悟らせてくださることによって、私たちは神さまと神さまの愛と恵みに満ちたみこころを知るようになります。それで、教会は、「神さまが恵みを与えてくださるために用いてくださる『恵みの手段』は御言葉である。」と告白してきました。 そのように、御言葉に耳を傾けて、御言葉を悟ることは、神の子どもとしての私たちのいのちに関わることで、決定的に大切なことです。そうではあっても、私たちが御言葉を知ることが大切なことであると考えるかどうかは、私たちが自分の自由な意志で決めることです。また、実際に、御言葉に耳を傾けるかどうかも、私たちが自分の自由な意志で選ぶことですし、悟った御言葉に沿って歩むかどうかも、私たちが自分の自由な意志で選ぶことです。 神の子どもとしての私たちのいのちに関わる御言葉についてであってもこうです。私たちが何をどのように知るかということも、何をどのように考えるかということも、私たち自身が自分の意志で決めることです。 その一方で、その逆の関係もあります。私たちに思うことも考えることもなければ、いくら意志が自由であっても、働きようがありません。私たちの自由な意志は、私たち自身の思いや考えに基づいて働きます。私たちは、自分の思いや考えに基づいて働く意志によって行動します。 このように、私たちの自由な意志と、私たちの思いや考えは、いわば、相互に関係し合っています。そして、私たちの心の働きを形作っています。このような、私たちの心の働きの自由を「良心の自由」と呼んでいます。この「良心の自由」は、「神のかたち」に造られており、自由な意志を持つ人格的な存在としての人間の自由の出発点であり中心です。 神さまは、「神のかたち」に造られている人間が、自由な意志を持つ人格的な存在としての特性を発揮するようになるために、人間の心に、 心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。 という第一の戒めと、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。 という第二の戒めに集約され、まとめられる、「愛の律法」を記してくださいました。 人間が「神のかたち」に造られているということは、愛の神さま── 愛を本質的な特性とする神さまのかたちに造られているということです。それで、「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性も愛です。もちろん、これは、罪を犯して堕落する前の、人間の本来の状態です。 また、「神のかたち」に造られている人間の心に「愛の律法」が記されているということは、自分の思いや考えを生み出す心そのものの特性、特に、自由な意志の特性が愛であるということを意味しています。 それで、「神のかたち」に造られている人間の心に「愛の律法」が記されているということは、「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性が愛である、ということと同じことを意味しています。ただ、人間の心に「愛の律法」が記されているということには、少し特殊な意味合いがあって、「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性が愛であることを意味するとともに、その愛が、人間の心の働きを通して、特に、自由な意志を通して、表現されるものであるということを意味しています。 神さまが、「愛の律法」を、「神のかたち」に造られている人間の心に記してくださったということは、「愛の律法」が外からの押しつけではなく、自分自身の律法となっていることを意味しています。言い換えますと、「神のかたち」に造られている人間にあっては、「愛の律法」がそのまま自分の思いとなり、意志となっているということです。 ですから、「神のかたち」としての人間の本質は、自由な意志を持つ人格的な存在であることにありますが、その自由な意志は、気ままに動くのではなく、自らの心に記されている「愛の律法」に導かれ、「愛の律法」に従って働きます。「神のかたち」に造られている人間の自由な意志が意志することは、自然と、「愛の律法」に沿っているのです。 このように、「神のかたち」に造られている人間の心に記されている「愛の律法」は、自分自身の人格の本質的な特性である愛を表現するものです。「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性が愛であることは、その心に記されている「愛の律法」を通してあかしされるのです。 このことを、先ほどお話ししました、私たちが何をどのように知るかということも、私たち自身が自分の意志で決めることである、ということに当てはめるとどうなるでしょうか。それは、「神のかたち」に造られている人間としての本来の姿においては、自分が何をどのように知るかを選び取ることに、愛が表現されるようになるということです。私たちが何かを知ることには、いろいろな条件が重なりあっていますが、一番深いところでは、造り主である神さまを愛し、隣人を愛するということを根本的な動機として、知るべきことを選び取っていくということです。 そのように、愛を根本的な動機としているときには、人は、造り主である神さまに対しても、隣人に対しても、真実であろうとします。それで、真理を知ろうとするようになります。また、神さまご自身と、神さまがお造りになった世界をより深く知ることを願うようになりますし、同じく「神のかたち」に造られている人間として、お互いをより深く理解し合いたいと願うようになります。 このようにして、「神のかたち」に造られている人間の本来の姿においては、人間の知的な活動を初めとする、さまざまな文化的な活動も、自らの心に記されている、 心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。 という第一の戒めと、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。 という第二の戒めに集約され、まとめられる、「愛の律法」に導かれたものとなります。 したがって、天地創造の初めに「神のかたち」に造られている人間に委ねられた、 生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。 創世記1章28節 という「歴史と文化を造る使命」も、その本来の姿においては、人間の心に記されている「愛の律法」に導かれて遂行されるものです。また、その「歴史と文化を造る使命」の遂行を通して、「神のかたち」に造られている人間の本質的な特性である愛が表現されるのです。 私たちは、御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いにあずかって、法的には、罪を完全に清算され、神の子どもとしての身分を与えられています。そして、御霊のお働きによって、御子イエス・キリストの復活のからだに結び合わされ、そのいのちに生かされていることによって、神の子どもとしての実質が内側に造り出されています。これによって、私たちは、地上の生涯を通して常に、神の子どもとして成長することができます。 それは、御子イエス・キリストの贖いの御業にあずかって神の子どもとされている者たちにおいて、天地創造の初めに「神のかたち」に造られている人間に委ねられた「歴史と文化を造る使命」を遂行する、本来の姿が回復されつつあるということを意味しています。私たちも、御霊が私たちの心に回復してくださっている「愛の律法」に導かれて、物事を知ることから始まって、さまざまなことを行なうように造り変えていただいています。 私たちは神の作品であって、良い行ないをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行ないに歩むように、その良い行ないをもあらかじめ備えてくださったのです。 エペソ人への手紙2章10節 「神のかたち」に造られている人間は、自らの心に記されている「愛の律法」に従って、「神のかたち」の本質的な特性である愛のうちに生きるときに、自由であることができます。その自由の出発点にあり、中心にあるのが「良心の自由」です。繰り返しになりますが、「神のかたち」に造られている人間として、自由な意志ばかりでなく、思うことや考えることや感じることも、「愛の律法」に導かれているときに、その人は「良心の自由」の状態にあると言えます。 これまで、私たちを愛してくださり、ご自身の意志で十字架への道を歩まれて、実際に、十字架につけられた御子イエス・キリストが、「良心の自由」という点から見ると、最も自由な状態にあったということをお話ししてきました。そして、先週は、イエス・キリストが十字架につけられるために渡された夜に、ゲツセマネにおいて祈られた祈りから、イエス・キリストがご自身の内側において「引き裂かれておられた」ことをお話ししました。 イエス・キリストは、私たちの罪に対する神さまの最終的なさばきをお受けになるために十字架におつきになりました。その時には、十字架刑の苦しみばかりでなく、私たちの罪に対する神さまの聖なる御怒りが余すところなく注がれて、父なる神さまとの交わりがまったく絶たれてしまうという、霊的な苦しみを味わわなければなりませんでした。 イエス・キリストは、そのような苦しみは何としても避けたいという、最も自然で当然の願いと、私たちを愛して、私たちの罪のためのなだめの供え物としてご自分(イエス・キリスト)をお遣わしになった父なる神さまのみこころに従いたいという願いとの間に、引き裂かれていたのです。ゲツセマネの祈りにおいては、そのような、ご自身の内なる葛藤が父なる神さまに告白されました。 そして、その祈りにおいてさらに力づけられて、父なる神さまのみこころをご自身のみこころとして、十字架におつきになる道をお選びになられました。 このことから、「良心の自由」の中にあるからといって、必ずしも、自分自身の内側に何の葛藤もないわけではない、ということが分かります。また、「良心の自由」を守るために内的な葛藤を経験することは、必ずしも罪であるわけではないことも分かります。 先週お話ししましたように、罪に満ちたこの世にあり、私たち自身の中になおも罪の性質が残っている状態にあっては、私たちは、「良心の自由」を守るためには、さまざまな葛藤を経験しなくてはなりません。 もし、私たちがマインドコントロールによって、人格的な自由を失っているとしたら、内側の葛藤は少なくなることでしょう。ですから、内側に葛藤があることは、「良心の自由」が働いていることのしるしでもあります。そして、そのような葛藤の中で、「愛の律法」に導かれて、神さまへの愛と隣人に対する愛を選び取ることに、人格的な自由としての「良心の自由」の現われがあります。 そのように、さまざまな葛藤の中で、「良心の自由」に従って、神さまへの愛と、隣人への愛を選び取ることは、愛による人格的な「応答」をすることです。それは、外側からの「刺激」に対する反射的な「反応」とは区別されます。 無限の栄光の神の御子イエス・キリストが十字架におつきになった時、総督ピラトの兵士たちは、イエス・キリストにつばきをかけ、葦で頭を叩いて嘲弄しました。人々は、十字架につけられたイエス・キリストに、さまざまなあざけりとののしりの言葉を投げつけました。 イエス・キリストがそのことに鈍感になって、何も感じなかったということはありえません。そのような仕打ちを受けることの無念さと悲しみを、十分すぎるほど味わっておられたはずです。 しかし、それに対するイエス・キリストの「応答」は、基本的には、沈黙でした。預言者イザヤが、 彼は痛めつけられた。 彼は苦しんだが、口を開かない。 ほふり場に引かれて行く小羊のように、 毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、 彼は口を開かない。 イザヤ書53章7節 と預言していたとおりです。 また、ペテロも、 ののしられても、ののしり返さず、苦しめられても、おどすことをせず、正しくさばかれる方にお任せになりました。 ペテロの手紙第一・2章23節 とあかししています。 そればかりでなく、ルカの福音書23章34節に、 そのとき、イエスはこう言われた。「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」 と記されていますように、ご自身を侮辱し、辱める者たちのために執り成しの祈りをささげておられます。まさに、 自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。 マタイの福音書5章44節 というご自身の「愛の律法」に導かれてのことです。 また、このことから、先ほどのペテロの、 ののしられても、ののしり返さず、苦しめられても、おどすことをせず、正しくさばかれる方にお任せになりました。 というあかしの中で、 正しくさばかれる方にお任せになりました。 と言われているのは、個人的な恨みを神さまに晴らしていただこうとする姿勢ではないことが分かります。「正しくさばかれる方にお任せに」なるに当たって、自分に不当な仕打ちを加えている人々のために執り成しておられるのです。 このように沈黙を守り通されたことも、執り成しの祈りをささげられたことも、外側からの「刺激」に対する単なる「反応」を越えた、「良心の自由」に基づく人格的な「応答」です。自由な意志が「愛の律法」に導かれるところから生み出される人格的な「応答」です。 私たちの場合を考えてみますと、私たちにとって、単なる反応は、反射的なものであり、習慣的なものです。それには、私たちのうちに残っている罪の性質── 罪の自己中心性が影を落としています。 私たちは、御子イエス・キリストの贖いの恵みによって、神の子どもとしての「良心の自由」を回復されています。それで、外側からの「刺激」に対してただ「反応」するだけの状態を越えて、「良心の自由」に基づく「応答」をすることへと招かれています。 このようなことを踏まえておきますと、たとえば、ガラテヤ人への手紙5章13節〜15節の、 兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。律法の全体は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という一語をもって全うされるのです。もし互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。 という戒めが、「良心の自由」に基づく「応答」を求めるものであることが分かります。 改めて説明するまでもありませんが、ここで、私たちが「自由を与えられるために召された」と言われているときの「自由」は、神の子どもとしての「良心の自由」に基づいて、人格的な「応答」をする自由です。── 御子イエス・キリストの贖いの恵みによって「神のかたち」の本来の栄光と尊厳性を回復していただいている者として、「愛の律法」に導かれて「応答」をする自由です。 これに対しまして、 もし互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。 と言われていることは、外側からの「刺激」に反射的、習慣的に「反応」しているだけのことです。私たちのうちから出てくる反射的、習慣的な「反応」には、私たちの罪の自己中心性が深く影を落としていますから、外側からの「刺激」のうち、自分より優れたものにはねたみ、言葉などの行き違いには憤りや恨み、といった「反応」が出てきてしまいます。そこから「互いにかみ合ったり、食い合ったり」と言われている状況が生まれてきます。 私たちが神の子どもとしての「良心の自由」に基づいて、人格的な「応答」をすることができるためには、先週お話ししましたように、まず、自分が、御子イエス・キリストの贖いの恵みによって神の子どもとしての「良心の自由」を中心とする「神のかたち」の本来の栄光と尊厳性を回復していただいていることを信じることが大切です。 それとともに、このガラテヤ人への手紙5章では、先ほどの13節〜15節の戒めに続く16節では、 私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。 と言われています。 この戒めに至るまでの流れを見ますと、13節では、 兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。 と言われていました。 この「肉の働く機会」の「肉」(サルクス)は、肉体(ソーマ)のことではありません。説明するのが少し難しいのですが、この「肉」は、罪によって堕落している人類全体を動かしている動因と言ったらいいでしょうか。広く採用されている言葉で言い換えますと、御子イエス・キリストの贖いに基づく御霊のお働きによって実現する「新しい時代」に対する、「この世」、「この時代」を「この世」、「この時代」としての特徴を持ったものとして生み出す動因です。また、この「肉」は、サタンを「この世」、「この時代」で働きやすくしていますが、サタンのことではありません。 自分のうちに罪の本性を宿している人はみな「肉」の働きかけを受けています。それで、私たち神の子どもも、 その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。 と戒められているのです。 「その自由を肉の働く機会と」してしまえば、神の子どもとしての「良心の自由」は失われ、外側からの「刺激」に「反応」して「互いにかみ合ったり、食い合ったり」と言われている状況が生まれてきます。 これに対して、16節では、 私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。 と言われていて、「その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕え」るようになる── 神の子どもとしての「良心の自由」に基づく人格的な「応答」をするようになる秘訣が示されています。 御霊は、御子イエス・キリストが成し遂げてくださった贖いを私たちに当てはめてくださいます。そして、実際に、私たちのうちに、神の子どもとしての「良心の自由」を中心とする「神のかたち」としての本来の栄光と尊厳性を回復してくださいました。また、私たちが、そのことを確信することができるように導いてくださっています。 このように、御霊は、私たちのうちに神の子どもとしての実質を生み出してくださり、神の子どもとしての確信を与え、神の子どもとしての歩みを導いてくださっています。 神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子どもです。あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、「アバ、父。」と呼びます。 ローマ人への手紙8章14節、15節 そのように導いてくださる中で、御霊は、私たちのうちに「良心の自由」に基づく人格的な「応答」── 「愛の律法」に導かれた「応答」を生み出してくださいます。なぜなら、ガラテヤ人への手紙5章22節、23節で、 御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。 と言われていますように、御霊の実は、その第一に挙げられている愛によってまとめられるものだからです。 御霊が私たちのうちに生み出してくださる「良心の自由」に基づく人格的な「応答」は、一回限りのものではありません。一回限りの「応答」というのは、「反応」と変わるところがない場合が多いのです。 御霊が生み出してくださる人格的な「応答」は、お互いの間のさまざまな行き違いや葛藤の中であっても、「寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制」という御霊の実の特性をもって「応答」し合うこと、すなわち、神の子どもとしての対話や話し合いを生み出します。 それは、外側からの「刺激」に対して「反応」する関係から、外側からの「刺激」に対して、なおも人格的な「応答」をする関係を経て、お互いに人格的に「応答」し合う関係を生み出すことを意味しています。 |
|
|
||