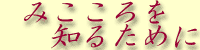 |
(第18回)
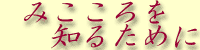 |
|
説教日:1999年9月12日 |
|
神さまは、私たちをご自身との愛の交わりに生きる神の子どもとしてくださるという、永遠の聖定において定められたみこころを実現してくださるために、天地創造の初めに、人間を「神のかたち」にお造りになりました。そして、人間を、ご自身の契約によって、ご自身との愛の交わりのうちに生きるものとしてくださいました。その意味で、私たちと神さまとの交わりは、神さまが一方的な恵みによって私たちに与えてくださっている契約に基づく交わりです。
その意味で、神さまの律法は、神さまの契約に関わるものです。律法は、神さまの一方的な恵みによって、神さまとの愛の交わりの中に入れていただいている人間に対して、どのように、ご自身との交わりをもつべきであるかを示してくださったものです。 ですから、神さまの律法は、それを守ることによって、神さまとの愛にある交わり、すなわち、永遠のいのちに入れていただくための手段ではありません。神さまとの愛にある交わりに入れていただくことは、神さまの一方的な恵みによっています。──天地創造の初めに人が「神のかたち」に造られて、神さまとの愛の交わりに入れていただいたのは、神さまの一方的な恵みによっています。また、人間が罪を犯して堕落し、神さまとのいのちの交わりを失い、死と滅びの力に捕らえられてしまったときに、御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いをもって、私たちを再びご自身とのいのちの交わりに回復してくださったのも、神さまの一方的な恵みによっています。 律法は、神さまとの愛の交わりに入れていただくための手段ではなく、すでに、神さまの一方的な恵みによって神さまとの愛の交わりに入れていただいている者が、どのように、神さまとの交わりをもつべきかを示すものです。ですから、律法は、「神のかたち」に造られている人間と造り主である神さまの関係のあり方、交わりのあり方を示すものです。 マタイの福音書22章35節〜40節には、 そして、彼らのうちのひとりの律法の専門家が、イエスをためそうとして、尋ねた。「先生。律法の中で、たいせつな戒めはどれですか。」そこで、イエスは彼に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』これがたいせつな第一の戒めです。『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』という第二の戒めも、それと同じようにたいせつです。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。」 と記されています。 「律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。」というイエス・キリストの御言葉に示されていますように、神さまの律法は、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という戒めと、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という戒めに集約され、まとめられます。 「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という「第一の戒め」の「あなたの神である主」という言葉が、この戒めを理解するための鍵です。「あなたの神である主」の「主」は、契約の神である主を示しています。そして、この「主」が「あなたの神」と呼ばれていることは、この戒めを受けた者がすでに神さまとの契約関係にあって、神である主の民とされていることを示しています。 ですから、この「第一の戒め」は、すでに、神さまとの契約関係にある者が、どうあるべきであるかを示すものです。神さまの一方的な恵みによって、ご自身との契約関係に入れていただいている者は、全身全霊をもって、契約の神である主を愛しなさいということです。 すぐにお分かりのように、この「第一の戒め」によって命じられていることは、神さまの一方的な恵みによって、ご自身との愛にある交わりに入れていただいている者にとっては当然のことであるばかりか、自然なことです。神さまは人間を神さまを愛するものとしてお造りになり、ご自身との契約関係に入れてくださいました。それで、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という戒めが与えられているのです。 律法の全体を集約する「第一の戒め」が、「神のかたち」に造られている人間にとって最も自然な姿を示しています。そうであれば、この「第一の戒め」によってまとめられる律法のすべての戒めが命じていることは、「神のかたち」に造られている人間にとって、当然のことであるばかりか、自然なことなのです。 いわば、律法の「第一の戒め」では、神さまが、「わたしはあなたを愛の中に生きるものとして造りました。ですから、愛の中に生きなさい。」と言ってくださっているわけです。その他のすべての戒めでも同じです。一般化した言い方をしますと、神さまが、「わたしは、あなたをこのようなものとして造りました。ですから、このように生きなさい。」と言っていてくださっているのです。──神さまは、律法の戒めをとおして、私たちに、「『神のかたち』に造られている人間の本来の姿でありなさい。」と戒めておられるのです。 それで、神さまの律法の戒めを見れば、「神のかたち」に造られている人間が、本来、どのようなものであるかが分かります。また、そうであるから、今日では、律法に照らして見ると、私たちが罪によって、どれだけ本来の姿から外れてしまっているかが分かるようになります。ローマ人への手紙3章20節で、 律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。 と言われているとおりです。 神さまの律法は、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という戒めと、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という戒めに集約され、まとめられます。 この二つの戒めに示されていることは、神さまの律法の根本精神であり、神さまの律法の一つ一つの戒めは、すべて、この根本精神の表現です。 このことをより具体的に述べているのは、ローマ人への手紙13章8節〜10節です。そこでは、 他の人を愛する者は、律法を完全に守っているのです。「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という戒め、またほかにどんな戒めがあっても、それらは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」ということばの中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は律法を全うします。 と言われています。 このローマ人への手紙13章8節〜10節では、前後関係から分かりますように、神の民のお互いの関係のことが取り上げられています。そのお互いの関係のことに関する律法の戒めとして、「『姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。』という戒め」が取り上げられています。これは、十戒の第6戒、7戒、8戒、10戒に当たる戒めです。 神の民のお互いの関係に関する戒めは、十戒の後半である第5戒から10戒までの戒めに要約されます。そして、それらの戒めはさらに、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という戒めによって要約されるというのです。 このことは、私たちが神さまの律法の戒めを理解するうえで、大切なことを示しています。それは、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という律法の戒めは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めに裏打ちされているということです。 このことは、二つの面から考えられます。 第一に、「自分は姦淫したこともないし、人を殺したこともない。また、人のものを盗んだこともないし、むさぼったこともない。」と言って、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という戒めを守っていると主張する人がいます。つまり、悪いことは何もしていないから、神さまの律法を破ってはいない、ということです。 しかし、神さまの律法についてのそのような理解には、根本的な欠陥があります。その人は、自分たちの標準や世間の標準で見て、悪いことは何もしていないと、しかも自分で、言っているだけです。それは、必ずしも、神さまの律法の戒めを守っているということにはなりません。 聖書は、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という、神さまの律法の戒めは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めにまとめられ、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めに裏打ちされていると教えています。 なぜ姦淫しないのでしょうか。それは、その人を愛するからです。なぜ殺さないのでしょうか。それは、その人を愛するからです。なぜ盗まないのでしょうか、それは、その人を愛するからです。なぜむさぼらないのでしょうか、それは、その人を愛するからです。 「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という、神さまの律法の戒めは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めの具体的な表現です。ですから、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めに従って、その人を愛し、その人の「神のかたち」としての尊厳性を大切にしていないなら、いくら、形として、姦淫していない、殺していない、盗んでいない、むさぼってはいないと言い張っても、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という、神さまの律法の戒めを守っているということにはならないのです。 ルカの福音書18章9節〜14節には、次のような、イエス・キリストのたとえが記されています。 ふたりの人が、祈るために宮に上った。ひとりはパリサイ人で、もうひとりは取税人であった。パリサイ人は、立って、心の中でこんな祈りをした。「神よ。私はほかの人々のようにゆする者、不正な者、姦淫する者ではなく、ことにこの取税人のようではないことを、感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげております。」ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。」あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。 この個所からは、色々なことが考えられますが、今お話ししていることとの関連で言いますと、このパリサイ人は、自分のことを「ゆする者、不正な者、姦淫する者ではなく」と言いながら、自分の隣りにいる「取税人」を見下しています。神さまの律法の条文を守ってはいますが、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めを守っていないのです。それでは、神さまの律法の戒めを守っている状態にはありません。 私たちも、自分の標準で、きよく正しく、品行に気をつけているからということで、このパリサイ人の感じ方と同じようになってしまってはいないでしょうか。 これが、お互いの関係に関する律法の戒めは、すべて、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めに裏打ちされている、ということから考えられる第一のことです。 第二のことは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めは、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という律法の戒め、あるいは、その他の、お互いの関係に関するさまざまな戒めによって、具体的な形で表現されているということです。 先ほどの「他の人を愛する者は、律法を完全に守っているのです。」という御言葉を盾に取って、自分は他の人を愛しているから、神さまの律法の戒めを守っている、と主張する人がいるかもしれません。 その主張は、そのとおりです。しかし、そこには、注意しなくてはならないことがあります。それは、その人が「自分は他の人を愛している。」ということがどういうことであるか、ということです。多くの場合には、それは、自分の気持ちで愛しているということか、自分なりの愛し方で愛しているということです。 しかし、聖書は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めは、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という律法の戒め、あるいは、その他のお互いの関係に関するさまざまな戒めによって、具体的な形で表現されていると教えています。ですから、自分の気持ちでは他の人を愛しているつもりでも、「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という律法の戒め、あるいは、その他のお互いの関係に関するさまざまな戒めに従っていないなら、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めを守っているとは言えないのです。 ヤコブの手紙2章8節〜11節では、 もし、ほんとうにあなたがたが、聖書に従って、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という最高の律法を守るなら、あなたがたの行ないはりっぱです。しかし、もし人をえこひいきするなら、あなたがたは罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯した者となったのです。なぜなら、「姦淫してはならない。」と言われた方は、「殺してはならない。」とも言われたからです。そこで、姦淫しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。 と言われています。 お互いの関係に関する神さまの律法のさまざまな戒めは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めにまとめられるだけでなく、具体的な状況において、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めを守るための指針なのです。 形として、お互いの関係に関する神さまの律法のさまざまな戒めを守っていても、その人を愛していないなら、神さまの律法に従っているとは言えません。それと同時に、お互いの関係に関する神さまの律法のさまざまな戒めに導かれていなくては、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めに従って、その人を愛しているとは言えないのです。ですから、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めさえ頭に入れておけば大丈夫であるということにはなりません。 ローマ人への手紙13章8節〜10節で、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という根本的な戒めにそって、「他の人を愛する者は、律法を完全に守っているのです。」と言われているのは、そこでは、神の子どもたちのお互いの関係のことが問題になっているからです。しかし、マタイの福音書22章35節〜40節に記されているイエス・キリストの教えにありますように、神さまの律法のいちばん大切な「第一の戒め」は、神さまとの関係のあり方を示す、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という戒めです。 この「第一の戒め」につきましても、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という「第二の戒め」について、これまでお話ししてきましたことがそのまま当てはまります。 「自分は、天地の造り主である神さまだけを神としている。偶像を拝んではいない。安息日を守っている。」ということで、直ちに、神さまの律法を守っているということにはなりません。もし「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という根本的な戒めが示しているように、全身全霊をもって、神さまを愛していなければ、それは、形としては、天地の造り主である神さまだけを神としており、偶像を拝まず、日曜日には礼拝をしている、というだけのことです。 同時に、いくら「自分は、全身全霊をもって、神さまを愛している。」と言っても、その人が、神さまとの関係に関する具体的な律法の戒めに従っていないとしたら、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」という根本的な戒めを守っているということにはなりません。 ヨハネの手紙第一・5章3節では、 神を愛するとは、神の命令を守ることです。 と言われています。また、イエス・キリストも、 わたしの戒めを保ち、それを守る人は、わたしを愛する人です。わたしを愛する人はわたしの父に愛され、わたしもその人を愛し、わたし自身を彼に現わします。 ヨハネの福音書14章21節 と言われました。 |
|
|
||