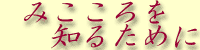 |
(第12回)
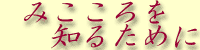 |
|
説教日:1999年7月18日 |
|
神さまは、この世界をお造りになること、それをどのようなものとしてお造りになるか、そして、お造りになるすべてのものがどのような在り方をすべきであるかを、永遠に定めておられます。それを(永遠の)「聖定」と呼びます。 神さまは、ご自身の聖定、すなわち、「永遠のみこころ」に従って、この世界をお造りになりました。そして、同じ「永遠のみこころ」に従って、お造りになったすべてのものを支えてくださり、導いてくださっています。その、最終的な目的は、ご自身の栄光を現わすことです。 この世界は、神さまの栄光を映し出すものとして造られているので、壮大で、神秘的で、複雑でありながら、調和が取れていて美しく、法則を観察することができるほどに秩序が整っていながら、明るく暖かい世界であるのです。 神さまがこの世界とその中にあるすべてのものをお造りになった方ですから、神さまご自身が、造られたものにとっての意味と価値の最終的な基準です。──何が善いことであり、優れたことであるか、何が意味があることであり、価値があることであるかの最終的な基準は、神さまご自身であるということです。 それで、造り主である神さまの栄光を豊かに映し出すものであればあるほど、豊かな意味と価値をもつものとして造られていると言うことができます。また、豊かな意味と価値をもつものとして造られていればいるほど、造り主である神さまの栄光を豊かに現わすようになります。 このことが、「神のかたち」に造られている人間の栄光と尊厳性の根底にあります。というのは、繰り返しお話ししてきましたように、「神のかたち」に造られている人間は、造られたものの中でも最も豊かに、造り主である神さまの栄光を現わすものとして造られているからです。 たびたび引用しています、詩篇8篇5節、6節では、「神のかたち」に造られた人間の栄光のことが、 あなたは、人を、神よりいくらか劣るものとし、 これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。 あなたの御手の多くのわざを人に治めさせ、 万物を彼の足の下に置かれました。 と告白されています。 この部分は、「神のかたち」に造られている人間の栄光の豊かさを告白していますが、全体として見ますと、この詩篇8篇は、1節と9節の、 私たちの主、主よ。 あなたの御名は全地にわたり、 なんと力強いことでしょう。 という讃美で始まっており、同じ讃美で結ばれています。ですから、詩篇8篇は、基本的には、造り主である神さまの栄光を讚えるものです。その中で、「神のかたち」に造られている人間の尊厳性と栄光が告白されているのです。 このことは、「神のかたち」に造られている人間の尊厳性と栄光の中心は、造り主である神さまの栄光を映し出すことにあり、神さまの栄光を映し出すことを離れて理解することはできない、ということを意味しています。 さらには、2節で、 あなたは幼子と乳飲み子たちの口によって、 力を打ち建てられました。 それは、あなたに敵対する者のため、 敵と復讐する者とをしずめるためでした。 と告白されていますように、神さまが、ご自身の栄光を映し出すものとしてお選びになったのは、人間の弱さであり、貧しさです。──あるいは、弱く貧しいものである人間です。 2節後半の、 それは、あなたに敵対する者のため、 敵と復讐する者とをしずめるためでした。 という言葉は、人間が罪を犯して堕落してしまった後に、その心が造り主である神さまから離れ、神さまの御前に高ぶって、神さまに敵対している者たちとの「霊的な戦い」が展開されている状況にあって、この詩篇が歌われていることを示しています。──その霊的な戦いの状況にあって、神さまが、ご自身の栄光の器としてお選びになったのは、弱く貧しいものである人間であることが示されているわけです。 それとともに、3節、4節で、 あなたの指のわざである天を見、 あなたが整えられた月や星を見ますのに、 人とは、何者なのでしょう。 あなたがこれを心に留められるとは。 人の子とは、何者なのでしょう。 あなたがこれを顧みられるとは。 と告白されているのを受けて、5節で、 あなたは、人を、神よりいくらか劣るものとし、 これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。 と歌い継がれています。 このことから、神さまが弱くて貧しいものである人間に心をかけてくださったのは、天地創造の初めに人が「神のかたち」に造られた時からのことであったことが分かります。 ですから、パウロが、 しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現われるからである。」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。 コリント人への手紙第二・12章9節 と述べていることは、人間が罪を犯して堕落したために生じた原則ではなく、天地創造の初めに、神さまが人間を「神のかたち」にお造りになった時からの、神さまのみこころなのです。──そのことが、福音の御言葉の中で繰り返し述べられているのは、人間が罪を犯して堕落してしまった後には、罪が生み出す高ぶりのために、そのことが見失われがちになっているからでしょう。 このように、詩篇8篇は、「神のかたち」に造られている人間の尊厳性と栄光は、造り主である神さまの栄光を映し出すことを離れては理解することはできないし、意味あるものとはならないということを示しています。また、神さまが、弱くて貧しいものである人間に心をかけてくださって、人間を「神のかたち」にお造りになったことに、人間の尊厳性と栄光の起源があることを示しています。 このことは、弱くて貧しいものである人間が「神のかたち」の栄光と尊厳性を与えられていることを通して、 私たちの主、主よ。 あなたの御名は全地にわたり、 なんと力強いことでしょう。 と、神さまの栄光が讚えられるようになるためであることを意味しています。 パウロが、コリント人への手紙第二・12章9節で、 ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。 と述べているのも、また、同じ手紙の4章7節で、 私たちは、この宝を、土の器の中に入れているのです。それは、この測り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。 と述べているのも、これと同じ精神を示しています。 このように見てみますと、御言葉が、私たちの弱さや貧しさを心に刻むべきことを教えているのは、私たちが、お互いを比べて、高ぶったりひがんだりする流れの中でのことではないことが分かります。私たちが、自らの弱さと貧しさを心に刻むのは、あくまでも、造り主である神さまとの関係においてのことです。 このことから、いくつかのことが考えられます。 第一に、詩篇8篇が示していますように、私たちは、天と地の造り主であり、無限、永遠、不変の、造り主である神さまの御前に立って初めて、本当の意味での、自分たちの弱さと貧しさを知ることができます。 第二に、神さまの御前で自らの弱さと貧しさを知ることは、ひがみやねたみを生み出すことはありません。むしろ、人間がお互いに比べ合うことから生まれてくる、誇りや高ぶり、ねたみやひがみを消し去ります。 第3に、神さまの御前で自らの弱さと貧しさを知ることによって、私たちは、このような弱く貧しい者たちを心に留めてくださっている神さまの愛と恵みの豊かさに触れることができるようになります。そして、詩篇8篇が示していますように、神さまの愛と恵みの豊かさに驚きつつ、神さまの御名を讚えるように導かれます。 第4に、これと関連することですが、神さまの御前で自らの弱さと貧しさを知ることによって、また、実際に、弱く貧しい者たちを心に留めてくださっている神さまの愛と恵みの豊かさに触れることによって、私たちは、神さまの愛と恵みの豊かさによって支えられている、「神のかたち」としての尊厳性と栄光を「誇る」ことができるようになります。 まさしく、「誇る者は主にあって誇れ。」と書かれているとおりになるためです。 コリント人への手紙第一・1章31節 と言われていることも、やはり、天地創造の初めに、神さまが人間を「神のかたち」にお造りになった時からの、神さまのみこころなのです。 神さまは、私たちに、真に誇るべきものを与えてくださっておられます。ですから、私たちから一切の誇りを取り去って、卑屈なものとしてしまわれることはありませんし、私たちが誇るべきものを誇ることを否定しておられるのではありません。ただ、罪を犯して堕落してしまっている人間が、お互いを比べ合うことから生まれてくる「誇り」を、「真に誇るべきもの」と取り違えてしまっているために、造り主である神さまの御前においてだけ自覚することができる「神のかたち」の栄光と尊厳性に関わる誇りを見失ってしまっていることが問題なのです。 お互いを比べ合うことから生まれてくる「誇り」は、比較の中での誇りですので、自分より「優れたもの」が出てくることに耐えられません。そのような誇りは、自分より「優れたもの」が出てくると、たちまちのうちに、ねたねたやひがみに変わってしまいます。 ルカの福音書18章9節〜14節には、パリサイ人と取税人が、祈るために宮に上ったという、イエス・キリストのたとえが記されています。11節、12節には、 パリサイ人は、立って、心の中でこんな祈りをした。『神よ。私はほかの人々のようにゆする者、不正な者、姦淫する者ではなく、ことにこの取税人のようではないことを、感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげております。』 と記されています。 広く指摘されていますように、このパリサイ人の問題は、自分がしていることを、繰り返し神さまの御前に主張していることにあります。ギリシャ語原文では、11節の「私は」は強調形です。パリサイ人は、自分の行ないによる義を立てようとしています。 それとともに、注目したいのは、「ことにこの取税人のようではないことを、感謝します。」という言葉に示されていますように、「パリサイ人の義」は、あるいは、ここでのお話に合わせて言いますと、パリサイ人の「誇り」は、彼らがさげすんでいる「取税人」がいることによって引き立つ義であり誇りです。「取税人」あるいは一般の人々と比較して見たときに、引き立って見える義です。 もちろん、パリサイ人が自覚することはなかったでしょうが、パリサイ人にとって、「取税人」がいることは「ありがたいこと」なのです。逆に、罪のない方であり、罪を犯すことがなかったばかりでなく、神さまのみこころのうちを歩み続けられたイエス・キリストは、自分たちの義や誇りをおびやかす存在であったのです。このような、他人次第で引き立ったり、くすんでしまったりする義や誇りは、神さまの御前に通用するものではありません。 神さまは、私たちに、真に誇るべきものを与えてくださっておられます。私たちは、神さまの愛と恵みの豊かさによって支えられている、「神のかたち」の尊厳性と栄光を「誇る」ように招かれています。それは、神さまの愛と恵みの豊かさを頼みとし、誇ることに他なりません。 しかし、そのようになるためには、私たちが、お互いを比べ合うことから生まれてくる「誇り」を、「真に誇るべきもの」と取り違えてしまっている、罪がもたらす錯覚から解放されていなくてはなりません。 さらに、そのためには、パウロが、先ほど一部を引用しましたコリント人への手紙第一・1章26節〜31節で、 兄弟たち、あなたがたの召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者をはずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取るに足りない者や見下されている者を、神は選ばれました。すなわち、有るものをない者のようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは、神の御前でだれをも誇らせないためです。しかしあなたがたは、神によってキリスト・イエスのうちにあるのです。キリストは、私たちにとって、神の知恵となり、また、義と聖めと、贖いとになられました。 まさしく、「誇る者は主にあって誇れ。」と書かれているとおりになるためです。 と述べていますように、御子イエス・キリストの十字架の死によって私たちに示されている、神さまの愛と贖いの恵みの豊かさに、いつも触れていることが必要です。これによって示されている神さまの私たちに対する愛と恵みは、そのまま、天地創造の初めに人間を「神のかたち」にお造りになった時からの愛と恵みでもあります。 しかし、私たちは、それでも、いつの間にか、お互いを比べ合っては、誇ったりねたんだり、安心したり不安になったりしてしまいやすいものです。 その第一の原因は、言うまでもなく、私たちのうちに、今なお罪の性質が残っているからです。 私たちは、福音の御言葉があかししている御子イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いを信じて受け入れたことによって、罪を赦されています。その赦しは、イエス・キリストの完全な罪の贖いに基づくものですから、完全な赦しです。──この後、私たちが神さまの御前に罪に定められることは、決してありません。 けれども、私たちの実質は、今なお、少しずつ造り変えられつつあるという状態にあります。私たちのうちには罪の性質が残っており、実際に、私たちは、さまざまな罪を犯します。そのような私たちは、自己中心の誇り、あるいは、その裏返しのひがみをもちやすいものです。 私たちがお互いを比べ合っては、誇ったりひがんだり、安心したり不安になったりしてしまいやすいことには、さらに別の原因があります。 それは、私たちにとって、お互いの存在は、目に見えるため実感しやすいということです。 また、私たちが何かを比べるときには、そこに何らかの共通性がなければなりませんが、その共通性が多ければ多いほど比べやすいものです。同じ人間でも、よその国の人よりは、同じ職場や学校にいる人の方が比べやすく、誇ったりひがんだりしやすいものです。その意味で、私たちがお互いに比べ合うことは、すぐにできることです。 これに対して、私たちが、神さまとの関係で自分のことを見つめるということは、そして、「神のかたち」の栄光と尊厳性を、造り主である神さまの御前で理解して、わきまえるということは、すぐにできることではありません。 その最大の原因は、やはり、私たちのうちに、今もなお罪が残っているために、いつも神さまを中心としているわけではないことにあります。 それとともに、先週お話ししました、私たちには、神さまがここにおられることを感覚的に実感することができないということも、大きな理由になっていると思われます。 神さまを中心として生きるようになるためには、そして、自分を神さまとの関わりで理解するようになるためには、どうしても、神さまの御臨在の御前に近づいて、礼拝と讃美、御言葉に聞くことと祈りを通しての、神さまとの親しい交わりの中に生きていることが必要です。けれども、神さまの御臨在は、感覚で捉えることができません。 私たちにとって、神さまの御臨在は、御子イエス・キリストが十字架の上で流された血によって確立されている契約によって保証されています。ヘブル人への手紙10章19節で、 こういうわけですから、兄弟たち。私たちは、イエスの血によって、大胆にまことの聖所にはいることができるのです。 と言われているとおりです。 神さまは、御子イエス・キリストの血によって確立された契約の御言葉を信じて御許に来る者たちを、贖いの恵みによって包んでくださり、ご自身との愛の交わりの中に迎え入れてくださいます。──私たちは、自分の感覚によってではなく、信仰によってそれを信じて受け入れるのです。 繰り返しになりますが、私たちに対する神さまのみこころの中心は、私たちが、どのような場合にも、神さまの愛に包まれて生きることです。それは、私たちが御子イエス・キリストの血によって確立されている契約の御言葉を信じて御臨在の御前に近づくことによって実現します。 そして、この神さまとの愛にある交わりという祝福の中にあって初めて、私たちは、徐々にではありますが、罪の自己中心性から解放されていきます。そして、神さまの愛と恵みの豊かさによって支えられている、「神のかたち」としての尊厳性と栄光を、現実的に理解し受け止めることができるようになります。 |
|
|
||