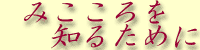 |
(第10回)
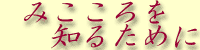 |
|
説教日:1999年7月4日 |
|
きょう、特に心に留めたいことは、神さまがご自身の「聖定的な意志」によって、私たちを「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」としてくださり、「御子のかたちと同じ姿」にしてくださるように定めてくださったのは、神さまの一方的で主権的な愛によっているということです。 そのことは、エペソ人への手紙1章4節、5節で、 神は私たちを世界の基の置かれる前からキリストのうちに選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされました。神は、ただみこころのままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられたのです。 と言われていることに示されています。 この「愛をもって」(直訳「愛にあって」)という言葉がどこにかかるかについては、意見が分かれています。新改訳は、「あらかじめ定めておられた」にかかると理解しています。私もそのように理解していますが、「どちらかと言えば」ということであって、もう一つの可能性を否定することはできないと思っています。 実は、この「愛にあって」という言葉は、ギリシャ語の原文では、4節の終わりに出てきます。ただし、節の区切りは便宜上のものであって、霊感されたものではありませんので、これが4節に記されていることにつながるか、5節に記されていることにつながるかの判断は、別個に判断しなくてはなりません。そして、文の構成の仕方などから、これは、4節に記されていることにつなげて理解すべきであると主張する人々もいます。 その場合には、4節は、 神は私たちを世界の基の置かれる前からキリストのうちに選び、御前で、愛にあって、聖く、傷のない者にしようとされました。 となります。この場合には、神さまは、私たちを愛のある者── 愛のうちに生きる「聖く、傷のない者」にしようと定めてくださったということになります。 この理解を取りますと、5節は、 神は、ただみこころのままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、あらかじめ定めておられたのです。 となり、そこには「愛にあって」という言葉はなくなります。そうであっても、「ご自分の子にしようと、あらかじめ定めておられた」ということ自体が、父なる神さまの私たちに対する愛の表現であることは、はっきりしています。 また、神さまが、ご自身の「聖定的な意志」によって、私たちを「御子のかたちと同じ姿」にしてくださるように定めてくださったのは、神さまの一方的で主権的な愛によっているということは、ローマ人への手紙8章29節で、 なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたからです。 と言われていることにも示されています。 この「あらかじめ知っておられる人々を」の「あらかじめ知っておられる」という言葉は、「永遠の前から愛しておられる」ということを意味しています。ここで、「あらかじめ愛しておられる」と言わないで、「あらかじめ知っておられる」と言われているのは、それによって、「永遠の愛によってお選びになっておられる」という意味合いをも伝えるためであると考えられます。 このように、神さまが、ご自身の「聖定的な意志」によって、私たちを「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」としてくださり、「御子のかたちと同じ姿」にしてくださるように定めてくださったのは、神さまの一方的で主権的な愛によっています。私たちには、永遠から、父なる神さまの愛が注がれているのです。 私たちに対する神さまの永遠の愛は、一方的で、主権的な愛ですが、愛は、一方通行で終わるものではありません。それは、愛による交わりを生み出します。ですから、神さまが、私たちを「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」としてくださり、「御子のかたちと同じ姿」にしてくださるように定めてくださったのは、私たちが、神さまとの愛による交わりに生きるようになるためです。神さまの愛を受け止めて、それに愛をもって応えるようになるためです。 神さまは創造の御業によって、「聖定的な意志」を実行に移されました。そして、摂理の御業によって、「聖定的な意志」に従って、すべてのものを支え導いてくださいます。 私たちに当てはめて言いますと、神さまは、創造の御業において、人を「神のかたち」にお造りになり、これに、「歴史と文化を造る使命」をお委ねになりました。そのことは、創世記1章27節、28節に、 神はこのように、人をご自身のかたちに創造された。神のかたちに彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた、彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。」 と記されています。 そして、さらに、摂理の御業を通して、私たちを「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」としてくださり、「御子のかたちと同じ姿」にしてくださるのです。 神さまが人間を「神のかたち」にお造りになり、これに、「歴史と文化を造る使命」をお委ねになったのは、人間が、神さまとの愛にある交わりのうちに生きるようにしてくださるためでした。そして、さらに、私たちを「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」とし、「御子のかたちと同じ姿」にしてくださるように導いてくださるのは、私たちが、神さまとのさらに深く豊かな愛の交わりのうちに生きるようにしてくださるためです。 このことは、前にお話ししたことがありますが、同じ創造の御業を、三位一体の神さまご自身とのかかわりで記している、ヨハネの福音書1章1節〜3節から、よりはっきりと知ることができます。 ヨハネの福音書1章1節〜3節では、 1 初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。 2 この方は、初めに神とともにおられた。 3 すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。 と言われています。 すでに、色々な機会にお話ししてきたことですので、詳しい説明は省きますが、1節と2節では、「ことば」として紹介されている御子が、永遠の神であられることと、父なる神さまとの永遠の愛の交わりの中にあることが示されています。──「ことばは神とともにあった。」と「この方は、初めに神とともにおられた。」の「神とともに」(プロス・トン・セオン)は、御子が父なる神さまと向き合っていることを暗示する言葉です。つまり、御子と父なる神さまの間に永遠の交わりがあることが示されています。 一位一体の神ですと、永遠の人格は一つしかないことになります。それで、「神は愛です。」(ヨハネの手紙第一・4章8節、16節)といっても、神には永遠の愛を通わす相手がいないことになってしまいます。しかし、ヨハネの福音書1章1節、2節では、御父と御子の間に、完全にして充満な愛が、永遠に通わされていることが示されています。 けれども、ここでは、ただ、御子が永遠の神であられることや、父なる神さまとの永遠の交わりの中にあること自体を伝えることが目的ではないようです。これを1章1節〜3節に限って見てみますと、その目的は、3節の、 すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。 という御言葉から汲み取ることができます。 この言葉は、すべてのものが例外なく、「この方によって造られた」ことを示しています。「この方」は、1節、2節が示しているように、永遠に、充満する愛において、父なる神さまとの交わりのうちにおられる御子です。ですから、3節は、父なる神さまとの愛の交わりにおいて完全な充足のうちにおられる御子が、すべてのものをお造りになったということを示しています。 この世界をお造りになった神さまは、愛の神です。しかも、完全な愛の性質と愛への飢え渇きはあるけれども、永遠の次元においてその愛に答えてくれる存在がいないというような、欠乏感のある神ではありません。三位一体の神さまのうちには、完全な愛が、永遠にまた無限に表現されています。神さまのうちには完全な愛の現実があり、神さまは完全な愛のうちに充足しておられます。 この、完全な愛のうちに充足しておられる神さまが、この世界と人間をお造りになりました。永遠に孤独な「神」が、その淋しさの中で、その愛への飢え渇きを満たす手慰めに、この世界と私たち人間を造ったのではありません。 このように、この世界は、完全な愛のうちに充足しておられる神さまの御手によって造られたものです。三位一体の神さまの御父と御子と御霊の交わりの中に、完全な愛が、永遠にまた無限に表現されています。神さまは、さらにその愛をご自身の外に向けて表現されるために、その充満な愛にうちに、この世界をお造りになりました。 このことと調和して、神さまは、この世界にあって、ご自身の愛を受け止める存在として人間をお造りになりました。永遠にして無限の愛における交わりの中に充足しておられる神さまが、その愛をご自身の外に向けて表現されるために、すべてのものをお造りになり、人間を「神のかたち」にお造りになりました。神さまが、人間を「神のかたち」にお造りになって、ご自身との交わりの中に生きるものとしてくださったのは、ご自身の欠けを満たすためではありません。むしろ、私たちを愛して、私たちをご自身の愛によって満たしてくださるためです。 これに対して、人間は、罪を犯して堕落して以来、造り主である神さまとの関係をそのように理解することはなくなってしまいました。 堕落後の人間が抱いている、神と人間の関係は、基本的に、奉仕の関係、あるいは、取引の関係です。人間が「神」に仕えると、「神」はそれに応えて、人間のために働いてくれるというのです。このように考えられている「神」は、決して自己充足している「神」ではありません。人間の奉仕を必要としている「神」です。 人間はなぜ「人間の奉仕を必要としている神」を考えてしまうのでしょうか。 その根本的な原因は、もちろん、人間が罪を犯して堕落して、その心が造り主である神さまから離れてしまっているからです。その結果、人間は造り主である神さまを見失ってしまいました。しかし、それによって、人間の中から「神への思い」がなくなってしまったのではありません。造り主である神さまとの交わりの中に生きるものとして、「神のかたち」に造られている人間の心の奥深くには「神への思い」があります。それで、人間は「神」を考えないでは生きられません。堕落によって、「神への思い」そのものが失われたのではなく、「神への思い」が歪んでしまったのです。本来は、その「神への思い」によって造り主である神さまに向く向くべきなのですが、偶像を生み出して「神への思い」を満たそうとするようになってしまったのです。このようにして、人間は、「神」を考えるときには、自分たちのイメージに合う「神」を考えるようになってしまいました。 罪を犯して堕落してしまった人間は、罪によって腐敗した本性の特徴である自己中心性によって動かされています。そこから、お互いの間に「利用し合う関係」が生まれてきます。相手が自分にとってどれだけ役に立つか、自分をどれだけ豊かにしてくれるか、より高尚には、自分を精神的にどれだけ高めてくれるかといったことから判断して、相手を評価するようなところがあります。 人間同士の間でそのような思いが働いているだけではなく、それが、「神」との関係にまで投影してしまいます。そこから、「神」を利用して自分の幸福を刈り取ろうとするご利益宗教が生まれてきます。人間と「神」との関係が、そのような利用し合う関係であるためには、「神」も人間を必要としていなくてはならないことになってしまいます。このようにして、人間の考える「神」は── 少なくとも、人間と関わって人間の願いに応えてくれると考えられている「神」は、何らかの意味で、人間の奉仕を必要としている「神」であるということになってしまうのです。 しかし、御言葉によりますと、神さまは無限、永遠、不変の神であり、あらゆる点において欠けることがなく、完全に充足しておられる方です。ですから、神さまは、人間の奉仕を必要としてはおられません。パウロが、使徒の働き17章24節、25節で、 この世界とその中にあるすべてのものをお造りになった神は、天地の主ですから、 ・・・ 人の手によって仕えられる必要はありません。神は、すべての人に、いのちの息と万物をお与えになった方だからです。 と言っているとおりです。 それでも、聖書の示すところでも、神さまは人間に奉仕を求めているではないか、という疑問が出されることでしょう。確かに、創世記1章26節においては、 そして神は、「われわれに似るように、われわれのかたちに、人を造ろう。そして彼らに、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配させよう。」と仰せられた。 と言われています。ここでは、神さまが、奉仕をさせるために人を造ったと言われているのではないでしょうか。 しかし、創世記1章に記されていることを全体として見てみますと、次のことが明らかです。 まず、人間に「海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配させ」るようになったとしても、それによって、神さまがそれらのものから手を引いてしまわれる訳ではないということです。それらすべてのものを支えておられるのは神さまです。神さまがお造りになり、神さまが支えていてくださるものを、人間は「神のかたち」に造られているものとして関わっていく使命を授けられているのです。ですから、これは、人間に仕事をさせて神が楽をするということとはまったく違います。 「神のかたち」に造られている人間に「歴史と文化を造る使命」が委ねられているのは、神さまの必要を満たすためでなく、むしろ、人間の「益」のためです。 この点につきましては、すでに、詩篇8篇3節〜9節などに基づいてお話ししましたので、まとめて言いますと、「神のかたち」に造られている人間は、造り主である神さまと、神さまがお造りになったすべてのものの間に立つ、「仲保者」の立場に立っています。人間は、神さまがお造りになったすべてのものを通して示されている神さまの栄光をくみ取り、その栄光を神さまにお返しすることを通して、すべてのものを巻き込んでいる、宇宙大の礼拝を主宰し、その中心にあって、造り主である神さまを礼拝するのです。 そして、人間は、このような使命を果たすことを通して、神さまがお造りになった世界のすばらしさにより深く触れることによって、造り主である神さまのすばらしさを、現実的に知ることができるようになります。 このように、創造の御業において、人間を「神のかたち」にお造りになった神さまは、それによって、人間をご自身との愛の交わりに生きるものとしてくださいました。 神さまは、さらに、摂理の御業において、ご自身の「聖定的な意志」に従って、私たちを導いてくださり、私たちが、「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」となり、「御子のかたちと同じ姿」となるようにしてくださいます。それは、私たちが、最初の「神のかたち」の栄光よりもさらに豊かな栄光をもつものとされて、神さまの御前にもっと近く近づいて、神さまとのより深く豊かな愛の交わりのうちに生きるようにしてくださるためです。 そのことは、神さまが、摂理の御業の中で特別に備えてくださった、ご自身の契約を通して、人間に示してくださり、約束してくださいました。そして、私たちが罪によって堕落してしまったにもかかわらず、最終的には、私たちの契約の主として神さまが立ててくださった御子イエス・キリストの十字架の死と死者の中からのよみがえりによって、実現してくださいました。 今、私たちは、御子イエス・キリストの血による契約にあずかって、すでに、「御前で聖く、傷のない者」、「ご自分の子」とされており、実際に、「御子のかたちと同じ姿」に造り変えられつつあります。その完成は、世の終わりにイエス・キリストが再臨されて、ご自身の民の救いを完成してくださる時に実現しますが、私たちは、すでに、父なる神さまと御子イエス・キリストとの愛による交わりの中に導き入れられています。 私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。 ヨハネの手紙第一・1章3節 そうであれば、私たちに対する神さまのみこころは、どのような場合にも、御子イエス・キリストの血によって確立されている契約によって保証されている、神さまの愛のうちにとどまり続けることにあります。 |
|
|
||