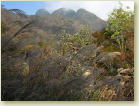| 日時 2006年10月21日 天気 登山コース 和佐又山ヒュッテ ⇒ 大普賢山頂 ⇒ 七曜岳 ⇒ 無双洞 ⇒ 底無井戸 8時 9時50分(休憩20分) 11時30分(休憩20分) 12時40分(昼食40分) 和佐又のコル ⇒ 和佐又ヒュッテ 14時40分 (歩数 22571歩) 美しい大普賢岳の黄・紅葉が見たくて今年も登って来ました。 8月は暑くて体力・気力もなく大普賢岳ピストンで終ってしまいましたが、今回は無双洞の周回コースを歩いて来ました。 下山後は和佐又山キャンプ場に泊まって、翌日は大台ケ原も少し歩いて来ました。 6時に自宅出発、R169の伯母峰トンネルを貫け、右に折れ林道を和佐又ヒュッテまで上がります。 8時前に到着、駐車場はほぼ満車、ヒュッテでキャンプ場を利用する事を言い、下山後に受付を頼んで歩き始めます。 和佐又のコルを右折れ、ブナが黄葉しかけた稜線を登り、指弾ノ窟・朝日ノ窟・笙ノ窟・鷲ノ窟を過ぎ、日本岳のコルに着きました。 ガスが立ち込めて何も見えない。 前回の稲村・山上もガスの中の歩きでした。今回も〜 石の鼻からも鋭く落ち込んだ地獄谷や大台ケ原の山々の展望もなく、後続の人に直ぐ場所を譲りました。 ここからはクサリ・鉄梯子・鉄橋の変化に富んだ急な登りが小普賢岳、奥駈道合流点まで続きます。 そして、奥駈道を少し登ると大普賢岳山頂です。 山頂では何時の間にかガスが取れ青空が広がり、多くの人が絶景を楽しんで賑わっています。 何時も休憩する岩頭まで下がり、私も20分程展望を楽しみました。 岩場の急坂を下ると、緩やかなアップ・ダウンでブナが黄葉した奥駈道を進み水太覗に到着です。 お天気最高・展望良好・風はすこぶる心地よく。 何時までも景色を眺めて昼寝でもしたくなりました。
稜線を南に進み弥勒岳の山頂の西側を巻いて、シャクナゲの群生地を過ぎます。 国見岳山頂はわかりませんでした。(らしき所には、ここは国見岳の山頂ではありませんと言うご丁寧な案内が木にぶら下っていました。) 道は左に折れクサリの付いた岩場を下り巨岩の上に出ます。薩摩転げと言う岩場らしい。 クサリを頼りに進み、薄暗い大岩に苔が付いた森に入ります。大きな盆栽の中に入り込んだ感じがしました。 直ぐ明るい平地に出て稚児泊ノ宿跡、七ツ池の案内板を過ぎ七曜岳に辿り着きます。 ここまでの奥駈道で見通しの利く稜線からは、大普賢・小普賢岳の鋭く尖った鋸歯状の山容や和佐又山までの絶景が望めます。 七曜岳の山頂は岩峰で、ここも素晴らしい眺めのビューポイントです。 狭い山頂で行者還トンネル西口から奥駈道を歩かれて来た年配のグループや周回コースを歩かれているご夫婦と楽しくお話ししました。 山頂から少し下がると、奥駈道と分かれ無双洞への下りが続きます。 自然林の中、どんどん高度を下げます。不明瞭な所もありますが、テープが所々にあって迷うことはありませんでした。 谷の水の音が聞えてからでも無双洞は、まだまだ下のようです。 えェ〜、こんな所まで下がるのと思い、だんだん不安になりましたが、急な岩肌を流れる沢が見えて無双洞に着きました。 洞窟からの湧水を口の含んでみる、冷たくて美味しいです。 湧水でカップメンとおにぎりの昼食、食後のコーヒーも湧水で頂きました。
十分な休憩を取って、沢の対岸に渡り水簾滝を見て、少し歩くと水太谷(涸谷)を斜めに横切る。ここから急登の始まりです。 岩・木・根っこを持って登り、垂直に見える岩壁をクサリと鉄アングルで登ります。やっとの思いで底無井戸に辿り着きました。 字のとおり底が見えない穴がポッカリ開いた井戸?案内板がなければ通り過ぎているかも知れません ここから先は緩やかな道で鷲ノ窟から下りて来る岩本新道と合流します 黄葉がまだ早いですが、気持ちのいいブナ林が和佐又のコルまで続いています。 和佐又山には登らず、ヒュッテに帰って来ました。 無双洞周回は上級コースらしいですが、気候が良かったのと素晴らしい景色の中を歩く事が出来たので疲労感がありませんでした。 思っていたより早く周れキャンプ場でノンビリ過しました。
絶景と記念写真・黄紅葉 和佐又山キャンプ場 大台ケ原 10月! |