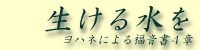 |
(第1回)
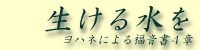 |
|
説教日:2000年9月10日 |
|
サマリヤ人の女性が町を出てから、ヤコブの井戸の方を見ますと、いつもは人気のない井戸の傍らに人がいました。一瞬いやな思いになりましたが、どうやらそれは旅人のようでした。旅人なら自分の素性を知っているわけではないので安心です。それに、わざわざ町の外まで水を汲みに来たのに、汲んで帰らないというわけにもいきません。 それで井戸まで行って見ますと、そこには旅の疲れで休んでいるユダヤ人がいました。暑い中を旅をしてきて、やっと井戸のある所にまで来てみると、井戸は深く、汲むものもなかったので困っている様子でした。案の定、その人は、「わたしに水を飲ませてください。」と言いました。 9節では、 そのサマリヤの女は言った。「あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリヤの女の私に、飲み水をお求めになるのですか。」── ユダヤ人はサマリヤ人とつきあいをしなかったからである。── と言われています。 その当時、「ユダヤ人はサマリヤ人とつきあいをしなかった」のです。その上、ユダヤ教の律法の教師であるラビたちの規定を記す『ミシュナ』には、サマリヤ人の女性は、常に「月のさわりの状態」にあるのと同じように汚れており、それに触れる者も汚れるというような教えが記されています。ですから、ユダヤ人の男性が、サマリヤ人の女性に声をかけるということは、考えられないことでした。 それでも、イエス・キリストがサマリヤ人の女性に声をおかけになったのは、イエス・キリストには、ユダヤ人に一般的であっただけでなく、ラビの教えにも見られるサマリヤ人に対する差別や偏見がまったくなかったからです。 神さまには、人種はもちろん、容姿やさまざまなハンディ、さらには社会的な地位など、本人の責任ではないことに対する差別や偏見がありません。そのような差別や偏見は罪の下にある人間が生み出しているものです。 それで、神さまは御子イエス・キリストの贖いの御業を通して、そのような差別や偏見を私たちの間からも取り除いてくださいました。ガラテヤ人への手紙3章26節〜28節に、 あなたがたはみな、キリスト・イエスに対する信仰によって、神の子どもです。バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだからです。 と記されているとおりです。 また、ヨハネの福音書9章1節〜3節には、 またイエスは道の途中で、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問して言った。「先生。彼が盲目に生まれついたのは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。その両親ですか。」イエスは答えられた。「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざがこの人に現われるためです。 ・・・・ 」 ということが記されています。 その当時の社会では、今日の日本の社会と同じように、因果応報の原理に従って物事の判断がなされました。それで、人が病気などの不幸に見舞われるのは、その人の罪に対する刑罰である、と考えられていました。弟子たちは、そのような考え方を受け入れた上で、 先生。彼が盲目に生まれついたのは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。その両親ですか。 と質問をしています。── この人が生まれつき目が見えないのは、罪に対するさばきであるけれども、この人は実際に罪を犯す前から目が見えなかった。それでは、それは誰の罪によるのかと問いかけているわけです。 それに対してイエス・キリストは、その人のことを因果応報の原理で判断することを否定されました。どんな人でも、さまざまな痛みと苦しみを背負っています。それは、人類が罪を犯して堕落したことによっています。しかし、ある人が他の人とは違う特別な苦しみを背負っているのは、必ずしも、その人の特定の罪の結果ではないし、その人が他の人より罪が深いということでもないのです。 そればかりか、イエス・キリストは、そのような苦しみにおいてこそ、「神のわざ」がその人に現われるようになると言われました。その「神のわざ」とは、もちろん、贖い主である御子イエス・キリストをとおしてなされる「神のわざ」です。事実、この生まれつき目が見えない人は、そこにいた誰よりも確かに、イエス・キリストが神さまから遣わされた贖い主であることを知るようになりました。 このように、イエス・キリストは、罪によって縛られている人間が生み出した人種や身分やさまざまなハンディに対する差別や偏見からまったく自由な方です。むしろ、しばしば、そのようなハンディをとおして、その人に近づいてくださり、ご自身をその人に示してくださいます。 そればかりではありません。先ほど引用しました18節に記されている、 私には夫がないというのは、もっともです。あなたには夫が五人あったが、今あなたといっしょにいるのは、あなたの夫ではないからです。あなたが言ったことはほんとうです。 というイエス・キリストの言葉から分かりますように、イエス・キリストは、この女性がサマリヤの人々からも非難されるような生活をしていることをご存知です。そのことを知っておられて、この女性に声をかけておられます。 ですから、イエス・キリストは、本人の責任ではなく、本人にはどうすることもできない人種の違いやさまざまなハンディに対する差別や偏見からまったく自由であられただけではありません。このサマリヤ人の女性のように、本人の責任で道を踏み外し、人から後ろ指を指される状態にはまり込んでしまっている人にも、真実に向き合ってくださいます。そして、初めに言いましたように、本当に大切なことを惜しむことなく教えてくださいます。 私たちは、しばしば、罪を犯してしまいます。そして、自分がこんな状態になってしまったのは自分自身の責任であり、自分は責められて当然であると感じます。そのために、このような自分は、とても神さまに受け入れていただくことはできないと感じて、絶望的な思いになることもあります。 しかし、このサマリヤ人の女性に語りかけてくださったイエス・キリストを思いだしてください。これは、イエス・キリストの例外的なお姿ではありません。これがイエス・キリストのお姿であれば、イエス・キリストは自分自身の罪に苦しんでいる人に近くいてくださいます。 その意味では、自分がちゃんとやっているということを心秘かに自任し、そのことから自分は神さまに近いと感じている人よりも、自分自身の罪に苦しんで、自分が神さまにふさわしくないことを悲しんでいる人の方が、神さまの近くにいます。そのことを示す例は、ルカの福音書18章9節〜14節に記されているイエス・キリストのたとえです。そこには、 自分を義人だと自任し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのようなたとえを話された。「ふたりの人が、祈るために宮に上った。ひとりはパリサイ人で、もうひとりは取税人であった。パリサイ人は、立って、心の中でこんな祈りをした。『神よ。私はほかの人々のようにゆする者、不正な者、姦淫する者ではなく、ことにこの取税人のようではないことを、感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげております。』ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。」 と記されています。 しかし、それは、その人が神さまに近づいているというよりは、イエス・キリストが、その人に近づいてくださっているからです。 主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、 たましいの砕かれた者を救われる。 詩篇34篇18節 考えてみますと、イエス・キリストがそのような方であることは、今日この記事を読んでいる私たちに分かることです。その時のサマリヤ人の女性には、このことは、まったく分からなかったはずです。 ヨハネの福音書4章6節では、 イエスは旅の疲れで、井戸のかたわらに腰をおろしておられた。 と述べられています。そのようなイエス・キリストのお姿を見ている彼女としては、この人はよほど疲れて、喉が渇いて困っているから、自分のようなサマリヤ人の女性に声をかけてきたのだ、と考えたに違いありません。 それは、イエス・キリストに対するサマリヤ人の女性の無理解によっています。しかし、そのことで、イエス・キリストが怒ってその女性を退けてしまわれたというようなことはありません。かえって、そのような彼女の無理解が生かされていると思われる節があります。 どういうことかと言いますと、お疲れになって井戸の傍らに座っておられるイエス・キリストのお姿を見たサマリヤ人の女性は、自分が優位な立場にあることを感じて、一種の余裕が持てたと考えられます。自分が、人目を避けて、真っ昼間に町の外まで水を汲みに出てきたことは、この疲れのあまり座り込んでいる一人の旅人を前にして、すっかり忘れることができたことでしょう。そうであるからこそ、 あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリヤの女の私に、飲み水をお求めになるのですか。 というような、皮肉をこめた質問をすることができたのであると考えられます。 言い換えますと、このサマリヤ人の女性は、イエス・キリストの、疲れて井戸の傍らに座っておられ、サマリヤ人の女性である自分にさえ水を求めて声をかけてきたお姿に接したので、心を開いて、自由にイエス・キリストとお話しすることができたのです。 このすべてのことの中に、栄光の主であるイエス・キリストの導きの御手が働いています。イエス・キリストは、永遠の神の御子としての権威をこのような形で発揮して、このサマリヤ人の女性を導いてくださっておられます。 具体的に見てみますと、3節、4節では、 主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。しかし、サマリヤを通って行かなければならなかった。 と言われています。少なくともそのことの目的の一つは、このサマリヤ人の女性と出会うためでした。 また、8節で、 弟子たちは食物を買いに、町へ出かけていた。 と言われているように、弟子たち全員を町に送り出されたことも、イエス・キリストがお一人でこの女性とお会いになるためでした。イエス・キリストが弟子たちに囲まれておられるのを見たとしたら、この女性はイエス・キリストに水を差し出したとしても、イエス・キリストと言葉も交わすことはなかったことでしょう。 そして、今お話ししましたように、イエス・キリストがお一人で「旅の疲れで、井戸のかたわらに腰をおろしておられた」ことも、このサマリヤ人の女性の心を開いて、彼女にご自身を示してくださるためだったのです。 そうであるからと言って、この時、イエス・キリストがわざとらしい「演技」をしておられたのではありません。イエス・キリストは、その旅の中で本当にお疲れになり、飢えと渇きで弱っておられたので、食料を買うために、弟子たちを町にお遣わしになり、ご自身は、井戸の傍らに座っておられたのです。同時に、永遠の神の御子として、その、いわば、「惨めなお姿」をお用いになって、サマリヤ人の女性にご自身をお示しになりました。 このことの中に、ヨハネの福音書1章14節で、 ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。 とあかしされている、人の性質を取って来てくださった永遠の神の御子の恵みとまことに満ちた栄光が見て取れます。 イエス・キリストは、私たちと同じ人の性質をお取りになりました。そして、私たちと同じように、飢えと渇きを経験され、さまざまな、痛みと悲しみを味わわれました。 そればかりでなく、預言者イザヤによって、 彼には、私たちが見とれるような姿もなく、 輝きもなく、 私たちが慕うような見ばえもない。 彼はさげすまれ、人々からのけ者にされ、 悲しみの人で病を知っていた。 人が顔をそむけるほどさげすまれ、 私たちも彼を尊ばなかった。 イザヤ書53章2節、3節 とあかしされているように、人から、どのようにでも誤解されるような立場に立たれました。 このサマリヤ人の女性の場合にも、彼女の現実を知っておられるイエス・キリストは、彼女が人目を忍んで出てくる時間に、町の外にある井戸の傍らに疲れて座り込んでいる人であられました。そのお姿を見たサマリヤ人の女性が、優位な立場に立ったと感じて、ご自身と自由に会話することができるまでにへりくだっておられました。しかも、それは、決して「演技」ではありませんでした。 そのようなイエス・キリストのお姿は、ご自身が十字架におつきになったことにおいて、最もはっきりと現われてきました。マルコの福音書15章29節〜32節には、 道を行く人々は、頭を振りながらイエスをののしって言った。「おお、神殿を打ちこわして3日で建てる人よ。十字架から降りて来て、自分を救ってみろ。」また、祭司長たちも同じように、律法学者たちといっしょになって、イエスをあざけって言った。「他人は救ったが、自分は救えない。キリスト、イスラエルの王さま。たった今、十字架から降りてもらおうか。われわれは、それを見たら信じるから。」また、イエスといっしょに十字架につけられた者たちもイエスをののしった。 と記されています。 イエス・キリストは、このような「惨めなお姿」を人々の前にさらしておられます。今日も、教会は、このようなイエス・キリストのお姿を隠しません。このようなイエス・キリストのお姿を見る人は、それこそ、イエス・キリストに向かって何とでも言えますし、イエス・キリストを踏みつけることさえできます。 もしイエス・キリストのお姿が、まばゆいばかりの栄光のお姿として示されたとしたら、すべての人がそのまばゆさに打たれて、恐れることでしょう。誰もイエス・キリストに楯突く人はいなくなります。しかし、その一方で、あえてイエス・キリストに何かを尋ねる人もいなくなるでしょう。ただ、イエス・キリストがまばゆいばかりの栄光の主であるということが分かるだけで、イエス・キリストがどなたであるかを、また、その愛と恵みを、本当に知ることはできないことでしょう。すべての人が、その愛と恵みを信じてイエス・キリストに従うのではなく、恐れから、イエス・キリストに従うようになることでしょう。 私たちも、サマリヤ人の女性と同じです。私たちもイエス・キリストの「惨めなお姿」に接したので、恐れなく、イエス・キリストの御許に行って教えを受けたり、疑問をぶっつけたり、駄々をこねたりすることができたのです。 そのことの中で、やがて、サマリヤ人の女性がイエス・キリストがどなたであるかを悟ったように、私たちも、人々から捨てられ、十字架につけられて殺されたイエス・キリストが神さまから遣わされた贖い主であることを悟りました。そして、イエス・キリストが、 もしあなたが神の賜物を知り、また、あなたに水を飲ませてくれと言う者がだれであるかを知っていたなら、あなたのほうでその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。 と言われたように、私たちも、イエス・キリストから「生ける水」をいただいて飲むものとされています。 あなたがたは、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなられました。それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富む者となるためです。 コリント人への手紙第二・8章9節
|
|
|
||