ぼくの家の横には広い空き地がある。夕方になると枯れかけたねこじゃらしが風にゆれる。見ていると昼間の暑さを忘れさせてくれる。黄色いつぼみをつけたまつよい草もゆらゆらと出番を待っているようだ。まつよい草は夕方から次の日の朝にかけて咲く花で、ぼくがとりわけ好きな花だ。
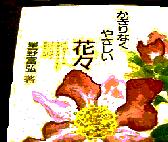
この花との出会いは三年前の夏休みだ。前に住んでいたマンションの裏にまつよい草があった。夕方上から見たその様子は黄色く光る星のようで、きらきらしてぼくに元気をくれるようだった。じっとその花をながめていると、何か話しかけてくれるような気持ちになった。
一学期の道徳で出会った星野富弘さんならまつよい草をどんなふうに書くのだろうか。またどんな詩をよむのだろうか。
大好きな体操をして、先生になってわずか二ヶ月で不自由な体になってしまった星野さんをぼくは最初、かわいそうだ、気の毒だなあと思った。けがをして二年が過ぎた時、首から下は不自由だけれども、生きている自分を見つめる時期がきたのだ。その時の気持ちを星野さんは、「自分から積極的に生きようとする気持ちはありませんでした。」と述べている。普通の健康な体でいるぼくは、何となく生かされていて、無意識に明日を迎えようとしている。口にペンをくわえて字を書くことは星野さんにとって大きな挑戦だったにちがいない。首の力が弱っていたので、並大抵の努力ではなかったと思う。最後まであきらめないという持ち前の根性が星野さんをそうさせたのだ。一つ一つの基礎となる技を毎日努力して、それの積み重ねが器械体操の美しい技につながることを自ら、経験していた星野さんはこの時、輝いているように見えた。努力を積み重ねて一つの挑戦をしていくことのすばらしさを星野さんから学ぶことができた。
星野さんは家族や病院の人たちに支えられてきた。特にお母さんへの、ひとことでは言えない感謝の気持ちを託した作品『ぺんぺん草』は星野さんのまっすぐな心をあらわしているようだ。絵や詩が書けるという喜びとそれを見てくれる人たちの姿を見て、希望や目標が持てるようになったのだ。
ぼくは今、合唱コンクールのピアノ伴奏の曲に少し行き詰まっている。指が短いぼくは、オクターブが続くところになるとどうしても止まってしまって、自分がいやになってしまうことさえある。「できないからといって放っておいても前進はしないよ。」と母にこの間も言われたところだ。自分にくやしくて涙が出た。
夏休みももう終わろうとしている。黄色く光るまつよい草が風にゆれながらがんばれといっている。目標に向かって努力しよう。それが達成できた時、喜びを味わうためにも。
未来に向かうあなたたちへ(母)
日常生活の中で、なにげなく発した私の言葉に、後悔や相手を傷つけたのではないかとはっとしてしまうことがある。私は心が病んでしまったり、自分を見失いかけたりしている時、星野富弘さんの詩画集を開くことがある。『鈴のなる道』の中にーー私の口から出たことばをいちばん近くで聞くのは私の耳なのだからーーという一節がある。白いくちなしの花が描かれた詩だ。この一節を読んでいると心を凛と落ち着かせることができ、私の心を包み込んでくれるような気持ちになれる。
この詩が授業で取り上げられたことがきっかけでこの夏、息子と再び『かぎりなくやさしい花々』を読むことにした。
三年前の夏、息子は引越やビアノのコンクールなどが重なり、心身ともに少し疲れていた。そんな時元気とやさしさそして安らぎを与えてくれたのが野に咲くまつよい草だった。あの花は息子に何を語ってくれたのだろうか。
『ア』から始まった星野さんの可能性への挑戦の旅。息子の胸にその生き方がどう映ったのだろう。
星野さんの描く花の中には枯れかけているものがあったり、虫食いの葉があったりして自然の姿を見ることができる。また詩の言葉には村の生活は好きでなかったのに、故郷の空や生き物、すべての空気が満ち溢れている。まさか人前では歌わないと思っていたお母さんが歌ったことや嫌いだったどくだみの花に新しい自分を見つけられたことなど長い病院生活の中から心を見つめ直し、今まで全然見えなかった人やものの本来の姿に気づいていく星野さん。読んでいくうちに私自身も忘れかけていた心を取り戻せそうになる。
子どもたちは今、希望や目標に向けて翼を広げている。疲れたときは羽を休めていいよ。
お母さんができることは前向きに挑戦しているあなたたちの姿を見守り続けることだけなのだから。