ぼくは、夏休みにお菓子や料理を作った。手巻きずし・パン・わらびもちに挑戦してみた。元々食べることも好きなぼくは作ることにも興味があって時々母の手伝いをしていた。手巻きずしは、すしめしの砂糖、酢のバランス、そして塩加減がポイントで家族のみんなが甘めが好きなので、砂糖を少し多めにした。四合炊いて作ったすしめしをあっという間にたいらげてしまった。
ぼくはどちらかといえば、ようかんやきんつばは甘さだけが強調されているようで苦手である。それなのにわらびもちはよく食べる。市販のものはきな粉が少なくて物足りなく感じていた。例の祖母からの箱にこのわらびもちの粉ときな粉が入っていたのだ。早速作ることにした。わらびもちの粉と水を木じゃくしで混ぜながら、火を入れていくのだが、意外と力が必要で透明になるにはかなり時間がかかった。きな粉も砂糖と塩を入れて完成した。父も兄もおいしいと言ってくれてがんばったかいがあってうれしかった。

ある日、パン作りをしていた母が、この時期は発酵しすぎるのと言った。ぼくはパンの発酵と温度の関係やパン作りの材料である砂糖の量と発酵との関係を知りたくなって自由研究の課題にした。発酵とは、イーストと呼ばれる微生物が働いて、食べ物の中に含まれる糖分を炭酸ガス(二酸化炭素)と、アルコールに変えることだ。実験でも温度が三十度位が一番発酵に適した温度だということがわかった。簡単にいえば、パンは炭酸ガスでふくらんだ生地を焼いたものなのだ。また、砂糖の量と発酵の関係を調べる実験では、一定の量のイースト菌に砂糖の量を変えて混ぜて反応をみた。この実験で砂糖はイースト菌の活動を助け、パンがうまく発酵するには砂糖の量も少なすぎたり、多すぎたりしてもいけないことがわかった。ぼくは今まで、砂糖はパンにほんのりとした甘さをつけるために入れる位に思っていたが、こんなものすごい働きがあることを知ってとても驚いた。それに砂糖は、食品の水分をしっかりかかえ込んで細菌を繁殖しにくくすることやパンなどのこんがりとした焼き色を付ける働きもあることがわかった。以前、家庭科の授業でりんごジャムを作った。この時僕はゼラチンを入れてないのになぜゼリーのよ
うに固まるのが不思議だった。果肉をゼリーのようにするにはペクチン、酸、糖が必要なことを知った。
祖母の送ってくれた箱の中に変わったものがあった。透明のかたまりの物が入った袋だ。袋には『氷砂糖』と書かれていた。確かに氷のように見えるし、大きな結晶のような形だ。
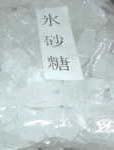
ぼくは祖母に色々なものを送ってくれたお礼とまたどうしてこのようなものを送ってくれたのかを尋ねたくてすぐに電話をしてみた。祖母に尋ねると、「あれは疲れている時にいいからね。非常用の袋に入れておくといいのよ。」と教えてくれた。ぼくは『氷砂糖』を一粒口に入れた。甘くて硬い。なかなか溶けない。『氷砂糖』のことをインターネットで調べてみた。『氷砂糖』はぼくがすしめしやきな粉に混ぜた砂糖と同じ原料でさとうきびやてん菜から作られている。砂糖を溶かしてろ過、濃縮などの工程を経てあの大きな結晶になるという。疲労や夏バテの時エネルギー補給になり、そのまま食べてもいいし、梅酒や煮物などのゆっくり溶かして味をしみ込ましていくものにいいらしい。母はお菓子を作る時は上白糖やグラニュー糖、料理に入れる時は上白糖か三温糖を使うといって色々見せてくれた。溶け方や味が微妙に違うので使い分けていると言っていた。原料が同じでも、形だけでなく用途も違うとは知らなかった。
毎日知らず知らずのうちにぼくたちが口にしている砂糖。昔の人の知恵と工夫で砂糖を利用して作り上げられてきた食品が多くあることもわかった。以外と知られていない様々な砂糖の働きを知って驚くことばかりだった。ぼくは日ごろ食べている砂糖が沖縄のさとうきびや北海道の寒い土地で作られているてん菜からできていることを忘れてはいけないと思った。ぼくはこの夏、自由研究や料理作りをして砂糖を今まで以上に貴重なものと再認識することができた。