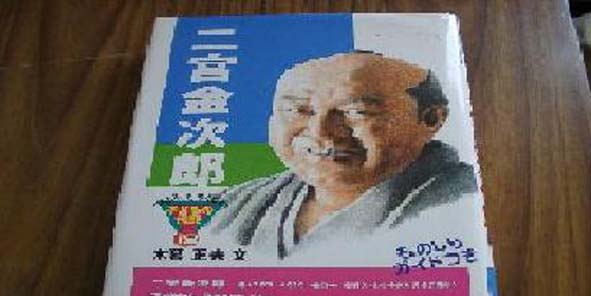
みんな、この石像の前で走り回ったり、学校の登下校の時、横をなにげなく通り過ぎたりしている。きっとみんな気を付けてはいないけれど、その像の名前が二宮金次郎ということは知っているだろう。でも、どんなことをした人なのかとなるとぼくは何も知らなかった。図書館の伝記コーナーでぐうぜん出会ったのが『二宮金次郎』の伝記だった。この本は、ぼくに人の生き方や考え方、それに伝記の楽しみ方を教えてくれた。
この本の表紙には大人のなった二宮金次郎のさし絵がある。読み始めてみると身長182センチメートル、体重94キログラム、わらじの大きさはなんと28センチメートルという大きい人だったことがわかった。石像の金次郎が細く小がらなので少しおどろいた。このからだの大きさとじょうぶさが、農民として役立ったことの1つになったにちがいない。また、この伝記は前からでも後ろからでも読めるようになっていた。ものしりガイドから読むと、クイズや写真があり、楽しく読むことができた。
金次郎が生きた時代は江戸時代後半だ。1学期の社会で、江戸時代のきびしい身分制度のことを学んだ。農民は藩に収穫の半分ほども年貢として納めなければいけない、五公公民というきまりがあった。だからききんなどが起きて、秋にお米が取れないということのなると農民は苦しくなる。金次郎のお父さんのゆい言の不公平なますを何とかしてほしいと言う言葉からも、きびしい年貢のことがよくわかった。なぜ、こんな農民にとってきびしい時代を、金次郎は力強く、人にはやさしく生き続けられたのだろうか。
ぼくは金次郎がお父さんのえいきょうをすごく受けたのだなあと思った。困っている人を見ると、自分のところが困ってでも何とかしてあげたいという、やさしいけれど、お人よしすぎる金次郎の父。「農民だって学問をして、さむらいにものが言えるようになれ」といって本を読むことを進めてくれた父。金次郎は単に人にお金や田んぼを貸すだけでなく、論語から学んだ『五常』の考えを広めた。それは、余裕のある人が困っている人を助け、借りた人はきちんと返せるよう努力し約束を守るという教えだ。五常講のおかげで多くの人が助かったのだ。
金次郎は武士にとりたてられても、農民の心を忘れなかった。それは生まれ故郷の川のはんらん、きびしい年貢の取り立て、ききんのつらさを経験したからだ。最後まで自然を見つめ、自分の分を知って働いた。
ぼくは、『小さなことでもそれが積みかさなれば、大きなみのりになる。』という言葉が心に残った。これは今のぼくたちにもつながると思う。最初は無理だと思っていても、こつこつ努力すればいつかは達成できると言うことだ。