![]()
このコーナーに掲載している新聞記事はすべて当該新聞社の掲載許可を受けたものです。
快諾くださった記者・新聞社のみなさま心から感謝申し上げます。

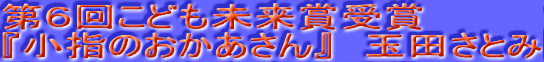 |
読売新聞 2003年2月16日(日)付
【第6回こども未来賞 財団賞に東京・大田の玉田さん】
| ◆ろう者の二男の成長描く 子育てにまつわる様々なエピソードを紹介する「第六回こども未来賞」(こども未来財団、読売新聞社主催)の受賞者が決まり、都内では大田区大森東の玉田さとみさん(40)の「小指のおかあさん」が、こども未来財団賞に輝いた。また、中野区東中野の小林純子さん(39)の「さようなら、魔法の人」が佳作に選ばれた。玉田さんに受賞の喜びを聞いた。(玉田さんの作品は29面に掲載) 「小指のおかあさん」は、耳が聞こえない二男・宙(ひろ)君(5)の子育てを通じて感じた思いを綴った作品。小指を立てて「おかあさん」と呼ぶ手話を懸命に試みる宙君のしぐさが、タイトルになった。 宙君の耳が聞こえないと分かったのは一歳九か月の時だ。当初はショックだったが、本やインターネットに情報を求め、ろうの女性を手話の家庭教師に招いたことで、ろう者に対する見方が変わった。 女性が語る日本手話(ろう者が使う手話で、日本語とは異なった文法を持つ言語)は、玉田さんにとっては未知のもの。その言語で女性は「聞こえないことは個性」と語り、ろう者としての誇りを持って生きていると繰り返した。「私の子どももこんな風に育ってくれたら」と感じたという。 「耳が聞こえないのは『かわいそう』ではなく、聞こえない人には当たり前のこと。自分の価値観でよかれと思っても、相手に良いとは限らないのです」 国内のろう学校で行われている「口話教育」では、子どもたちは唇の動きから読みとり、発声する訓練を受ける。 しかしテレビのインタビューなどで子どもたちが「訓練はつらかったけれど、お母さんが喜ぶ顔を見たいから我慢した」と語るのを聞き、聞こえる側の価値観を押しつけているようで胸が痛んだ。 「聞こえないことをあるがままに受け入れ、日本手話で子どもを育てたい」。同じ思いを抱く親たちと二〇〇〇年、「全国ろう児をもつ親の会」を設立。ろう者が日本手話で教える学校づくりを目指して活動を続けている。 午後の日差しが注ぐ部屋で、長男の海士(かいと)君(7)と宙君がブロック遊びをしていた。二人は手話で笑い、けんかもする。「私の知らない言語(手話)をどんどん覚えていくのが誇らしくもあるんです」と言って、玉田さんはほほ笑んだ。 |
| 二男は“目の人”です。生まれたばかりの二男の写真はどれも二重まぶたのどんぐり目。よく乳を飲み、よく泣き、よく眠る。男の子にしては、手のかからない赤ん坊でした。 二男は耳が聞こえません。とりたてて不自由とか不便ということはなく、ただ聞こえないだけ。違うところは、日本語ではなく手話で話すということです。そんな当たり前のことに気づくのにずいぶん時間がかかりました。 初めて聞こえないとわかったときは、身も心もよじれんばかりに泣きました。「子供の前で泣いてはいけない」と思いながら、無邪気に遊ぶ息子の姿にこらえきれないときもありました。アニメに夢中になっていた二男が振り向くと、いつもと違う母の顔。まだ二歳にならない二男は、不思議そうに母の顔をのぞき込み、小さな手でほおの涙をふき取ります。ところが、涙は止まりません。息子は大急ぎでティッシュを探し、母の目からあふれ出る涙を一生懸命ふき取ります。 その傍らに、何も言わずじっと見つめる長男がいました。その表情を見たときに私はハッとしたのです。「お母さん、どうして泣いてるの? 弟のせい? 弟はお母さんを悲しませる子なの?」と言っているような気がしました。「違う、何か違う!」。あの日を境に、私の目はすっかり乾きました。あらゆる情報を求めて昼間は本屋と図書館を駆け回り、夜はパソコンとにらめっこです。そして、意外な言葉に出会ったのです。 「生まれたときから聞こえないから、聞こえないことがフツー。手話で自由に話ができるし、不幸でも不便でもない。だから、ひとつの個性として認めて欲しい」 正直言って驚きました。でも、何だかすんなり理解できました。 それから二か月。 二男の小さな手が話し始めました。 「おかし、ちょうだい」 「チョコレート好き」 「いーっぱい」 「ダメー!」 話しはじめの少ない単語の中に「ダメー」を見たときは、「しまった!」と思いました。「○○しちゃダメ」「△△はダメ」という私の“ダメダメ攻撃”の裏返しです。ダメという前に「○○すると××になるよね。どう思う?」と聞かなきゃいけない。わかってるんだけど、忙しい子育ての中ではなかなか出来ないっ。何しろ男兄弟は年齢に関係なく、朝から【起きる→ケンカ→遊び→ケンカ→遊び→ケンカ→寝る】というのが日常。母は「ナニやってんの! 何回言ったらわかんの! ダメでしょ!」とどなってしまう毎日なのです。 人さし指で軽くほおに触れ、 親指を立てると「お父さん」。 小指を立てると「お母さん」。 二男はすぐに「お父さん」と呼ぶようになりました。もちろん主人は大喜び。でも、なかなか「お母さん」と呼んでくれません。ある時、部屋の隅で二男がモゾモゾしています。右手で左手の小指を立てているのです。二歳になったばかりの息子にとって小指を立てる動作はまだ難しいのです。添えている右手を離すと、左手の小指はすぐに曲がってしまいます。何度か繰り返しているうちに、二男は左手の小指を右手でギュッとつかんでほおに当て、そのまま私のところに走ってきました。 「おかあさん!」 小さな手で呼んでくれた「おかあさん」はどんな大きな声よりも、どんな流ちょうな日本語よりも、いとおしく頼もしく思えました。そして、二男の手話は瞬く間に上達していったのです。 このころ「弟のために手話を覚える」と、家族の中で一番張り切っていた長男の様子がおかしくなってきました。「僕も聞こえなければよかった……」とつぶやきます。弟に両親を取られたような寂しさがあったのでしょう。 主人と相談した結果、「長男と母だけの時間」を作ることにしました。公園に行ったり、本を読んだり、映画を見たり。一年以上かけてかたくなになった長男の心は、一年たった今、ようやく溶けはじめ、自分の意志で弟と向き合うようになりました。 長男が生まれて七年、二男が生まれてから四年。私は、この子たちから“人として一番大切なこと”を教わりました。家族であっても、相手を思いやる心がないと、その気持ちを理解することはできない。相手を知って、相手を認めた上で、人としての関係が成り立つのだということ。 今になって実家の母が言います。「あの時、おまえは息子のことがふびんだったかもしれないけど、私には孫だけでなく“おまえ”もふびんだったのよ」と。ここにも計りきれない親心がありました。 「おばあちゃんに千円もらっちゃった。僕お金持ちー。お母さんうらやましい?」と少しだけ大きくなった二男の手が舞います。「僕なんか、一万円も貯金があるんだぞ」と少年になりかけている長男の手が揺れると、「お兄ちゃん、ずるーい」と、またまたケンカの始まりです。これから先、この子たちがどんなことを体験させてくれるのか? ちょっと怖いけど、楽しみです。 |


※無断転載禁止 Copyright(c)2000 全国ろう児をもつ親の会